目次
本記事では、アンケート調査を始めたいけれど、何から手をつければ良いか分からない方のために、基礎知識から実践的な進め方、成功させるためのポイントまでを網羅的に解説します。アンケートと一口に言っても、アンケートを実施する目的に応じて、最適な手法や種類があります。課題解決に用いられる手段の一つとして直接ターゲットの声を集めることが出来るアンケートについて基礎を学びましょう。

アンケート調査とは?目的やメリット
アンケート調査とは、複数人から特定のテーマに関する意見や行動などのデータを収集する方法です。現状把握、仮説検証、意思決定の支援など、さまざまな目的で活用されます。
アンケート調査で収集する情報は、定量と定性的なデータの主に2つあります。定量的なデータとは、主に数値化できるデータで選択肢による回答や、5段階評価で回答できる質問などを指します。一方で定性的なデータとは、数値化できない回答者からの自由なコメントなどのデータを取得することであり、必要に応じて使い分けてデータを取得します。
アンケート調査で得られるデータは、回答者の意見や考えを直接尋ねることから「アスキングデータ(Asking Data)」と呼ばれます。これにより、「なぜその商品を購入したのか」「どのような点に不満があるのか」といった、行動の背景にある動機やインサイトを深く探ることができます。
一方で、POSデータやウェブサイトのアクセスログなど、実際の行動履歴から得られるデータを「アクチュアルデータ(Actual Data)」と呼びます。アクチュアルデータからは「何が売れたか」「どのページがよく見られているか」といった事実を把握できますが、その理由までは分かりません。
アンケート調査(アスキングデータ)とアクチュアルデータを組み合わせることで、「何が起こったか(アクチュアルデータ)」と「なぜそれが起こったか(アスキングデータ)」の両方を理解することができ、より精度の高いマーケティング戦略や意思決定が可能になります。
アンケート調査の主なメリットは、以下の通りです。
■比較的低コストで手軽に実施できる:
Webアンケートツールなどを活用すれば、時間やコストを抑えられます。
■客観的なデータを取得できる:
数値データ(定量データ)として収集することで、営業やマーケティング活動の根拠にできます。
■幅広い層から意見を集められる:
ターゲット層のニーズを直接探ることが可能です。
総務省が公開している「アンケート調査」に関する資料も併せてご覧ください。
アンケート調査で収集する情報は、定量と定性的なデータの主に2つあります。定量的なデータとは、主に数値化できるデータで選択肢による回答や、5段階評価で回答できる質問などを指します。一方で定性的なデータとは、数値化できない回答者からの自由なコメントなどのデータを取得することであり、必要に応じて使い分けてデータを取得します。
アンケート調査で得られるデータは、回答者の意見や考えを直接尋ねることから「アスキングデータ(Asking Data)」と呼ばれます。これにより、「なぜその商品を購入したのか」「どのような点に不満があるのか」といった、行動の背景にある動機やインサイトを深く探ることができます。
一方で、POSデータやウェブサイトのアクセスログなど、実際の行動履歴から得られるデータを「アクチュアルデータ(Actual Data)」と呼びます。アクチュアルデータからは「何が売れたか」「どのページがよく見られているか」といった事実を把握できますが、その理由までは分かりません。
アンケート調査(アスキングデータ)とアクチュアルデータを組み合わせることで、「何が起こったか(アクチュアルデータ)」と「なぜそれが起こったか(アスキングデータ)」の両方を理解することができ、より精度の高いマーケティング戦略や意思決定が可能になります。
アンケート調査の主なメリットは、以下の通りです。
■比較的低コストで手軽に実施できる:
Webアンケートツールなどを活用すれば、時間やコストを抑えられます。
■客観的なデータを取得できる:
数値データ(定量データ)として収集することで、営業やマーケティング活動の根拠にできます。
■幅広い層から意見を集められる:
ターゲット層のニーズを直接探ることが可能です。
総務省が公開している「アンケート調査」に関する資料も併せてご覧ください。
-
様々な施策で有効活用できる!アンケート調査でデータを取得する
アンケート調査の種類【得られる示唆別】
アンケート調査の方法は大きく分けて2種類あり、「定量調査」と「定性調査」に分けられます。目的によって使い分けることが重要です。
定量調査:全体の傾向把握に役立つ
定量調査とは、調査対象から「数値で表現することができるデータ」を集計し統計的に分析する調査のことです。大規模なデータを扱うこともあって全体的な傾向を知りたいときに役立ちます。調査対象が多いときやエビデンスとする信頼度の高いデータを集めたいときなどは、定量調査を選びましょう。ネットリサーチなど、予め決められた選択肢から該当する回答を選択する形式のものが一般的です。
このほか市場規模の把握や顧客満足度調査、製品・サービスの評価、市場セグメンテーション、広告効果測定などにも定量調査が適しています。
このほか市場規模の把握や顧客満足度調査、製品・サービスの評価、市場セグメンテーション、広告効果測定などにも定量調査が適しています。
定性調査:改善点や深層心理の掘り下げに役立つ
定性調査とは、調査対象者から意見や感想など「数値では表現できないデータ」を回収し分析する調査のことです。企業側で見落としている問題点や改善点を発見することに適しており、対面でのインタビュー調査などで、質問の深堀りや回答者の表情を観察します。
ユーザー自身も気づかない不満点や、企業が見落としている改善要素を発見できるときもあります。このほか新製品のコンセプトテストや顧客体験(CX)・ユーザーエクスペリエンス(UX)の評価、顧客の購買行動の理解、ブランドイメージ調査、社会的テーマの理解などでも、定性調査は役立つでしょう。
ユーザー自身も気づかない不満点や、企業が見落としている改善要素を発見できるときもあります。このほか新製品のコンセプトテストや顧客体験(CX)・ユーザーエクスペリエンス(UX)の評価、顧客の購買行動の理解、ブランドイメージ調査、社会的テーマの理解などでも、定性調査は役立つでしょう。
-
定量・定性データどちらも取得出来る!サーベロイドに登録する
アンケート調査の種類【手法別】
アンケート調査の手法にはいくつか種類があるため、目的に合わせて使い分けることが大切です。
ここでは代表的な4つのアンケート調査の手法についてご紹介します。
ここでは代表的な4つのアンケート調査の手法についてご紹介します。
Web調査
インターネットを通して行う調査手法です。
主に、冒頭でご紹介した「定量調査」と呼ばれる「結果を数字で表すデータ」を収集する際によく使われます。
短時間で多くのデータを収集できるという特長があり、紙のアンケートよりも時間や人件費がかからないのでスムーズに調査が進みます。
昨今、Web調査の需要は大きくなっており、手軽にできるセルフ型のアンケートツール(自分でアンケートの設計〜集計まで実施するツール)も人気です。
セルフ型アンケートツール「サーベロイド」のサービスを確認する
主に、冒頭でご紹介した「定量調査」と呼ばれる「結果を数字で表すデータ」を収集する際によく使われます。
短時間で多くのデータを収集できるという特長があり、紙のアンケートよりも時間や人件費がかからないのでスムーズに調査が進みます。
昨今、Web調査の需要は大きくなっており、手軽にできるセルフ型のアンケートツール(自分でアンケートの設計〜集計まで実施するツール)も人気です。
セルフ型アンケートツール「サーベロイド」のサービスを確認する
会場調査(CLT)
指定の会場に対象者を集めて、直接アンケート(インタビュー)をする調査手法です。
自社商品を様々な見せ方で体験(試用、試飲、試食等)してもらい、評価をその場で得ることができます。
あいまいな回答に対して、深堀りして聴取をすることができるなど、知りたいことを正確に聴取することが可能かつ、対面なので回答者のリアルな表情や目線、行動等も見ることができます。
試用のほか、店舗の商品棚を再現した「模擬購買」テストなどを実施できる点も他にはない手法といえます。
自社商品を様々な見せ方で体験(試用、試飲、試食等)してもらい、評価をその場で得ることができます。
あいまいな回答に対して、深堀りして聴取をすることができるなど、知りたいことを正確に聴取することが可能かつ、対面なので回答者のリアルな表情や目線、行動等も見ることができます。
試用のほか、店舗の商品棚を再現した「模擬購買」テストなどを実施できる点も他にはない手法といえます。
郵送調査
特定の住所に質問紙を郵送し、返送してもらうことで回答を集める調査手法です。
Web調査ではアプローチできない属性の回答を得ることができます。
また、全国規模で広範囲に郵送できたり、特定の地域に絞っての郵送が比較的安価にできます。
懸念点は、回収率のコントロールが困難なこと、回収期間が長く結果が出るまでに時間がかかることです。
さらに、調査内容によっては回収率が伸びない場合もあります。
Web調査ではアプローチできない属性の回答を得ることができます。
また、全国規模で広範囲に郵送できたり、特定の地域に絞っての郵送が比較的安価にできます。
懸念点は、回収率のコントロールが困難なこと、回収期間が長く結果が出るまでに時間がかかることです。
さらに、調査内容によっては回収率が伸びない場合もあります。
街頭調査
調査員が街頭に出て、対象者を選別してその場で回答を得る手法です。
テレビや雑誌などのメディアでも積極的に行われている手法ですよね。
特定の地域や街などに限定でき、直接意見を聞けるという特長がある一方で、込み入った質問はなかなかできなかったり、場所の確保に手間と時間がかかったりする場合もあります。
テレビや雑誌などのメディアでも積極的に行われている手法ですよね。
特定の地域や街などに限定でき、直接意見を聞けるという特長がある一方で、込み入った質問はなかなかできなかったり、場所の確保に手間と時間がかかったりする場合もあります。
アンケート調査の種類【用途別】
用途別で分けたアンケート調査の種類には、「学術調査」や「海外調査」などがあります。それぞれ詳しく解説します。
学術調査
学術調査とはアカデミック調査やアカデミックリサーチとも呼ばれ、研究者や大学教授、学生などが学術研究のために行う調査です。調査結果や得られたデータを研究の論文や卒論、修士論文のほか、学会誌への投稿などに活用するために行われます。一般的なマーケティングリサーチと同様に、インターネット調査やグループインタビューなど、目的に応じた手法で実施します。
企業が行うマーケティングリサーチが社内秘とすることが多いのに対し、学術調査は論文や学会誌等で公開されることが多い点が特徴といえるでしょう。
サーベロイドの活用事例│学術調査を行いたい
企業が行うマーケティングリサーチが社内秘とすることが多いのに対し、学術調査は論文や学会誌等で公開されることが多い点が特徴といえるでしょう。
サーベロイドの活用事例│学術調査を行いたい
海外調査
海外調査とは外国で行う調査のことで、ビジネスのグローバル化やインバウンド対策、越境ECが活性化する中で、活用する企業や団体が増えてきています。国内調査と同様に、特定の国の消費者調査や海外における競合企業・商品の調査、自社商品・サービスの認知度調査、海外支社従業員満足度調査など、その内容は多岐に渡ります。
国内に比べモニター集めなどが難しいと思われがちですが、海外調査経験や海外モニター保有数も豊富な調査会社も多くあります。
▼関連記事
海外調査の基礎知識(海外調査とは!?)
国内に比べモニター集めなどが難しいと思われがちですが、海外調査経験や海外モニター保有数も豊富な調査会社も多くあります。
▼関連記事
海外調査の基礎知識(海外調査とは!?)
アンケート調査の種類【目的別】
アンケート調査は、マーケティングにかかわる意思決定をするために行われることが多く、集めたデータは企業内で分析され、製品やサービスの課題解決に利用されます。
ここでは、目的に合わせたアンケート調査の方法を3種類ご紹介します。
ここでは、目的に合わせたアンケート調査の方法を3種類ご紹介します。
ブランド・認知度調査
ブランド認知度調査とは、自社の製品やサービスがどのくらい市場に浸透していて、どのような評価やイメージを持たれているかを把握する調査です。競合がいる企業がほとんどの中、自社ブランドの認知状況やポジションを明確にすると、今後取り組むべき課題が見えてきます。
また、この調査を実施することで、企業と利用者間におけるギャップを知ることができ、現状を把握することができます。
刻々と変化する市場を追うために、認知度調査は定期的に実施することで成果が得られます。また、定量的なデータが必要なケースが多いので、調査手法としてはWeb調査が多く用いられます。
ブランド認知度調査のアンケート例はこちら
また、この調査を実施することで、企業と利用者間におけるギャップを知ることができ、現状を把握することができます。
刻々と変化する市場を追うために、認知度調査は定期的に実施することで成果が得られます。また、定量的なデータが必要なケースが多いので、調査手法としてはWeb調査が多く用いられます。
ブランド認知度調査のアンケート例はこちら
顧客満足度調査
自社の商品やサービスを利用した顧客に対して、満足度やリピート意向、意見等を聴取する調査です。
顧客満足度は企業の売り上げに深く結びつくため、課題解決に役立たせることができます。
顧客にとって期待値以上の製品もしくはサービスを提供した場合、リピートしてくれる確率が上がり、周りの人にお勧めしてくれたりするなど、自社にとってはかなりありがたい存在になります。
一方で満足感が得られなかった場合は、他社に流れたり、ネガティブなレビューを広める可能性もあります。
昨今はSNSの普及により、良くも悪くも評判はすぐに広まってしまうため、顧客満足度を高めることは特に重要視されています。
顧客満足度調査のアンケート例はこちら
顧客満足度は企業の売り上げに深く結びつくため、課題解決に役立たせることができます。
顧客にとって期待値以上の製品もしくはサービスを提供した場合、リピートしてくれる確率が上がり、周りの人にお勧めしてくれたりするなど、自社にとってはかなりありがたい存在になります。
一方で満足感が得られなかった場合は、他社に流れたり、ネガティブなレビューを広める可能性もあります。
昨今はSNSの普及により、良くも悪くも評判はすぐに広まってしまうため、顧客満足度を高めることは特に重要視されています。
顧客満足度調査のアンケート例はこちら
競合調査
自社と他社の製品やサービスなどを多面的に比較して、自社のポジショニングを明確にし、売上アップ・顧客獲得を狙うための調査です。
また、商品開発や新規事業を展開する場合にも有効な調査といえます。
市場の競争で生き残っていくためには、競合を知り差別化を図ることが重要です。
調査完了後は、結果から自社の強みや弱みを把握し、改善すべき課題等の洗い出しをします。
また、商品開発や新規事業を展開する場合にも有効な調査といえます。
市場の競争で生き残っていくためには、競合を知り差別化を図ることが重要です。
調査完了後は、結果から自社の強みや弱みを把握し、改善すべき課題等の洗い出しをします。
-
2万円から海外消費者にアンケートができる!サーベロイドの海外調査とは

アンケート調査の進め方
冒頭でも記載しましたが、アンケート調査にはオンラインとオフラインの2種類があります。
アンケート調査を実施する上での基本的な進め方に大きな違いはありませんが、進め方を誤ると意図したデータが取れない、回答者が集まらない等の不備が出てくる可能性があります。
調査を実施する際は、これから解説するコツを掴んで確実にデータを集められるようにしましょう!
アンケート調査を実施する上での基本的な進め方に大きな違いはありませんが、進め方を誤ると意図したデータが取れない、回答者が集まらない等の不備が出てくる可能性があります。
調査を実施する際は、これから解説するコツを掴んで確実にデータを集められるようにしましょう!
①目的・ターゲットを明確にする
アンケート調査の作り方として、目的・ターゲットを明確にすることはとても重要です。
上記を怠ると、回答結果から表面的な理解を得ることはできても、本質的なところで立ち止まり、十分な分析ができなくなる可能性があります。有効的にデータを活用できずに終わるのはもったいないことです。
そういったことを避けるために、最初を固めておくことで、その後のプロセスをスムーズに進めることができます。
データを有効活用するためにも、必ず調査結果の活用方法まで想定しておきましょう。
上記を怠ると、回答結果から表面的な理解を得ることはできても、本質的なところで立ち止まり、十分な分析ができなくなる可能性があります。有効的にデータを活用できずに終わるのはもったいないことです。
そういったことを避けるために、最初を固めておくことで、その後のプロセスをスムーズに進めることができます。
データを有効活用するためにも、必ず調査結果の活用方法まで想定しておきましょう。
②質問を作成する
次に、実際に回答してもらう質問を考えていきます。
アンケートの回答形式は、自由記述よりも選択肢を作成しておく方が、後々の集計や分析はしやすくなります。
また、アンケートを作成するときは、回答者の立場になることを心がけましょう。
作りこまれていないアンケートは「回答しづらい」「回答する気力を失う」といった理由から、回収したデータが精度の低いものになる可能性があります。
ここでは、アンケート調査で質問を作成する際に気をつけたいポイントを3つご紹介します。
1.質問文は簡潔で分かりやすく
一般的に使われてない文言を多用したり、長文で聞きたいことを盛り込んだ文章だと、回答するまでに思考することが増え、回答負荷が高まります。具体的な画像や図を提示する、といった配慮により、回答者が回答する際にかかる負荷を軽減させることが大切です。回答しやすい調査内容にすることで、より正確なデータの回収にも繋がります
2.質問順は時系列に沿って設定する
例えば「自社製品の浸透実態」を調査するときの質問順として、正しい順番は以下になります。
認知→購入経験→直近購入経験→今後の購入意向
購入経験→認知 のような順番にすると時系列が乱れ、回答負荷が高まります。
3.質問数に配慮する
質問の順番と同様に、質問の数にも配慮が必要です。質問の数が多くなりすぎないように、質問を厳選して調査を実施しましょう。また、質問文も長くなりすぎないよう、簡潔に記載することを心がけましょう。
4.似ている選択肢を作らない
例えば、選択肢内に「テレビ」と「マスメディア」があると、テレビはマスメディアに含まれるため、回答者は迷ってしまい、回答が分散する恐れがあります。
また、択肢は、内容が重複しないようにし、考えられる回答を網羅している必要があります(MECEの状態)。また、「どちらともいえない」「その他」といった選択肢を用意することで、無理に回答を選ばせることを避けられます。
5.目的に合ったアンケートツールを選ぶ
Webアンケートを実施する場合、どのツールを使うかも重要なポイントです。無料で使えるシンプルなツールから、高度な集計・分析機能を備えた有料ツールまで様々です。セキュリティ、使いやすさ、サポート体制などを比較検討し、調査の規模や目的に合ったツールを選定しましょう。
▼関連記事
アンケート調査票の作り方は?例(テンプレート)や良い例・悪い例を公開
アンケートの選択肢の重要性・作成時の注意点・種類について解説
アンケートの回答形式は、自由記述よりも選択肢を作成しておく方が、後々の集計や分析はしやすくなります。
また、アンケートを作成するときは、回答者の立場になることを心がけましょう。
作りこまれていないアンケートは「回答しづらい」「回答する気力を失う」といった理由から、回収したデータが精度の低いものになる可能性があります。
ここでは、アンケート調査で質問を作成する際に気をつけたいポイントを3つご紹介します。
1.質問文は簡潔で分かりやすく
一般的に使われてない文言を多用したり、長文で聞きたいことを盛り込んだ文章だと、回答するまでに思考することが増え、回答負荷が高まります。具体的な画像や図を提示する、といった配慮により、回答者が回答する際にかかる負荷を軽減させることが大切です。回答しやすい調査内容にすることで、より正確なデータの回収にも繋がります
2.質問順は時系列に沿って設定する
例えば「自社製品の浸透実態」を調査するときの質問順として、正しい順番は以下になります。
認知→購入経験→直近購入経験→今後の購入意向
購入経験→認知 のような順番にすると時系列が乱れ、回答負荷が高まります。
3.質問数に配慮する
質問の順番と同様に、質問の数にも配慮が必要です。質問の数が多くなりすぎないように、質問を厳選して調査を実施しましょう。また、質問文も長くなりすぎないよう、簡潔に記載することを心がけましょう。
4.似ている選択肢を作らない
例えば、選択肢内に「テレビ」と「マスメディア」があると、テレビはマスメディアに含まれるため、回答者は迷ってしまい、回答が分散する恐れがあります。
また、択肢は、内容が重複しないようにし、考えられる回答を網羅している必要があります(MECEの状態)。また、「どちらともいえない」「その他」といった選択肢を用意することで、無理に回答を選ばせることを避けられます。
5.目的に合ったアンケートツールを選ぶ
Webアンケートを実施する場合、どのツールを使うかも重要なポイントです。無料で使えるシンプルなツールから、高度な集計・分析機能を備えた有料ツールまで様々です。セキュリティ、使いやすさ、サポート体制などを比較検討し、調査の規模や目的に合ったツールを選定しましょう。
▼関連記事
アンケート調査票の作り方は?例(テンプレート)や良い例・悪い例を公開
アンケートの選択肢の重要性・作成時の注意点・種類について解説
③実施期間を決める
アンケート調査の種類によって、実施~集計までの期間が変わります。
今回は、以下の4つのアンケート手法において、それぞれどれくらいの期間が必要になるかを記載します。
※記載の期間はあくまでも目安であり、内容によって異なります。
・Webアンケート…2週間程度
・会場調査…4~5週間
・郵送アンケート…1ヶ月~2ヶ月
・街頭調査…1ヶ月以上
今回は、以下の4つのアンケート手法において、それぞれどれくらいの期間が必要になるかを記載します。
※記載の期間はあくまでも目安であり、内容によって異なります。
・Webアンケート…2週間程度
・会場調査…4~5週間
・郵送アンケート…1ヶ月~2ヶ月
・街頭調査…1ヶ月以上
④集計・分析をする
データが回収できたら、集計や分析をします。
それぞれいくつか種類があり、目的によって手法を変えます。
本記事では主に使われている手法についてご紹介します。
それぞれいくつか種類があり、目的によって手法を変えます。
本記事では主に使われている手法についてご紹介します。
集計方法
■単純集計
選択式の設問において、回答ごとの数を足し合わせるシンプルな集計方法です。
調査結果全体を俯瞰的に見ることができ、回答の傾向を把握することができます。
■クロス集計
ある設問において他設問や属性情報と掛け合わせることで、より深掘りした傾向を把握することができます。
例えば「性別」や「年代」で回答傾向は異なるのか確認したいときに、クロス集計を実施します。
■自由記述集計
数値もしくは文章のどちらかを回答者に記入させる形式の設問において行う集計方法です。
- ・数値
最小値、最大値、平均値、中央値、標準偏差を確認することで、データの読み違いを防ぐことができます。 - ・文章
自由記述だけの集計一覧表を作成します。その後、キーワードをカテゴライズする「アフターコーディング」や出現単語を視覚的にわかりやすくする「テキストマイニング」などで分析をしていきます。
⑤レポーティングをする
分析結果をまとめ終えたら、レポートを作成します。結果を元に、立てた仮説が正しかったのか違ったのか、結論をわかりやすく記載しましょう。第三者が見てもわかりやすく、意思決定において役立つ資料になるように作成することが大切です。加えて、グラフ等を用いて数値データを視覚的にわかりやすくすることも求められるでしょう。次の施策を考えたり、マーケティング戦略のヒントを得ることができるようなレポートが理想です。

質の高いアンケートと質の低いアンケートの違い
アンケートの質は、調査設計や対象者属性の正確さ、適切な調査方法などで決まります。特に設問文が調査目的に沿って作られており、回答者が誤解や間違いのないように作られていれば質の高いアンケート調査となり、その後の意思決定やマーケティング戦略構築に有意義なデータを回収できます。
ここでは、2つのアンケート票を例にして、質の高いアンケートの作り方を解説します。
ここでは、2つのアンケート票を例にして、質の高いアンケートの作り方を解説します。

1.誘導的な質問にしない
質の低いアンケートのQ1は、誘導尋問になっています。「~賛成ですか。」と聞かれれば、「賛成です」と答えやすくなり、「どう思いますか。」の方が適切といえます。このほか「~した経験はありますか。」「~良いと思いますか。」なども、誘導設問にあたります。
2.主語を明確にする
質の低いアンケートのQ2は主語が抜けており、回答者は自分のことなのか家族のことを聞かれているかがわかりません。主語は必ず明確にしましょう。
3.曖昧な表現を避ける
質の低いアンケートのQ3は、「普段」という言い方が人によって解釈が変わるため曖昧表現となります。「現在」「普段」「最近」などは極力避けるようにして、「最近1週間以内」「この1か月間で」など、誰でも同じ解釈となる言葉を選びましょう。
4.1つの設問に複数の内容を入れない
質の低いアンケートのQ4の質問では、清涼飲料水とお弁当の2つの要素についての回答を求めていて、回答者はどちらのことを聞かれているのか判断できません。1つの設問では1要素を聞くようにしましょう。
5.選択肢は必要十分にする
質の低いアンケートのQ5では、「弁当・おにぎり」がコンビニエンスストアの主力商品であるため、選択肢にないと正確なデータを得られないリスクが高まります。選択肢は偏りがなく、必要十分な項目を入れましょう。
6.結びを統一して、「?」は使用しない
設問文の結びが「お答えください」「お知らせください」などが混在していると、違いがあるかもと勘ぐられ回答に悪影響が出る可能性があります。結びの表現は統一しましょう。また「~ですか。」などの末尾に「?」は必要ありません。
7.専門用語や略語、差別用語は使わない
たとえばCVやSMなどの専門用語やコンビニ、スマホなどの略語は、わからない回答者がいる可能性もあるため使わないようにしましょう。老人、盲(めくら)といった差別的用語の使用も避けましょう。
8.過度な敬語・謙譲語は使わない
過度な敬語や謙譲語もかえって意図が伝わりづらくなる可能性もあるため、使わないようにしましょう。「あなたの年収をお答えいただけますと幸いです。」は不自然で、「あなたの年収をお知らせください。」が妥当です。
質の低いアンケートのQ1は、誘導尋問になっています。「~賛成ですか。」と聞かれれば、「賛成です」と答えやすくなり、「どう思いますか。」の方が適切といえます。このほか「~した経験はありますか。」「~良いと思いますか。」なども、誘導設問にあたります。
2.主語を明確にする
質の低いアンケートのQ2は主語が抜けており、回答者は自分のことなのか家族のことを聞かれているかがわかりません。主語は必ず明確にしましょう。
3.曖昧な表現を避ける
質の低いアンケートのQ3は、「普段」という言い方が人によって解釈が変わるため曖昧表現となります。「現在」「普段」「最近」などは極力避けるようにして、「最近1週間以内」「この1か月間で」など、誰でも同じ解釈となる言葉を選びましょう。
4.1つの設問に複数の内容を入れない
質の低いアンケートのQ4の質問では、清涼飲料水とお弁当の2つの要素についての回答を求めていて、回答者はどちらのことを聞かれているのか判断できません。1つの設問では1要素を聞くようにしましょう。
5.選択肢は必要十分にする
質の低いアンケートのQ5では、「弁当・おにぎり」がコンビニエンスストアの主力商品であるため、選択肢にないと正確なデータを得られないリスクが高まります。選択肢は偏りがなく、必要十分な項目を入れましょう。
6.結びを統一して、「?」は使用しない
設問文の結びが「お答えください」「お知らせください」などが混在していると、違いがあるかもと勘ぐられ回答に悪影響が出る可能性があります。結びの表現は統一しましょう。また「~ですか。」などの末尾に「?」は必要ありません。
7.専門用語や略語、差別用語は使わない
たとえばCVやSMなどの専門用語やコンビニ、スマホなどの略語は、わからない回答者がいる可能性もあるため使わないようにしましょう。老人、盲(めくら)といった差別的用語の使用も避けましょう。
8.過度な敬語・謙譲語は使わない
過度な敬語や謙譲語もかえって意図が伝わりづらくなる可能性もあるため、使わないようにしましょう。「あなたの年収をお答えいただけますと幸いです。」は不自然で、「あなたの年収をお知らせください。」が妥当です。
アンケート調査活用事例
様々な業界でのアンケート活用事例を3つ紹介します。ビジネス上の課題を解決するための一手段としてアンケートを用いて製品開発・改善、広告戦略などに活かします。
酒類メーカー 自社顧客だけでなく一般消費者の声をアンケートで集める
自社顧客へのアンケートは実施してきたが、一般消費者に対する市場調査を行ったことがなかったため、市場の現状や課題を把握するために、お酒の量り売りにフォーカスした実態把握調査を行った。回答モニターを保有しているネットリサーチツールを使用したことで、今まで情報がなかった若年層へのアプローチもでき、調査結果から新たな課題が見つかり、全社共通の認識を持つことが出来ました。また、データは今後の顧客となり得る層への販促方法などのマーケティング施策に判断材料の一つとして活用しています。
調査事例紹介|酒類メーカー 自社顧客だけでなく一般消費者の声をアンケートで集める
調査事例紹介|酒類メーカー 自社顧客だけでなく一般消費者の声をアンケートで集める
広告代理店 提案時の強みになるデータをネットリサーチで取る
クライアントが抱える課題をプロモーションに落とし込む際に、消費者データを用いた提案をしたくネットリサーチを活用しました。スピード感が求められることも多く、外部に調査を委託する時間や余裕がない案件において、セルフ型のアンケートツールを用いて自分で調査をすることで次の日の提案にエビデンスのあるデータを添えることが出来ています。
調査事例紹介|広告代理店 提案時の強みになるデータをネットリサーチで取る
調査事例紹介|広告代理店 提案時の強みになるデータをネットリサーチで取る
販促企画部署 消費者インサイトをネットリサーチで確認
購買データ(アクチュアルデータ)を眺めていてもわからない「なぜ?」の部分をアンケートを取って深堀することで、今後の企画や施策を実行する上でのヒントを得ています。
調査事例紹介|販促企画部署 消費者インサイトをネットリサーチで確認
調査事例紹介|販促企画部署 消費者インサイトをネットリサーチで確認

アンケート調査の費用相場
ここからは、アンケート調査を実施する際のおおまかな費用を、オンライン・オフライン別に解説します。
オンラインの場合
オンライン調査として、インターネットで行う定量調査とオンライングループインタビューの相場を紹介します。
インターネット定量調査
インターネット定量調査にかかる費用は、集める回答者数であるサンプル数×設問数で算出されます。調査会社に依頼する場合は、自社サイトに料金表を掲載していることが多いため確認してみましょう。
・300s/20問の場合:20万円~30万円程度
セルフ型アンケートツールを活用すると安価に実施することも可能です。
・300s/20問の場合:6万円
※「Surveroid」活用の場合
セルフ型アンケートツール「Surveroid」の料金体系を確認する
・300s/20問の場合:20万円~30万円程度
セルフ型アンケートツールを活用すると安価に実施することも可能です。
・300s/20問の場合:6万円
※「Surveroid」活用の場合
セルフ型アンケートツール「Surveroid」の料金体系を確認する
オンライングループインタビュー
オンライングループインタビュー費用は、調査企画費、調査対象者のリクルーティング費用、謝礼、機材・備品費用など実査にかかる費用と、実査及び発言録・レポート作成などの対応工数に基づく人件費などで計算されます。費用相場は対象者数やグループ数で異なることもあります。
・6名×1グループの場合:40万円~60万円程度
セルフ型アンケートツールを活用すると安価に実施することも可能です。
・6名の場合:12万円~18万円
※「Surveroid」活用の場合
セルフ型アンケートツール「Surveroid」のオンラインインタビューの詳細を確認する
・6名×1グループの場合:40万円~60万円程度
セルフ型アンケートツールを活用すると安価に実施することも可能です。
・6名の場合:12万円~18万円
※「Surveroid」活用の場合
セルフ型アンケートツール「Surveroid」のオンラインインタビューの詳細を確認する
オフラインの場合
オフライン調査には郵送調査や街頭調査、会場調査(CLT)・ホームユーステスト(HUT)調査などが挙げられます。それぞれ実査に必要な人件費や郵送費・会場費などの実費がかかるため、オンライン調査よりも割高になる傾向があります。
郵送調査、街頭調査
調査対象者の自宅等にアンケート用紙を送付し返送してもらう郵送調査では、アンケート用紙や謝礼の送付・返送の実費や人件費がかかります。
・郵送調査:1,000通送付の場合:20万円~50万円程度
・街頭調査:500件回収の場合:15万円~40万円程度
・郵送調査:1,000通送付の場合:20万円~50万円程度
・街頭調査:500件回収の場合:15万円~40万円程度
CLT(会場テスト)
複数名の調査対象者を会場に集め、商品やサービスを実際に使って評価や意見を集めるCLTは、会場費や謝礼などの実費がかかります。
・100名/15問(スクリーニングを含む)の場合:100万円~200万円程度
・100名/15問(スクリーニングを含む)の場合:100万円~200万円程度

アンケート調査会社の選び方
アンケート調査を実施するにあたって調査会社を使用する場合は、以下のポイントに注意して選びましょう。
ポイント1.パネルの規模・品質を確認する
アンケートの回答者(パネル)の規模や属性は、調査結果の質を左右するため必ず事前に確認しましょう。保有パネルの規模が大きければ、必要なサンプルを確保できます。またパネル情報の更新頻度が高ければ質の高いパネルを保有していると考えられ、求める属性に正しく合致する対象者を選択できます。
ポイント2.リサーチコストが見合っている
目的や用途によって調査手法や規模が変わるため、コストも大きく異なります。予算内にクオリティの高い調査を行うためにも、事前に複数社から見積を取ることをおすすめします。実査費用のほかに分析やレポート作成がオプションとなる調査会社もあるため、細かくチェックしましょう。
ポイント3.経験や実績が豊富
リサーチ経験や実績が豊富な調査会社であれば、安心して任せることができます。またリサーチ会社のネットリサーチツールなどを利用する場合は、サポート体制が充実しているところを選ぶとよいでしょう。アンケート調査は専門的なノウハウが必要なので、プロによる支援があれば、不測の事態が起きてもスムーズな進行ができるでしょう。
選ぶ際に意識したいチェック項目
アンケート調査会社を選ぶ際のチェックリストをご用意したので活用ください。
- ☑パネルの規模は充分か、高い品質を保っているか
- ☑予算内に収まる調査費用か、オプション費用はないか
- ☑自社と同業界、同業種の調査経験は豊富か
- ☑実施しようとしている調査と同様の調査経験や実績があるか
- ☑サポート体制や支援内容が希望通りになっているか
- ☑納期を厳守できる体制になっているか
- ☑目的やニーズに合った調査方法や調査設計が可能か
- ☑回答の品質を担保する対策があるか
- ☑高い分析力でレポートや報告書作成が可能か
- ☑データなどの納品物の種類や品質は適正か
ネットリサーチなら「Surveroid(サーベロイド)」
ネットリサーチツールのSurveroid(サーベロイド)は、約600万人(2025年8月時点)のモニターに対して、低コストかつスピーディーにアンケートが実施することが特徴のツールです。
昨今、ビジネスのPDCAにおいて意思決定のスピードが加速する中、Surveroidは登録から即日でアンケートの作成〜配信が実施でき、最短翌日にはデータ回収が完了している速さがユーザーから好評なサービスです。
1.直感的操作でスピーディなアンケートを実現
Surveroidは初めてネットリサーチツールを利用する方でも簡単にアンケートを作成することができます。直感的な操作で作成ができ、初心者の方にも多く利用いただいております。最短1日でアンケート結果が確定するため、明日の会議やプレゼンテーションに活用できます。
Surveroidは初めてネットリサーチツールを利用する方でも簡単にアンケートを作成することができます。直感的な操作で作成ができ、初心者の方にも多く利用いただいております。最短1日でアンケート結果が確定するため、明日の会議やプレゼンテーションに活用できます。
2.充実の機能を搭載
Surveroidは、セルフ型アンケートツールの専門企業がサービスを運営しており、アンケートに必要な基本機能は全て搭載し、実際に大手の市場調査会社も使用する消費者モニター(パネル)へ配信することが可能です。
年齢や性別、都道府県、子供の有無や職種など多彩な項目から絞り込んで配信ができるため、自社のターゲット層に対して効率的にマーケティングを行うことができます。さらに、セグメントごとに比較が可能なように性別・年代別で回収数を指定することも可能です。
Surveroidは、セルフ型アンケートツールの専門企業がサービスを運営しており、アンケートに必要な基本機能は全て搭載し、実際に大手の市場調査会社も使用する消費者モニター(パネル)へ配信することが可能です。
年齢や性別、都道府県、子供の有無や職種など多彩な項目から絞り込んで配信ができるため、自社のターゲット層に対して効率的にマーケティングを行うことができます。さらに、セグメントごとに比較が可能なように性別・年代別で回収数を指定することも可能です。
3.アンケート結果の集計も手軽
ネットリサーチツールはアンケートの作成から集計までが手軽でなければ利便性に優れているとは言えません。Surveroidはアンケート結果に対して付属の集計ツールが利用できます。
単純集計表・クロス集計表・FA表などの集計表がマウスのクリック操作という直感的な操作のみで作成でき、グラフやレポートの出力も可能です。
ネットリサーチツールはアンケートの作成から集計までが手軽でなければ利便性に優れているとは言えません。Surveroidはアンケート結果に対して付属の集計ツールが利用できます。
単純集計表・クロス集計表・FA表などの集計表がマウスのクリック操作という直感的な操作のみで作成でき、グラフやレポートの出力も可能です。
4.低価格での利用が可能
Surveroidは初期費用、月額費用は一切発生せず、利用した分だけ費用が発生する完全な従量課金制(最低価格1万円(税別)〜) となっています。
ネットリサーチ会社などに外注した場合と比較して、圧倒的なコスト圧縮が可能です。
Surveroidは初期費用、月額費用は一切発生せず、利用した分だけ費用が発生する完全な従量課金制(最低価格1万円(税別)〜) となっています。
ネットリサーチ会社などに外注した場合と比較して、圧倒的なコスト圧縮が可能です。

まとめ
アンケート調査はビジネスの課題解決に欠かせない重要な手法で、様々な手法や種類があります。
本記事内でもご紹介した「Surveroid(サーベロイド)」は、Web上でアンケート作成から集計までをご自身で実施できるため、調査費用が抑えられる・業務の負担が減るといったメリットがあります。
アンケート調査の実施検討している方は、ぜひ一度サービス内容をご確認いただければと思います。
本記事内でもご紹介した「Surveroid(サーベロイド)」は、Web上でアンケート作成から集計までをご自身で実施できるため、調査費用が抑えられる・業務の負担が減るといったメリットがあります。
アンケート調査の実施検討している方は、ぜひ一度サービス内容をご確認いただければと思います。
108 件
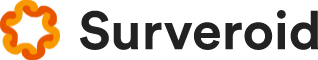 サーベロイドでリサーチをはじめませんか?
サーベロイドでリサーチをはじめませんか?




