目次
アンケートは、顧客や生活者の声をデータとして可視化できる、もっともシンプルで効果的なリサーチ手法です。
しかし、設計を誤ると「役立たない結果」に終わってしまうことも少なくありません。
なんとなく質問を並べただけでは、集めたデータを分析しても有益な結論が導けないのです。
この記事では、アンケートの作り方を初心者にもわかりやすく体系的に解説します。
目的設定から設問設計、失敗しないコツ、集計・分析の基本、さらに活用できる質問例やテンプレートまで、すべてを一つの記事にまとめました。
しかし、設計を誤ると「役立たない結果」に終わってしまうことも少なくありません。
なんとなく質問を並べただけでは、集めたデータを分析しても有益な結論が導けないのです。
この記事では、アンケートの作り方を初心者にもわかりやすく体系的に解説します。
目的設定から設問設計、失敗しないコツ、集計・分析の基本、さらに活用できる質問例やテンプレートまで、すべてを一つの記事にまとめました。
アンケートの作り方の基本と重要性
アンケート調査は「設計段階で成否が決まる」と言われるほど、最初の準備が重要です。
目的があいまいなまま質問を作ると、集めた回答は分析に活かせず、せっかくの調査が「数字を並べただけ」で終わってしまいます。
アンケートのゴールは「回答を集めること」ではなく、意思決定や施策改善につながるデータを得ることです。
そのためには、事前に「誰に」「何を」「どのように」聞くのかを整理してブレない調査設計を行う必要があります。
よくある失敗例
・質問が多すぎて回答者が途中離脱する
・設問があいまいで、回答が解釈次第になってしまう
・回答形式がバラバラで、集計・比較が難しい
・誘導的な表現で回答が偏る
これらはすべて「設計不足」が原因です。裏を返せば、設計をしっかり行えば、こうした失敗を避けることができます。
目的があいまいなまま質問を作ると、集めた回答は分析に活かせず、せっかくの調査が「数字を並べただけ」で終わってしまいます。
アンケートのゴールは「回答を集めること」ではなく、意思決定や施策改善につながるデータを得ることです。
そのためには、事前に「誰に」「何を」「どのように」聞くのかを整理してブレない調査設計を行う必要があります。
よくある失敗例
・質問が多すぎて回答者が途中離脱する
・設問があいまいで、回答が解釈次第になってしまう
・回答形式がバラバラで、集計・比較が難しい
・誘導的な表現で回答が偏る
これらはすべて「設計不足」が原因です。裏を返せば、設計をしっかり行えば、こうした失敗を避けることができます。
アンケート実施の前に目的を整理しておく
アンケートを始める前に、必ず調査の目的を言語化することが大切です。
目的が整理されていないと、質問が増えすぎたり、結果が実務に活かせなかったりといった問題につながります。
整理すべき観点
アンケート企画書のように、以下を簡単に書き出しておくと調査がブレません。
・なぜ調査を行うのか(例:新商品の改良点を知りたい/利用者満足度を測りたい)
・誰に答えてもらうのか(例:既存顧客、特定の年代、購入経験者)
・何を聞きたいのか(例:購買理由、不満点、利用頻度)
・どんな方法で実施するのか(例:オンライン調査、オフライン、定量/定性)
目的が整理されていないと、質問が増えすぎたり、結果が実務に活かせなかったりといった問題につながります。
整理すべき観点
アンケート企画書のように、以下を簡単に書き出しておくと調査がブレません。
・なぜ調査を行うのか(例:新商品の改良点を知りたい/利用者満足度を測りたい)
・誰に答えてもらうのか(例:既存顧客、特定の年代、購入経験者)
・何を聞きたいのか(例:購買理由、不満点、利用頻度)
・どんな方法で実施するのか(例:オンライン調査、オフライン、定量/定性)

アンケート作成の基本ステップとコツ
アンケート設計は「流れ」に沿って組み立てることで、抜け漏れや偏りを防ぎやすくなります。
ここでは、質問項目の決め方から文言の工夫、選択肢設計まで、初心者がつまずきやすいポイントを押さえながら、失敗しないためのコツを紹介します。
ここでは、質問項目の決め方から文言の工夫、選択肢設計まで、初心者がつまずきやすいポイントを押さえながら、失敗しないためのコツを紹介します。
STEP1:質問項目を決める
アンケート設計の第一歩は「どんなことを聞くか」を整理することです。
この段階で重要なのは、目的に直結する項目だけを残すという姿勢です。
質問項目を決める際の流れ
1.ざっくり洗い出す
最初は思いつく限りの項目を書き出します。(例:利用頻度、満足度、不満点、改善要望)
2.取捨選択する
調査の目的と照らし合わせて「必要/不要」を分けます。
3.優先順位をつける
目的に強く関係するものから順番に残していくと、無駄のない調査票になります。
注意点
1.質問数を増やしすぎない
回答負担が大きくなり、途中離脱につながる。理想は5〜10問程度
2.似たような質問を重複させない
集計しても意味が重ならないようにする。
3.後の分析を意識して項目を選ぶ
例えば「年齢」や「性別」を聞くのは、後でクロス集計するため。
この段階で重要なのは、目的に直結する項目だけを残すという姿勢です。
質問項目を決める際の流れ
1.ざっくり洗い出す
最初は思いつく限りの項目を書き出します。(例:利用頻度、満足度、不満点、改善要望)
2.取捨選択する
調査の目的と照らし合わせて「必要/不要」を分けます。
3.優先順位をつける
目的に強く関係するものから順番に残していくと、無駄のない調査票になります。
注意点
1.質問数を増やしすぎない
回答負担が大きくなり、途中離脱につながる。理想は5〜10問程度
2.似たような質問を重複させない
集計しても意味が重ならないようにする。
3.後の分析を意識して項目を選ぶ
例えば「年齢」や「性別」を聞くのは、後でクロス集計するため。
STEP2:質問文を決める
質問項目が決まったら、次は実際の質問文の表現を考えます。
質問文の書き方ひとつで、回答の正確性や信頼性は大きく変わります。初心者がもっともつまずきやすいのも、このステップです。
例えば、以下のような質問文はNGです。
❌「当社の商品を購入していただいた際、スタッフの対応や商品の品質について全体的にご満足いただけましたでしょうか?」
この質問は、
・文が長くて理解しづらい
・複数の要素(スタッフ対応・商品の品質)を同時に聞いている
という問題があり、回答がぶれやすくなります。
正しい書き方の例はこちらです。
⭕「購入した商品の品質に満足していますか?」
⭕「スタッフの対応に満足していますか?」
このように、短くシンプルに、1つの質問で1つのことを聞くのが基本です。
質問文作成のポイント
1.誰にでもわかる表現にする
専門用語や社内用語は避け、一般的な言葉に置き換える。
例:「NPSを教えてください」ではなく「あなたはこの商品を友人や同僚に勧めたいと思いますか?」
2.1つの質問で1つのことを聞く
「価格とデザインに満足していますか?」のように複数要素を同時に聞くと、回答がぶれてしまう(=ダブルバレル質問)。
3.前提を揃える
回答者の理解に差があると、同じ質問でも解釈が異なる。必要に応じて条件や前提を補足する。
例:「最近購入した商品の満足度をお答えください(ここ1か月以内に購入した商品が対象です)」
4.誘導的な表現を避ける
「多くの人が良いと答えていますが、あなたはどう思いますか?」と書くと、回答が偏ってしまう。
5.過度な敬語や冗長な言い回しを避ける
質問はシンプルに。「〜でいらっしゃいますか?」より「〜ですか?」で十分。
質問文の書き方ひとつで、回答の正確性や信頼性は大きく変わります。初心者がもっともつまずきやすいのも、このステップです。
例えば、以下のような質問文はNGです。
❌「当社の商品を購入していただいた際、スタッフの対応や商品の品質について全体的にご満足いただけましたでしょうか?」
この質問は、
・文が長くて理解しづらい
・複数の要素(スタッフ対応・商品の品質)を同時に聞いている
という問題があり、回答がぶれやすくなります。
正しい書き方の例はこちらです。
⭕「購入した商品の品質に満足していますか?」
⭕「スタッフの対応に満足していますか?」
このように、短くシンプルに、1つの質問で1つのことを聞くのが基本です。
質問文作成のポイント
1.誰にでもわかる表現にする
専門用語や社内用語は避け、一般的な言葉に置き換える。
例:「NPSを教えてください」ではなく「あなたはこの商品を友人や同僚に勧めたいと思いますか?」
2.1つの質問で1つのことを聞く
「価格とデザインに満足していますか?」のように複数要素を同時に聞くと、回答がぶれてしまう(=ダブルバレル質問)。
3.前提を揃える
回答者の理解に差があると、同じ質問でも解釈が異なる。必要に応じて条件や前提を補足する。
例:「最近購入した商品の満足度をお答えください(ここ1か月以内に購入した商品が対象です)」
4.誘導的な表現を避ける
「多くの人が良いと答えていますが、あなたはどう思いますか?」と書くと、回答が偏ってしまう。
5.過度な敬語や冗長な言い回しを避ける
質問はシンプルに。「〜でいらっしゃいますか?」より「〜ですか?」で十分。
STEP3:選択肢形式を決める
質問文が決まったら、次はどのような形式で回答をもらうかを考えます。
選択肢形式の設計は、集計のしやすさや回答のしやすさに直結する重要なポイントです。
選択肢形式の設計は、集計のしやすさや回答のしやすさに直結する重要なポイントです。
代表的な回答形式
| 回答形式 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 単一回答(ラジオボタン) | 選択肢の中から1つだけ選ぶ | 集計が簡単、迷いにくい | 回答のニュアンスが拾えない |
| 複数回答(チェックボックス) | 選択肢の中から複数選ぶことが可能 | 実態を反映しやすい | 回答が散らばりやすい |
| マトリクス形式(表形式) | 複数項目に対して同じ尺度で回答 | 複数の質問を効率的に聞ける | 項目数が多いと回答負担が増える |
| 自由記述 | テキストで自由に回答 | 定性的な意見を補完できる | 集計に手間がかかる |
回答形式は「調査目的」「回答者の負担」「分析のしやすさ」を基準に決めましょう。自由記述は補助的に使い、基本は選択式を中心に設計するのが失敗しにくい方法です。
ポイント
①目的に合わせて形式を選ぶ
満足度を知りたい場合は「5段階評価」、購買理由を知りたい場合は「複数回答」など、アンケートの目的によって最適な回答形式は異なります。また、形式は見た目や作りやすさだけでなく、集計・分析のしやすさまで考慮して選ぶことが大切です。
②ネットリサーチでは選択式が基本
自由記述は分析に手間がかかり、回答者自身も言語化が難しい場合が多いため、有効な回答が得られにくいことがあります。そのため、自由記述は補助的に活用するのが一般的です。
具体的な意見や背景を深掘りしたいなら、アンケートではなくインタビュー調査を組み合わせる方が有効です。
③制御機能を活用する
選択肢に「排他設定」や「個数制限」を設けることで、回答の整合性が高まり、より正確で分析しやすいデータが得られます。
ポイント
①目的に合わせて形式を選ぶ
満足度を知りたい場合は「5段階評価」、購買理由を知りたい場合は「複数回答」など、アンケートの目的によって最適な回答形式は異なります。また、形式は見た目や作りやすさだけでなく、集計・分析のしやすさまで考慮して選ぶことが大切です。
②ネットリサーチでは選択式が基本
自由記述は分析に手間がかかり、回答者自身も言語化が難しい場合が多いため、有効な回答が得られにくいことがあります。そのため、自由記述は補助的に活用するのが一般的です。
具体的な意見や背景を深掘りしたいなら、アンケートではなくインタビュー調査を組み合わせる方が有効です。
③制御機能を活用する
選択肢に「排他設定」や「個数制限」を設けることで、回答の整合性が高まり、より正確で分析しやすいデータが得られます。
STEP4:選択肢を決める
質問文に合わせて用意する選択肢の設計も、アンケートの精度を左右する大事なポイントです。選択肢が不適切だと、回答者が迷ったり、分析で解釈に困ったりする原因になります。
選択肢を作るときの基本ルール
1.シンプルで分かりやすい言葉を使う
専門用語や業界用語は避け、誰が読んでも理解できる表現にしましょう。
2.選択肢の数は適切に
尺度を測る質問(満足度・印象など)は5〜7段階が目安。
一方、趣味やブランドなどカテゴリ型の質問は10〜15個 になる場合もありますが、多すぎる場合はジャンル別に分けたり、複数回答時に上限設定をするなど、回答しやすい工夫をしましょう。
3.MECE(漏れなく・重複なく)を意識する
選択肢に抜け漏れがあると回答者が困り、重複があるとデータが偏ります。
購入理由を聞くときに、「価格が安い/品質が良い/デザインが好き」だけだと不十分なので、 「口コミで評判だった」「ポイントが貯まる」「その他」なども加えると、より網羅的になります。
4.「その他」や「わからない」も用意する
無理に選ばせず、回答者に選択肢がないストレスを与えないことで、データの正確性が高まります。
特にBtoB(法人向け)調査では、会社の状況について「わからない」と答えるケースが少なくありません。スクリーニング調査の段階で「わからない」を入れておくと、ターゲットの選定がスムーズになります。
一方で、実施後に「その他」ばかりに回答が集中した場合は、回答者が適切な選択肢を見つけられなかった=選択肢設計に不足があったサインと考えるべきです。その場合は、次回の設計で選択肢を見直し、「その他」に含まれていた回答を新しい選択肢として取り込むことが有効です。
▼関連記事
アンケートの選択肢の重要性・作成時の注意点・種類について解説
選択肢を作るときの基本ルール
1.シンプルで分かりやすい言葉を使う
専門用語や業界用語は避け、誰が読んでも理解できる表現にしましょう。
2.選択肢の数は適切に
尺度を測る質問(満足度・印象など)は5〜7段階が目安。
一方、趣味やブランドなどカテゴリ型の質問は10〜15個 になる場合もありますが、多すぎる場合はジャンル別に分けたり、複数回答時に上限設定をするなど、回答しやすい工夫をしましょう。
3.MECE(漏れなく・重複なく)を意識する
選択肢に抜け漏れがあると回答者が困り、重複があるとデータが偏ります。
購入理由を聞くときに、「価格が安い/品質が良い/デザインが好き」だけだと不十分なので、 「口コミで評判だった」「ポイントが貯まる」「その他」なども加えると、より網羅的になります。
4.「その他」や「わからない」も用意する
無理に選ばせず、回答者に選択肢がないストレスを与えないことで、データの正確性が高まります。
特にBtoB(法人向け)調査では、会社の状況について「わからない」と答えるケースが少なくありません。スクリーニング調査の段階で「わからない」を入れておくと、ターゲットの選定がスムーズになります。
一方で、実施後に「その他」ばかりに回答が集中した場合は、回答者が適切な選択肢を見つけられなかった=選択肢設計に不足があったサインと考えるべきです。その場合は、次回の設計で選択肢を見直し、「その他」に含まれていた回答を新しい選択肢として取り込むことが有効です。
▼関連記事
アンケートの選択肢の重要性・作成時の注意点・種類について解説
STEP5:回答順を決める
質問内容が決まったら、最後にどの順番で質問を並べるかを設計しましょう。
回答順は一見ささいな要素に思えますが、実は回答者のモチベーションや離脱率に大きく影響します。
回答順を考えるときの基本ルール
1.時間軸を意識する(過去→現在→未来)
回答者はアンケートに答えながら記憶を整理していくことが多いため、設問は時系列に沿って配置するとスムーズです。
例えば「商品を購入した場面」を聞く場合は、過去の経験(購入のきっかけ)→現在の利用状況→将来の意向という流れにすると、自然に思い出しやすく、回答の精度も高まります。
2.「答えやすさ」と「重要度」のバランスをとる
冒頭は「性別」「年齢」「利用経験」など、直感的に答えられるシンプルな質問でウォーミングアップするのが基本です。
ただし必ず聞きたい重めの質問がある場合は、序盤〜中盤に配置する方が安全です。最後に回してしまうと、離脱や疲れによる適当な回答のリスクが高まります。
3.シーンを思い出しやすい順にする
回答者はアンケートに答えながら記憶を整理していくこともできるので、
例えば「商品を購入した場面」を聞く場合は、過去の経験(購入のきっかけ)→現在の利用状況→将来の意向と流れを作ると、回答者が自然に思い出しやすく、回答の精度も高まります。
4.関連する質問はまとめる
「利用状況」「満足度」「改善点」など、関連性のある設問はまとめて配置した方が理解しやすく、回答もしやすくなります。
回答順は一見ささいな要素に思えますが、実は回答者のモチベーションや離脱率に大きく影響します。
回答順を考えるときの基本ルール
1.時間軸を意識する(過去→現在→未来)
回答者はアンケートに答えながら記憶を整理していくことが多いため、設問は時系列に沿って配置するとスムーズです。
例えば「商品を購入した場面」を聞く場合は、過去の経験(購入のきっかけ)→現在の利用状況→将来の意向という流れにすると、自然に思い出しやすく、回答の精度も高まります。
2.「答えやすさ」と「重要度」のバランスをとる
冒頭は「性別」「年齢」「利用経験」など、直感的に答えられるシンプルな質問でウォーミングアップするのが基本です。
ただし必ず聞きたい重めの質問がある場合は、序盤〜中盤に配置する方が安全です。最後に回してしまうと、離脱や疲れによる適当な回答のリスクが高まります。
3.シーンを思い出しやすい順にする
回答者はアンケートに答えながら記憶を整理していくこともできるので、
例えば「商品を購入した場面」を聞く場合は、過去の経験(購入のきっかけ)→現在の利用状況→将来の意向と流れを作ると、回答者が自然に思い出しやすく、回答の精度も高まります。
4.関連する質問はまとめる
「利用状況」「満足度」「改善点」など、関連性のある設問はまとめて配置した方が理解しやすく、回答もしやすくなります。
-
1万円からネットリサーチができる!サービスを確認する
-
無料でアンケートを作成してみるサーベロイドに登録する

アンケートの実施手順
アンケートは、実施手法によって作り方や注意点が変わります。
「誰に」「どこで」答えてもらうのかを踏まえて、適切な方式を選びましょう。
「誰に」「どこで」答えてもらうのかを踏まえて、適切な方式を選びましょう。
実施するアンケート手法に沿って作成
主な実施手法と特徴
1.紙媒体アンケート
店頭配布やイベント会場、展示会などで活用される、オフラインでの定番アンケート方法です。
対面でその場で回収できる場合は回答率が高く、回答者の反応を直接見られるというメリットがあります。一方で、持ち帰りや郵送回収になると回答率が下がりやすく、データ入力や集計の工数も増えるのが課題です。記入漏れや読み取りミスを防ぐため、選択式中心の設計にしておくと後処理がスムーズになります。
2.自社顧客向け(オンライン)
Googleフォームなどの無料ツールを使えば、手軽にアンケートを作成してメールやSNSで配布できます。
既存顧客リストを活用できる点が強みですが、回答者が自社顧客に偏りやすいため、回答を促す工夫が必要です。
特典や回答期限を設けることで、回収率を高めやすくなります。
▼関連記事
Googleフォームの作り方を徹底解説!メリットや便利な使い方まで紹介
3.一般生活者向け(オンライン調査)
自社顧客以外から幅広く回答を集めたい場合は、調査モニターを保有するリサーチプラットフォームの利用がおすすめです。
特に Surveroid であれば、
・600万人規模のモニター母集団から、全国の幅広い生活者にリーチできる
・アンケートの作成から配信・集計までをワンストップで完結できる
・初心者でも直感的に操作できる管理画面と、安心のサポート体制
・集計結果を見た後に「もっと理由を知りたい」と思えば、インタビュー調査まで一貫対応が可能
といったメリットがあり、信頼性の高いデータを効率よく収集・分析でき、調査から施策立案までスムーズにつなげられます。
自社で回答者を集めるのが難しい場合でも、Surveroidなら全国600万人規模のモニターからすぐに回収可能です。▶[詳細はこちら]
アンケートは実施手法によって最適な設計が変わります。
自社顧客に聞くのか、一般消費者から幅広く集めたいのかを整理し、それに合ったツールを選ぶことが成功の第一歩です。
1.紙媒体アンケート
店頭配布やイベント会場、展示会などで活用される、オフラインでの定番アンケート方法です。
対面でその場で回収できる場合は回答率が高く、回答者の反応を直接見られるというメリットがあります。一方で、持ち帰りや郵送回収になると回答率が下がりやすく、データ入力や集計の工数も増えるのが課題です。記入漏れや読み取りミスを防ぐため、選択式中心の設計にしておくと後処理がスムーズになります。
2.自社顧客向け(オンライン)
Googleフォームなどの無料ツールを使えば、手軽にアンケートを作成してメールやSNSで配布できます。
既存顧客リストを活用できる点が強みですが、回答者が自社顧客に偏りやすいため、回答を促す工夫が必要です。
特典や回答期限を設けることで、回収率を高めやすくなります。
▼関連記事
Googleフォームの作り方を徹底解説!メリットや便利な使い方まで紹介
3.一般生活者向け(オンライン調査)
自社顧客以外から幅広く回答を集めたい場合は、調査モニターを保有するリサーチプラットフォームの利用がおすすめです。
特に Surveroid であれば、
・600万人規模のモニター母集団から、全国の幅広い生活者にリーチできる
・アンケートの作成から配信・集計までをワンストップで完結できる
・初心者でも直感的に操作できる管理画面と、安心のサポート体制
・集計結果を見た後に「もっと理由を知りたい」と思えば、インタビュー調査まで一貫対応が可能
といったメリットがあり、信頼性の高いデータを効率よく収集・分析でき、調査から施策立案までスムーズにつなげられます。
自社で回答者を集めるのが難しい場合でも、Surveroidなら全国600万人規模のモニターからすぐに回収可能です。▶[詳細はこちら]
アンケートは実施手法によって最適な設計が変わります。
自社顧客に聞くのか、一般消費者から幅広く集めたいのかを整理し、それに合ったツールを選ぶことが成功の第一歩です。
最終確認を行って実施
アンケートが完成したら、配信前に必ず最終チェックを行いましょう。ちょっとした見落としでも、回答者の離脱やデータの信頼性低下につながることがあります。
チェックすべきポイント
1.質問文の誤字・表現の曖昧さ
誤字脱字や曖昧な表現があると信頼感を損ねます。第三者に読んでもらうことで、自分では気づけない部分を発見できます。
2.回答者目線での操作性
スマホやPCで実際に回答してみて、「選択肢が見づらい」「スクロールが多い」など不便がないか確認しましょう。特に現在はスマホ回答が主流のため、スマホでの見え方を必ずチェックすることが大切です。
3.論理チェック(スキップ設定や排他設定)
「購入した」を選んだのに、購入していない人向けの質問が出てくるなど、分岐設定のミスで不自然な流れになっていないかを確認しましょう。条件外の質問が続くと離脱や適当回答につながるため、スキップ設定・排他・必須項目に誤りがないかを念入りにチェックします。
4.回答時間の目安
自分で通し回答して時間を測りましょう。想定より長い場合は、設問を削る・選択肢を整理するなど、回答者の負担を減らす工夫も大切です。
アンケートは「作って終わり」ではなく、実際に回答者の立場になってテストすることが成功のカギです。小さな調整でも、回答率やデータの質に大きな差が出ます。
チェックすべきポイント
1.質問文の誤字・表現の曖昧さ
誤字脱字や曖昧な表現があると信頼感を損ねます。第三者に読んでもらうことで、自分では気づけない部分を発見できます。
2.回答者目線での操作性
スマホやPCで実際に回答してみて、「選択肢が見づらい」「スクロールが多い」など不便がないか確認しましょう。特に現在はスマホ回答が主流のため、スマホでの見え方を必ずチェックすることが大切です。
3.論理チェック(スキップ設定や排他設定)
「購入した」を選んだのに、購入していない人向けの質問が出てくるなど、分岐設定のミスで不自然な流れになっていないかを確認しましょう。条件外の質問が続くと離脱や適当回答につながるため、スキップ設定・排他・必須項目に誤りがないかを念入りにチェックします。
4.回答時間の目安
自分で通し回答して時間を測りましょう。想定より長い場合は、設問を削る・選択肢を整理するなど、回答者の負担を減らす工夫も大切です。
アンケートは「作って終わり」ではなく、実際に回答者の立場になってテストすることが成功のカギです。小さな調整でも、回答率やデータの質に大きな差が出ます。
集計・分析・レポーティング
アンケートを配信したあとは、集計・分析・レポート化のステップに進みます。せっかく集めたデータも、整理や分析が不十分だと“ただの数字の羅列”で終わってしまいます。
ここでは、結果を「活かせるデータ」に変えるための基本の流れを押さえましょう。
1. 集計(データを整える)
まずは、回答結果を整理して全体の傾向を把握します。
・単純集計:回答をそのまま集計し、全体像を把握する
例:「満足」と答えた人が全体の60%
・クロス集計:属性や条件ごとに分けて比較する
例:年代別・性別・利用経験別などで満足度を比較
単純集計だけでは「当たり前の結果」で終わることが多いため、クロス集計を前提に設問を設計しておくことが重要です。
▼関連記事
【マーケター必見!】クロス集計(クロス分析)とは?わかることやメリット・デメリット、見方を解説
2. 分析(仮説を検証する)
次に、集計した数字をもとに「なぜその結果になったのか」を読み解きます。単に数値を見るだけでなく、仮説を立てて検証する姿勢が大切です。
たとえば「価格が高いから不満なのか?」「認知度が低いから購入されないのか?」といった“理由”を探ることで、施策に直結するインサイトが得られます。
▼関連記事
アンケート結果の分析方法5選!ポイントや流れを解説
3. レポーティング(伝える)
最後に、分析結果をわかりやすく伝える形にまとめることが重要です。グラフや表を使って視覚的に整理し、「結論」から提示する構成を意識しましょう。
レポートの基本構成は以下の通りです。
・調査概要(目的・対象・方法)
・主な結果(数値・グラフ)
・考察(なぜそうなったか、どんな意味があるか)
・提案(次に何をすべきか)
▼関連記事
アンケート結果報告書の書き方とは?伝わるまとめ方と作成ポイントを解説
ここでは、結果を「活かせるデータ」に変えるための基本の流れを押さえましょう。
1. 集計(データを整える)
まずは、回答結果を整理して全体の傾向を把握します。
・単純集計:回答をそのまま集計し、全体像を把握する
例:「満足」と答えた人が全体の60%
・クロス集計:属性や条件ごとに分けて比較する
例:年代別・性別・利用経験別などで満足度を比較
単純集計だけでは「当たり前の結果」で終わることが多いため、クロス集計を前提に設問を設計しておくことが重要です。
▼関連記事
【マーケター必見!】クロス集計(クロス分析)とは?わかることやメリット・デメリット、見方を解説
2. 分析(仮説を検証する)
次に、集計した数字をもとに「なぜその結果になったのか」を読み解きます。単に数値を見るだけでなく、仮説を立てて検証する姿勢が大切です。
たとえば「価格が高いから不満なのか?」「認知度が低いから購入されないのか?」といった“理由”を探ることで、施策に直結するインサイトが得られます。
▼関連記事
アンケート結果の分析方法5選!ポイントや流れを解説
3. レポーティング(伝える)
最後に、分析結果をわかりやすく伝える形にまとめることが重要です。グラフや表を使って視覚的に整理し、「結論」から提示する構成を意識しましょう。
レポートの基本構成は以下の通りです。
・調査概要(目的・対象・方法)
・主な結果(数値・グラフ)
・考察(なぜそうなったか、どんな意味があるか)
・提案(次に何をすべきか)
▼関連記事
アンケート結果報告書の書き方とは?伝わるまとめ方と作成ポイントを解説
-
アンケート作成のポイントがわかる!資料をダウンロードする
-
初期費用や月額費一切なしサーベロイドに登録してみる
アンケート設計に役立つ質問例とテンプレート
アンケートを作るときに悩みやすいのが「どんな聞き方をすればいいのか?」という点です。
ここでは代表的な調査(顧客満足度調査・認知度調査・商品評価調査)の質問例とテンプレートを紹介します。
そのまま参考にするだけでなく、自社の目的に合わせてアレンジすることで、回答率が高く、改善につながるデータを得やすくなります。
ここでは代表的な調査(顧客満足度調査・認知度調査・商品評価調査)の質問例とテンプレートを紹介します。
そのまま参考にするだけでなく、自社の目的に合わせてアレンジすることで、回答率が高く、改善につながるデータを得やすくなります。
顧客満足度調査
最もよく実施されるアンケートの一つが顧客満足度(CS)調査です。
商品やサービスの「満足度」を数値化することで、現状把握や改善施策につなげることができます。
よく使われる質問例
「当社の商品にどの程度満足していますか?」
→ 回答形式:5段階評価(とても満足/やや満足/どちらともいえない/やや不満/とても不満)
「満足(不満)の理由を教えてください」
→ 回答形式:複数回答(品質・価格・デザイン・対応スピードなど)+自由記述
「家族や友人に勧める可能性はどれくらいありますか?」
→ 回答形式:単一回答(0〜10点評価)
設計のポイント
1.全体満足度+理由をセットで聞く
満足度の数値だけでは「なぜそうなのか」がわかりません。“満足・不満の理由”を合わせて質問し、改善につながるデータを得ましょう。
2.NPS(ネットプロモータースコア)を活用する
「あなたはこの商品を友人や同僚に勧めたいと思いますか?」(0〜10点評価)と聞くことで、将来の利用意向を測定できます。
3.改善に直結する粒度で設問を作る
「サービスに不満」と聞くだけでは抽象的すぎます。 「価格」「対応」「利便性」などに分けて質問すると、改善すべきポイントが明確になります。
▼関連記事
顧客満足度アンケートの作り方を徹底解説!すぐに使える質問例と分析のコツ
商品やサービスの「満足度」を数値化することで、現状把握や改善施策につなげることができます。
よく使われる質問例
「当社の商品にどの程度満足していますか?」
→ 回答形式:5段階評価(とても満足/やや満足/どちらともいえない/やや不満/とても不満)
「満足(不満)の理由を教えてください」
→ 回答形式:複数回答(品質・価格・デザイン・対応スピードなど)+自由記述
「家族や友人に勧める可能性はどれくらいありますか?」
→ 回答形式:単一回答(0〜10点評価)
設計のポイント
1.全体満足度+理由をセットで聞く
満足度の数値だけでは「なぜそうなのか」がわかりません。“満足・不満の理由”を合わせて質問し、改善につながるデータを得ましょう。
2.NPS(ネットプロモータースコア)を活用する
「あなたはこの商品を友人や同僚に勧めたいと思いますか?」(0〜10点評価)と聞くことで、将来の利用意向を測定できます。
3.改善に直結する粒度で設問を作る
「サービスに不満」と聞くだけでは抽象的すぎます。 「価格」「対応」「利便性」などに分けて質問すると、改善すべきポイントが明確になります。
▼関連記事
顧客満足度アンケートの作り方を徹底解説!すぐに使える質問例と分析のコツ

認知度・ブランド調査
商品やサービスが「どれくらい知られているのか」の把握、「どんなイメージを持たれているか」を探るのが認知度・ブランド調査です。マーケティング戦略や広報活動の効果測定に欠かせない調査のひとつです。
よく使われる質問例
「このブランドを知っていますか?」
→ 回答形式:単一回答(よく知っている(内容まで理解している)/名前を聞いたことがある程度/全く知らなかった)
「どこでこの商品・サービスを知りましたか?」
→ 回答形式:複数回答(テレビCM/SNS/ネット検索/口コミ/店頭 など)
「このブランドにどんなイメージを持っていますか?」
→ 回答形式:複数回答(信頼できる/価格が高い/先進的/親しみやすい など)
設計のポイント
1.認知度+イメージの両面で聞く
単に「知っている人の割合」を測るだけでなく、どう評価されているかまで掘り下げると活用度が高まります。
2.競合比較を意識する
自社ブランドだけでなく、競合ブランドと並べて聞くことでポジショニングが明確になります。
3.経路分析を取り入れる
認知のきっかけ(広告/口コミ/体験)を押さえることで、どの施策に投資すべきかが見えてきます。
▼関連記事
今すぐ実践可能!認知度調査を成功に導く設問例と実施方法
よく使われる質問例
「このブランドを知っていますか?」
→ 回答形式:単一回答(よく知っている(内容まで理解している)/名前を聞いたことがある程度/全く知らなかった)
「どこでこの商品・サービスを知りましたか?」
→ 回答形式:複数回答(テレビCM/SNS/ネット検索/口コミ/店頭 など)
「このブランドにどんなイメージを持っていますか?」
→ 回答形式:複数回答(信頼できる/価格が高い/先進的/親しみやすい など)
設計のポイント
1.認知度+イメージの両面で聞く
単に「知っている人の割合」を測るだけでなく、どう評価されているかまで掘り下げると活用度が高まります。
2.競合比較を意識する
自社ブランドだけでなく、競合ブランドと並べて聞くことでポジショニングが明確になります。
3.経路分析を取り入れる
認知のきっかけ(広告/口コミ/体験)を押さえることで、どの施策に投資すべきかが見えてきます。
▼関連記事
今すぐ実践可能!認知度調査を成功に導く設問例と実施方法

コンセプト調査
新商品やサービスを開発する前に、そのコンセプト(企画案・アイデア)がターゲットに受け入れられるかを確認するのがコンセプト調査です。
「実際に発売してから失敗するリスクを減らす」ために、多くの企業が導入しています。
よく使われる質問例
「このコンセプトにどのような印象を持ちましたか?」
→ 回答形式:単一回答(とても良い/良い/どちらともいえない/あまり良くない/全く良くない)
「この商品が発売されたら購入したいと思いますか?」
→ 回答形式:単一回答(必ず購入したい/たぶん購入する/どちらともいえない/あまり購入しない/全く購入しない)
「この商品の魅力に思ったところを全てお知らせください。」
→ 回答形式:複数回答(特徴①/特徴②/特徴③/特徴④/特徴⑤)
設計のポイント
1.第一印象+購入意向をセットで聞く
「好印象でも買わない」というケースがあるため、購入意向の確認は必須です。
2.ターゲット層を限定する
誰にとって魅力的なのかを明確にするため、対象者をしっかり絞って調査します。
3.定性的調査と組み合わせる
定量調査で全体傾向を把握し、インタビューで深掘りするのが効果的です。
▼関連記事
コンセプト受容性調査とは?目的・手法・設問例・費用まで徹底解説
「実際に発売してから失敗するリスクを減らす」ために、多くの企業が導入しています。
よく使われる質問例
「このコンセプトにどのような印象を持ちましたか?」
→ 回答形式:単一回答(とても良い/良い/どちらともいえない/あまり良くない/全く良くない)
「この商品が発売されたら購入したいと思いますか?」
→ 回答形式:単一回答(必ず購入したい/たぶん購入する/どちらともいえない/あまり購入しない/全く購入しない)
「この商品の魅力に思ったところを全てお知らせください。」
→ 回答形式:複数回答(特徴①/特徴②/特徴③/特徴④/特徴⑤)
設計のポイント
1.第一印象+購入意向をセットで聞く
「好印象でも買わない」というケースがあるため、購入意向の確認は必須です。
2.ターゲット層を限定する
誰にとって魅力的なのかを明確にするため、対象者をしっかり絞って調査します。
3.定性的調査と組み合わせる
定量調査で全体傾向を把握し、インタビューで深掘りするのが効果的です。
▼関連記事
コンセプト受容性調査とは?目的・手法・設問例・費用まで徹底解説

-
ネットリサーチで使えるテンプレまとめ調査テンプレートをダウンロードする
-
調査テンプレートを使って調査可能サーベロイドに登録してみる

アンケートのよくある失敗パターンと回避法
失敗例を知っておけば、事前に避けることができます。ここでは典型的なNG例と対策を紹介します。
回答数が集まらない
アンケートの失敗で最も多いのが、回答数が思うように集まらないケースです。十分なサンプルが集まらなければ、統計的に意味のある分析ができず、調査結果の信頼性も低下します。
よくある原因
1.対象者が適切に設定されていない
誰に聞けば有効なデータになるのかを明確にせず、広すぎたり狭すぎたりするターゲット設定をしている。
2.回答の負担が大きい
設問数が多すぎたり、自由記述ばかりで面倒に感じられ、離脱されやすい。
3.インセンティブ不足
回答するメリットが弱いと、特に一般生活者からは回答を集めにくい。
回避法
1.配信対象を見直す
自社顧客だけでは限界がある場合、モニターを保有するリサーチプラットフォーム(例:Surveroid)を活用する。
2.回答者にとっての負担を減らす
設問数は目的達成に必要な最小限にし、10分以内で答えられるボリュームに収める。
3.回答意欲を高める工夫をする
アンケート冒頭で「所要時間」を明示する、インセンティブ(ポイントや抽選)を用意する、といった工夫で参加率が上がる。
よくある原因
1.対象者が適切に設定されていない
誰に聞けば有効なデータになるのかを明確にせず、広すぎたり狭すぎたりするターゲット設定をしている。
2.回答の負担が大きい
設問数が多すぎたり、自由記述ばかりで面倒に感じられ、離脱されやすい。
3.インセンティブ不足
回答するメリットが弱いと、特に一般生活者からは回答を集めにくい。
回避法
1.配信対象を見直す
自社顧客だけでは限界がある場合、モニターを保有するリサーチプラットフォーム(例:Surveroid)を活用する。
2.回答者にとっての負担を減らす
設問数は目的達成に必要な最小限にし、10分以内で答えられるボリュームに収める。
3.回答意欲を高める工夫をする
アンケート冒頭で「所要時間」を明示する、インセンティブ(ポイントや抽選)を用意する、といった工夫で参加率が上がる。
回答者に直接的な回答を求める
アンケートでありがちな失敗のひとつが、回答者に直接すぎる質問を投げかけてしまうことです。「どうすればもっと利用してもらえますか?」「10年前と比べてどう変わりましたか?」といった質問は、一見有効に思えますが、回答者にとっては難しすぎたり抽象的すぎたりします。
なぜ失敗するのか
1.回答者が専門家ではない
改善策や要因分析を答えるのは研究者やコンサルタントの仕事。生活者に「どう改善すべきか」と聞いても、的外れな答えが返ってくるリスクが高い。
2.記憶の限界がある
「10年前と比べて…」のように長期的な比較を求めると、多くの人が正確に答えられません。結果として適当な回答になり、データの信頼性を下げてしまいます。
回避法
1.具体的な行動や経験を聞く
「直近3か月でこの商品を購入しましたか?」「購入したときにどんな点に満足/不満を感じましたか?」といった質問なら、回答者の記憶を呼び起こしやすい。
2.選択肢で補助する
自由回答ではなく「価格/品質/デザイン/対応スピード」などの選択肢を提示することで、回答者は答えやすくなり、分析もしやすいデータが得られます。
3.改善のヒントは分析から導く
「どうすれば利用者が増えるか」を直接聞くのではなく、「不満点はどこに集中しているか」を分析して、改善策を導き出すのが調査の本来の役割です。
アンケートで「改善策」を直接聞いても、必ずしも実用的な答えは得られません。
具体的な行動や経験を聞く → 分析で改善策を導くという設計が、正しいアプローチです。
なぜ失敗するのか
1.回答者が専門家ではない
改善策や要因分析を答えるのは研究者やコンサルタントの仕事。生活者に「どう改善すべきか」と聞いても、的外れな答えが返ってくるリスクが高い。
2.記憶の限界がある
「10年前と比べて…」のように長期的な比較を求めると、多くの人が正確に答えられません。結果として適当な回答になり、データの信頼性を下げてしまいます。
回避法
1.具体的な行動や経験を聞く
「直近3か月でこの商品を購入しましたか?」「購入したときにどんな点に満足/不満を感じましたか?」といった質問なら、回答者の記憶を呼び起こしやすい。
2.選択肢で補助する
自由回答ではなく「価格/品質/デザイン/対応スピード」などの選択肢を提示することで、回答者は答えやすくなり、分析もしやすいデータが得られます。
3.改善のヒントは分析から導く
「どうすれば利用者が増えるか」を直接聞くのではなく、「不満点はどこに集中しているか」を分析して、改善策を導き出すのが調査の本来の役割です。
アンケートで「改善策」を直接聞いても、必ずしも実用的な答えは得られません。
具体的な行動や経験を聞く → 分析で改善策を導くという設計が、正しいアプローチです。
集計をやり込めてない
アンケートを実施しても、集計や分析を十分に行わないまま「結果が出なかった」と終わってしまう失敗はよくあります。
せっかく回答が集まっても、単純集計だけでは浅い気づきしか得られず、調査が形骸化してしまいます。
なぜ失敗するのか
1.単純集計だけで満足してしまう
「満足:60%、不満:40%」といった数字を出すだけで終わり、背景や違いを探らない。
2.クロス集計を設計段階で考えていない
性別・年代・利用状況などで比較する前提で設問を作らないと、分析したくてもデータが取れない。
3.分析視点が曖昧
「なんとなく数字を出す」だけでは、次のアクションに結びつかない。
回避法
1.クロス集計を前提に設問を設計する
性別・年代・利用経験など、比較したい切り口を事前に決めて設問を組み込む。
2.仮説検証の視点を持つ
「価格が高いから売れないのか?」「認知度が低いから買われないのか?」といった仮説をもとに数字を解釈する。
3.可視化して伝える
集計結果は表やグラフで整理し、誰が見ても次のアクションを考えられる形にする。
アンケートは「集める」ことが目的ではなく、分析して次のアクションにつなげることが本質です。
単純集計だけで終わらず、クロス集計や仮説検証を行うことで、調査が事業に貢献するレベルに引き上がります。
せっかく回答が集まっても、単純集計だけでは浅い気づきしか得られず、調査が形骸化してしまいます。
なぜ失敗するのか
1.単純集計だけで満足してしまう
「満足:60%、不満:40%」といった数字を出すだけで終わり、背景や違いを探らない。
2.クロス集計を設計段階で考えていない
性別・年代・利用状況などで比較する前提で設問を作らないと、分析したくてもデータが取れない。
3.分析視点が曖昧
「なんとなく数字を出す」だけでは、次のアクションに結びつかない。
回避法
1.クロス集計を前提に設問を設計する
性別・年代・利用経験など、比較したい切り口を事前に決めて設問を組み込む。
2.仮説検証の視点を持つ
「価格が高いから売れないのか?」「認知度が低いから買われないのか?」といった仮説をもとに数字を解釈する。
3.可視化して伝える
集計結果は表やグラフで整理し、誰が見ても次のアクションを考えられる形にする。
アンケートは「集める」ことが目的ではなく、分析して次のアクションにつなげることが本質です。
単純集計だけで終わらず、クロス集計や仮説検証を行うことで、調査が事業に貢献するレベルに引き上がります。
まとめ
アンケートは「とりあえず作って配信する」だけでは、意味のある結果が得られません。
成功のポイントは、設計 → 実施 → 分析 → 改善 の一連の流れをしっかり押さえることにあります。
・設計段階では、調査の目的を明確にし、質問文・選択肢・回答順を丁寧に組み立てる
・実施段階では、配信方法やツールを選び、回答者が答えやすい環境を整える
・分析段階では、単純集計で終わらずクロス集計や仮説検証を行い、次のアクションにつなげる
さらに、よくある失敗パターン(回答数が集まらない、直接的な回答を求めすぎる、集計が浅い)を避けるだけでも、データの価値は大きく変わります。
まずは小さな調査から実践し、改善を重ねていけば、誰でも精度の高いアンケートが作れるようになります。
成功のポイントは、設計 → 実施 → 分析 → 改善 の一連の流れをしっかり押さえることにあります。
・設計段階では、調査の目的を明確にし、質問文・選択肢・回答順を丁寧に組み立てる
・実施段階では、配信方法やツールを選び、回答者が答えやすい環境を整える
・分析段階では、単純集計で終わらずクロス集計や仮説検証を行い、次のアクションにつなげる
さらに、よくある失敗パターン(回答数が集まらない、直接的な回答を求めすぎる、集計が浅い)を避けるだけでも、データの価値は大きく変わります。
まずは小さな調査から実践し、改善を重ねていけば、誰でも精度の高いアンケートが作れるようになります。
アンケートをするならSurveroid
ここまでアンケートの作り方を解説してきましたが、実際に運用するとなると「回答者を集める」「配信する」「集計する」といった作業に意外と手間がかかります。
そんなときに頼れるのが、セルフ型アンケートツール Surveroid(サーベロイド) です。
▼Surveroidの特徴
600万人規模のモニター母集団
自社顧客だけでなく、潜在層や幅広い生活者にリーチ可能。信頼性の高いデータを短期間で集められます。
ワンストップで完結
アンケート作成から配信・回収・集計まで、すべてオンラインで効率的に行えます。
初心者でも安心
直感的に操作できる管理画面とサポート体制により、リサーチ経験が浅い担当者でもすぐに調査を始められます。
定量+定性の一貫対応
数字を集めるだけでなく、必要に応じてインタビュー調査まで一貫して実施可能。数字の背景にある「本音」まで把握できます。
実際に、アンケート調査とインタビュー調査を組み合わせてリサーチを行うユーザーの事例も多数公開しています。
そんなときに頼れるのが、セルフ型アンケートツール Surveroid(サーベロイド) です。
▼Surveroidの特徴
600万人規模のモニター母集団
自社顧客だけでなく、潜在層や幅広い生活者にリーチ可能。信頼性の高いデータを短期間で集められます。
ワンストップで完結
アンケート作成から配信・回収・集計まで、すべてオンラインで効率的に行えます。
初心者でも安心
直感的に操作できる管理画面とサポート体制により、リサーチ経験が浅い担当者でもすぐに調査を始められます。
定量+定性の一貫対応
数字を集めるだけでなく、必要に応じてインタビュー調査まで一貫して実施可能。数字の背景にある「本音」まで把握できます。
実際に、アンケート調査とインタビュー調査を組み合わせてリサーチを行うユーザーの事例も多数公開しています。
広いターゲットに向けて定量的に実態を把握する調査であれば、今からでもすぐに実施できます。
Surveroidなら、傾向を数字で掴み、その背景をインタビューで深掘りする――
そんなマーケティングリサーチの流れをひとつのツールで完結させることが可能です。
もし「どんな調査をすべきか迷っている」という方がいれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
Surveroidなら、傾向を数字で掴み、その背景をインタビューで深掘りする――
そんなマーケティングリサーチの流れをひとつのツールで完結させることが可能です。
もし「どんな調査をすべきか迷っている」という方がいれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
61 件

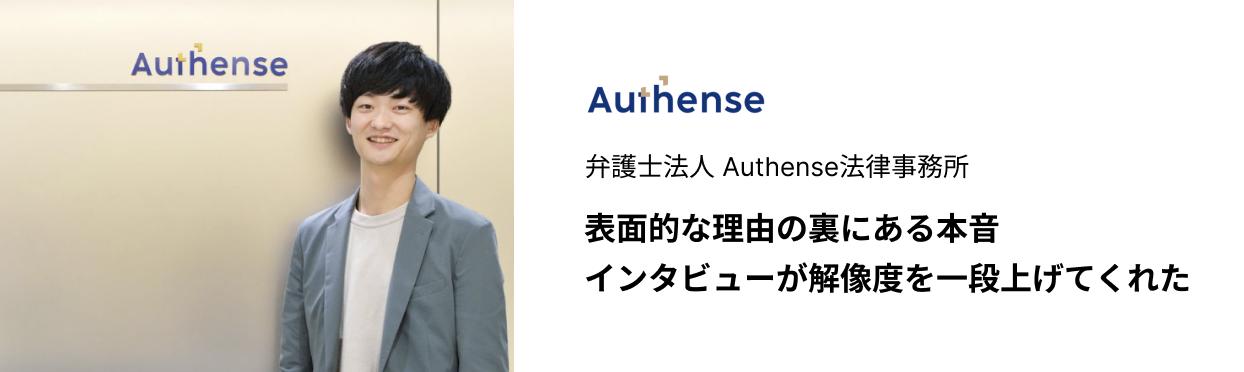
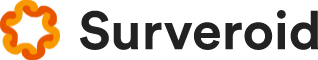 サーベロイドでリサーチをはじめませんか?
サーベロイドでリサーチをはじめませんか?




