目次
本記事では、調査結果をわかりやすく伝えるための6つの具体的なまとめ方を解説します。調査データを読み手に伝えるためのポイントや、作成の際に役立つ報告書例も具体的にご紹介しますので、これからレポートを作成する方はぜひ参考にしてください。
アンケート結果報告書の目的
特にマーケティングや商品開発、サービス改善などにおいては、数値の傾向だけでなく、背景や調査の狙いを踏まえた報告が重要です。報告書は、単なる記録ではなく、調査の価値を伝え、行動につなげるための資料として位置づけられます。
アンケートの調査結果を報告するメリット
ここでは、アンケート結果の報告がもたらす主な3つの効果を紹介します。
経営陣と現場の意思疎通に貢献
組織やプロジェクトの課題の共有・解決につながる
社内外からの会社の評価向上につながる
調査報告書とは
特にアンケート調査においては、調査票に基づいて得られた回答を集計・分析し、分かりやすい表現やグラフで可視化した上で報告書にまとめることで、社内外の関係者がデータをもとに判断・議論できるようになります。
また、調査報告書は記録としての役割も持つため、同様の調査を繰り返す際の比較資料や、過去の戦略を振り返る上でも有用です。わかりやすく正確に構成された報告書は、企業の信頼性やデータ活用力を示す証拠資料としても活躍します。
アンケートを作成する際の流れ
1.アンケートの目的を決める
2.アンケート内容や手法を決める
3.調査票を作成し実施する
4.結果を集計・分析して報告書にまとめる

アンケート結果を伝える6つのグラフ活用法
ここでは、アンケート調査報告書でよく使われる6つのグラフと、その活用シーンをご紹介します。
円グラフ
たとえば、マーケットシェアや予算配分、利用チャネルの内訳など、全体に対する割合やバランス感を一目で把握したい場面に適しています。色分けすれば各項目の違いも明確に表現でき、視覚的に訴求力のある資料を作成できます。
一方で、項目数が多くなると見づらくなり、細かい比較や複数設問の分析には不向きです。その場合は、棒グラフなど別のグラフ形式を検討するとよいでしょう。
棒グラフ(縦棒・横棒)
ただし、項目数が多すぎると視認性が下がるほか、構成比の全体感を伝えるにはやや不向きな場合もあります。伝えたい内容に応じて、円グラフなど他の形式と使い分けるのが効果的です。
積み上げ棒グラフ
たとえば、「年代別の評価傾向」や「属性別の意見分布」など、複数の層や設問における回答傾向を比較・分析する場面に適しています。「あてはまる」「ややあてはまる」などの評価を項目ごとに並べて見せることで、傾向を一目で捉えやすくなります。
折れ線グラフ
レーダーチャート
たとえば、製品やサービスに対する評価を「やわらかい」「明るい」「高級感がある」などの印象項目で可視化すれば、ブランドイメージや訴求力の傾向を直感的に把握することができます。また、複数ブランドや競合製品を同じ軸上で比較することで、優位性や改善ポイントが明確になります。
項目数が多すぎると図が煩雑になり、個々の違いが分かりにくくなる点には注意が必要です。また、自由回答のような非定量データには不向きなため、明確なスコア評価がある設問で活用しましょう。
散布図
たとえば、「広告費と売上」「サービスの価格と満足度」など、“Aが増えるとBも増えるか?”といった関係性を探る調査に適しています。単純集計やクロス集計では見えにくい相関やパターンを見出したいときに力を発揮します。
一方で、データポイントが多すぎると視認性が低下しやすく、外れ値の影響を受けやすい点には注意が必要です。また、見た目で相関がありそうに見えても因果関係とは限らないため、結果の解釈には慎重さも求められます。

調査報告書作成のポイント
ここでは、報告書作成時に押さえておきたい基本のポイントを紹介します。
「どのような目的で」「誰に」対しての報告書なのかの目的とターゲットを意識する
主な公開先を大きく2つに分けると、社内(上司、役員など)か社外(取引先、一般消費者など)になります。
誰が見てもわかりやすいものであることや提出期限を守ることは、公開先が違ってももちろん大切なポイントとなりますが、社内か社外で重視するポイントが僅かに異なります。
社内に報告書を提出するときは、日々の業務で忙しい中確認してもらう必要があるため、簡潔かつ重要事項がわかりやすくまとまっていることが求められます。ぱっと見た時に視覚的に理解できるようにグラフを用いたり、重要な箇所にマークをするなど見て欲しい箇所を目立たせると良いでしょう。
また、社外向けの報告書は、レイアウトを工夫し、空白やグラフを効果的に用いて「見栄えの美しさ」にこだわることが重要です。自社商品をアピールしたい場合は商品のイメージにあった色合いやデザインにしたり、競合商品と比較をする際は自社商品を目立たせたりするなどの工夫をすると直感的理解に繋がるでしょう。
私見を排除して作成する
分析者の印象や主観的な解釈をそのまま記載してしまうと、読み手の誤解や不信を招く恐れがあります。
特に示唆や解釈を述べる場面では、「〜という傾向が見られた」「〜と回答した人が多かった」というように、根拠となるデータを添えて書くことが大切です。報告書の信頼性を保つためにも、私見は極力排除し、客観的表現を心がけましょう。
要約は必ず載せる
要約を読むことで、読み手は全体像を把握しやすくなり、その後の詳細な内容への理解もスムーズに進みます。特に報告内容が多岐にわたる場合、冒頭に「結論」や「要点」がまとまっていることで、読み手のストレスを軽減できます。
構成としては、「タイトル」→「要約」→「詳細」の3段構造がおすすめです。
内容によっては報告書が何十ページにも及ぶことがあり、最後まで読まなければ結果がつかめない資料では、読み手に負担をかけてしまいます。“まず結果を知りたい”という読み手の視点を考えれば、要約は欠かせない要素です。
要約には以下のような内容を簡潔に盛り込みましょう。
・調査の目的
・対象や手法の簡単な説明
・主な結果・傾向
・特に注目すべき示唆や結論
このように、調査の全体像 → 詳細なデータへとズームインしていく構成にすることで、論理的かつ読みやすい報告書が実現します。
所感は調査結果と分けて記載する
ただし、所感は調査結果(要約や詳細情報)と混在させず、必ず明確に分けて記載することが重要です。事実と意見が混ざってしまうと、読み手がどこまでを客観的なデータとみなすべきか判断しづらくなり、報告書全体の信頼性が損なわれるおそれがあります。
一般的には、本文の最後に「所感」「考察」「補足コメント」といった項目を設けて記載すると自然な構成になります。
また、所感の内容は必ず調査テーマと一貫性を保ち、事実に基づいた視点で記述することが大切です。単なる感想ではなく、「この結果からどんな示唆が得られるか」「どのような打ち手につながるか」といった前向きな考察を添えることで、より実用的な報告書に仕上がります。
-
提案時の根拠となるデータを取ろうサービスを見てみる
-
1万円からターゲットへ調査可能サーベロイドに登録してみる
調査報告書の項目
ここでは、調査報告書に盛り込むべき主な構成要素と、それぞれの書き方のポイントについて解説します。
1.報告書のタイトル
社内向けであれば「〇〇に関する実態調査報告書」など端的なタイトルが適しています。外部向けの場合は、「〜の○割が購入を検討」といった数値を含めるなど、読み手の関心を引く工夫を加えると効果的です。
2.調査の背景・目的
下記は一例です。
『当社の強みである○○部門について新ターゲット層の獲得を推進したいという背景があり、△△を対象に□□を明らかにし、今後の新領域展開への示唆を得ることを目的としています。』
3.調査の概要
下記は一例です。
調査名:○○実態調査
調査方法:インターネット調査
調査期間:2022年1月21日(金)~2022年1月24日(月)
対象者:20~69歳/既婚女性/全国
回収数:1,000サンプル
4.調査の回収状況
5.調査結果の概要
6.調査結果の詳細
概要と齟齬がないように作成することはもちろん、テキストだけではなく、表やグラフなどを活用して数値データを視覚的に理解できるようにわかりやすく作成しましょう。読みやすさを重視するため、シンプルな文章や見出しを意識するとより良いです。
7.調査結果に対しての所感
上述したように、報告書は今後の意思決定における基本的な資料になり得るため、事実に基づいた自分の意見を具体的に述べることが重要です。また、事実とはっきり分けて書くことがわかりやすい報告書を作成するポイントになります。
-
消費者の声を反映させた報告が出来るセルフ型アンケートツールとは
-
登録から最短翌日にデータ回収完了サーベロイドに登録してみる
調査報告書のサンプル
調査報告書の例1(オンライン消費について)
2022年1月27日
△△部△△課○○部長(宛名)
△△部△△課○○○○(差出人)
オンライン消費に関する調査報告書
標記の件について調査を行いましたので、下記の通りご報告いたします。
調査の趣旨
新型コロナウイルスの感染拡大により外出自粛が要請され、百貨店等の実店舗に影響が及んでいる中、オンラインでの購買活動について消費者の行動に影響が出たのか、ネットショッピング事情に関して調査を実施しました。オンライン消費の実態について明らかにし、今後のEC事業参入時の参考にすることを目的としています。
調査方法
期間:2022年1月21日(金)~2022年1月24日(月)
対象:20~69歳/男女/全国
方法:インターネット調査
調査結果概要
7割を超える人が直近1ヶ月間でネットショッピングをしたと回答し、特に60代以上の高齢層の利用に増加傾向がありました。また、外出機会が減った分、ネットショッピングにかけることのできる予算も上がったことがわかりました。ネットで購入できるものが増えたことや、欲しいものがすぐに見つかる点がコロナ禍の現在利用頻度が上がっている要因となっています。
調査詳細
-
ネットショッピング利用状況
(直近1ヶ月の利用頻度、頻度の増減、今後の利用意向についてなど) -
ネットショッピングを利用する際に重視するポイント
(価格、届くまでの期間、併用できるポイント、クーポンの有無、口コミ・レビューなど) -
ネットショッピングの使い方
(店舗にないものを買う、いつも使用しているものを買う、忙しいとき、ポイントを貯めるなど) -
ネットショッピングにかける予算
(予算の変化や1回あたりの平均利用額など) -
ネットで購入しているもの
(日用品・生活雑貨、食品(生鮮食品・米・油など)、ファッション(衣類・靴など)、家電・AV機器、雑誌・書籍など)
所感
今回のアンケートの結果では、外出自粛を受けてネットショッピング利用が増え、今後も増加傾向にあることがわかりました。ネットショッピングの手軽さを再確認し、全世代においてネット利用が一般的になっていることから、これまでEC事業に足を踏み入れてこなかった自社においても、オンラインでの収益化が見込める結果だと感じます。
以上
調査報告書の例2(新商品の浸透度について)
2022年1月27日
△△部△△課○○部長(宛名)
△△部△△課○○○○(差出人)
新商品「□□」の売上状況に関する調査報告書
標記の件について調査を行いましたので、下記の通りご報告いたします。
調査概要
調査目的:新商品「□□」の市場での浸透状況や利用実態の確認
調査期間:2021年12月1日(水)~31日(金)
調査方法:実際の購買データによるPOS分析
調査対象者:新商品を購入した顧客
調査結果の要約
新たに販売された「□□」がどのくらいユーザーに受け入れられているか、競合他社の売上状況や自社の他商品との比較も含めて現状を把握するために調査しました。売上が上がっている店舗がある一方、伸び悩んでいる店舗もあり、店舗に合った対策を検討することが必要です。
調査結果
-
新商品の販売状況
(よく売れる時間帯、売上が伸びている店舗、どれくらいの価格で売れているのか、リピーターの有無) -
シェアの比較
(競合の売上と比較、自社の他商品と比較) -
店舗別の売上
(店舗別の売上、各店舗での新商品販売に対する取り組み、売上が伸びている店舗の施策)
所感
売上が伸び悩んでいる店舗がある一方で、順調に売上を伸ばしている店舗があることから、売れる商品であることはわかりました。なぜ伸びているのかをさらに分析を進め、立地や客層を考えたキャンペーンや売り場構成、セット販売などの施策の見直しを図り、今後の対策を立てることが必要だと考えられます。
以上
調査報告書の作成についてよくある質問
調査報告書はどのくらいのボリュームで作成するべき?
重要なのはページ数よりも「必要な情報が整理されていて、すぐに理解できるか」です。
フォントや文字サイズは何が良い?
文字サイズは本文で11〜12pt、見出しで14pt前後が推奨されます。フォントとサイズを統一しつつ、強調したい箇所にだけ変化をつけると、視線誘導もしやすくなります。
まとめ
また、セルフ型リサーチサービスのSurveroid(サーベロイド)でアンケートを実施すると、回収データを集計するのはもちろん、オプションとしてグラフ出力機能が付属しています。アンケート結果のまとめ作業をサポートするツールとしても使用いただけるかと思います。


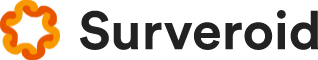 サーベロイドでリサーチをはじめませんか?
サーベロイドでリサーチをはじめませんか?




