目次
アンケートを行うときに、何人にアンケートを答えてもらえば良いか迷ったことはないでしょうか?
もちろん対象者全員にアンケートが取れたら完璧なデータを得ることができますが、例えば国内の20代女性全てに対してアンケートを取ることは現実的ではありません。
本記事では、誤差が生じる範囲と信頼度を理解することで何人から回答を得れば良いのかがわかるようになりますので、是非ご覧ください。
もちろん対象者全員にアンケートが取れたら完璧なデータを得ることができますが、例えば国内の20代女性全てに対してアンケートを取ることは現実的ではありません。
本記事では、誤差が生じる範囲と信頼度を理解することで何人から回答を得れば良いのかがわかるようになりますので、是非ご覧ください。
-
最短12時間で100人以上の回収が出来る!サーベロイドでアンケートをする

「サンプル数」と「サンプルサイズ」の違い
まず「サンプル数」と「サンプルサイズ」の違いについて解説します。
これについて誤解されているケースが多いのですが、まったく違う意味を持っています。
「サンプル数」とは
実施したアンケートの数。
「サンプルサイズ」とは
アンケートの対象となる人数(n数)です。
例えば10代から60代までの年代別に同様のアンケートを1,000人ずつに行った場合、
「サンプル数」が6、「サンプルサイズ」が各1,000ということになります。
また、サンプルサイズが複数の場合の例は次の通りです。
あるショップの利用者数の中から、スマホ決済を利用した人の数を調査した例を使ってご説明します。
調査は合計5回行われ、毎回調査人数は変更しました。
①1回目:全利用者の中から500人を抽出
②2回目:全利用者の中から100人を抽出
③3回目:全利用者の中から400人を抽出
④4回目:全利用者の中から200人を抽出
⑤5回目:全利用者の中から300人を抽出
この場合の「サンプル数」は5、「サンプルサイズ」は500、100、400、200、300となります。
この違いを覚えておくと、実際にリサーチを行う際スムーズに進めることが出来ます。
ただし、誤解されていることが多く一般的には「サンプル数」の方が浸透していることもありますので、この記事では「サンプルサイズ」を「回収サンプル数」という言葉で説明してきます。
これについて誤解されているケースが多いのですが、まったく違う意味を持っています。
「サンプル数」とは
実施したアンケートの数。
「サンプルサイズ」とは
アンケートの対象となる人数(n数)です。
例えば10代から60代までの年代別に同様のアンケートを1,000人ずつに行った場合、
「サンプル数」が6、「サンプルサイズ」が各1,000ということになります。
また、サンプルサイズが複数の場合の例は次の通りです。
あるショップの利用者数の中から、スマホ決済を利用した人の数を調査した例を使ってご説明します。
調査は合計5回行われ、毎回調査人数は変更しました。
①1回目:全利用者の中から500人を抽出
②2回目:全利用者の中から100人を抽出
③3回目:全利用者の中から400人を抽出
④4回目:全利用者の中から200人を抽出
⑤5回目:全利用者の中から300人を抽出
この場合の「サンプル数」は5、「サンプルサイズ」は500、100、400、200、300となります。
この違いを覚えておくと、実際にリサーチを行う際スムーズに進めることが出来ます。
ただし、誤解されていることが多く一般的には「サンプル数」の方が浸透していることもありますので、この記事では「サンプルサイズ」を「回収サンプル数」という言葉で説明してきます。
-
500万人からターゲットを絞り込める!サーベロイドでアンケートをする
回収サンプル数を決める=どれくらい誤差が出てもよいかを考える事

アンケートに回答してもらう人数を決めることは、「どれくらい誤差が出てもよいと考えるか」を決める事です。
例えば、30人のクラス全員から回答を集める場合は「全数調査」と言い、誤差を考える必要はありません。
一方で、例えば「20代男性の調理率を調べたい」となった場合、日本全国の20代男性からアンケートを取る事は不可能に近い為、全国の20代男性を「母集団」とし、一部を「標本」として取り出し、この一部の方にアンケートを答えてもらいます。
標本のアンケート結果から母集団の値を推定する事を「標本調査」と言います。
当然推定なので誤差が発生します。
「どれくらい誤差が出てもよいと考えるか」とは実際にはどのように考えるのかを詳しく解説していきます。
例えば、30人のクラス全員から回答を集める場合は「全数調査」と言い、誤差を考える必要はありません。
一方で、例えば「20代男性の調理率を調べたい」となった場合、日本全国の20代男性からアンケートを取る事は不可能に近い為、全国の20代男性を「母集団」とし、一部を「標本」として取り出し、この一部の方にアンケートを答えてもらいます。
標本のアンケート結果から母集団の値を推定する事を「標本調査」と言います。
当然推定なので誤差が発生します。
「どれくらい誤差が出てもよいと考えるか」とは実際にはどのように考えるのかを詳しく解説していきます。
信頼度95のサンプル数は何人?
アンケート調査の結果を信頼できるものにするためには、適切なサンプル数を確保することが重要です。
信頼度95%の精度を求める場合の母集団ごとの必要なサンプル数は以下の表の通りです。
信頼度95%の精度を求める場合の母集団ごとの必要なサンプル数は以下の表の通りです。
信頼度95%と許容誤差5%を前提とした場合、約385人が必要サンプル数として計算されています。
ただし、これは母集団の大きさによって変動し、母集団が大きいほど必要サンプル数も多くなりますが、
母集団が1万人以上になると、必要サンプル数にそこまで変化がないため、約400名から回答を得ることが一般的です。
適切なサンプル数を見積もるためには、信頼水準や許容誤差を考慮した計算ツールを使用することが推奨されます。
ただし、これは母集団の大きさによって変動し、母集団が大きいほど必要サンプル数も多くなりますが、
母集団が1万人以上になると、必要サンプル数にそこまで変化がないため、約400名から回答を得ることが一般的です。
適切なサンプル数を見積もるためには、信頼水準や許容誤差を考慮した計算ツールを使用することが推奨されます。
-
400人に5問 2万円でアンケート!サーベロイドに登録してみる

回収サンプル数の決め方手順
今回は、標本誤差早見表を用いた回収サンプル数の決め方をご紹介します。
許容誤差を決める
まず、どの程度の誤差が出てもよいかを考えます。
先に説明した通り標本調査を行う場合は「母集団」から、一部を標本として無作為に取り出しアンケートを実施しこの結果から母集団を推定する為どうしても誤差が生じます。
こちらの誤差を「許容誤差」と呼び、許容誤差を何%以内にするかを決めます。
許容誤差5%の意味は、例えばアンケートで90%の人が「そう思う」と回答した場合
母集団は85%~95%(90%の誤差±5%)の人が「そう思う」と回答したという結果になります。
先に説明した通り標本調査を行う場合は「母集団」から、一部を標本として無作為に取り出しアンケートを実施しこの結果から母集団を推定する為どうしても誤差が生じます。
こちらの誤差を「許容誤差」と呼び、許容誤差を何%以内にするかを決めます。
許容誤差5%の意味は、例えばアンケートで90%の人が「そう思う」と回答した場合
母集団は85%~95%(90%の誤差±5%)の人が「そう思う」と回答したという結果になります。
信頼度を決める
次に「信頼度」を決めます。
信頼水準はそのサンプルがどの程度の確率で許容誤差内の結果となるか表します。
先程の例でいうと、どの程度の確率で許容誤差が5%以内となるかという事です。
信頼度95%の場合「100回アンケートを実施した場合、95回は許容誤差内の結果に収まる」ことを示しています。
一般的に「信頼度」95%で統計上は十分意味があると言われています。
信頼水準はそのサンプルがどの程度の確率で許容誤差内の結果となるか表します。
先程の例でいうと、どの程度の確率で許容誤差が5%以内となるかという事です。
信頼度95%の場合「100回アンケートを実施した場合、95回は許容誤差内の結果に収まる」ことを示しています。
一般的に「信頼度」95%で統計上は十分意味があると言われています。
回答比率を確認する
回答比率とは、支持率や保有率などの調査対象者の回答比率の事です。
例えば、事前調査にてある商品を持っていると回答した人が70%いた場合、回答比率は70%ととなります。
事前に回答比率の情報が分かっている場合はその比率を用いますが、事前に分からない場合は最も誤差が出るところの50%を用います。
例えば、事前調査にてある商品を持っていると回答した人が70%いた場合、回答比率は70%ととなります。
事前に回答比率の情報が分かっている場合はその比率を用いますが、事前に分からない場合は最も誤差が出るところの50%を用います。
必要回収サンプル数を確認する
こちらが信頼度95%の標本誤差早見表となります。
確認方法は、まず表側の該当する回答比率を確認し、次に表の値が標本誤差となりますので該当の値を確認します、最後に表頭を見ると該当の回収サンプル数(サンプルサイズ)が記載されていますので必要数が分かります。
以下が、それぞれの場合の必要な回収サンプル数となります。
回答比率50%、許容誤差5%の場合は400人の回収が必要。
回答比率50%、許容誤差10%の場合は100人の回収が必要。
確認方法は、まず表側の該当する回答比率を確認し、次に表の値が標本誤差となりますので該当の値を確認します、最後に表頭を見ると該当の回収サンプル数(サンプルサイズ)が記載されていますので必要数が分かります。
以下が、それぞれの場合の必要な回収サンプル数となります。
回答比率50%、許容誤差5%の場合は400人の回収が必要。
回答比率50%、許容誤差10%の場合は100人の回収が必要。

信頼できる最低限の回収サンプル数は?
必要な回収サンプル数には諸説があり、一般的によく言われている回収サンプル数を紹介します。
・50サンプル
50サンプルで十分だという意見があります。こちらは標本誤差が15%程となります。
市場について深く分析する必要はなく大まかに把握したい場合やスピード重視で結果を確認したい場合は十分な回収サンプル数と言われています。
・100サンプル
標本誤差を10%に抑えられる為、意味があるアンケートを実施したいのであれば最低100サンプルは必要と言われることが多いです。
また調査を行ううえで、費用との兼ね合いも発生するので、100サンプルを選ばれることが多くあります。
・400サンプル
標本誤差5%に抑えられるため、より詳細な結果を求められる場合は400サンプルの回収をお薦め致します。
統計学では、標本誤差が5%以下だと有意水準であると考えられているので、アンケート結果を経営に関わるような重要な判断に用いる場合などは最低400サンプルに対して調査を実施すると効果的と言われています。
・50サンプル
50サンプルで十分だという意見があります。こちらは標本誤差が15%程となります。
市場について深く分析する必要はなく大まかに把握したい場合やスピード重視で結果を確認したい場合は十分な回収サンプル数と言われています。
・100サンプル
標本誤差を10%に抑えられる為、意味があるアンケートを実施したいのであれば最低100サンプルは必要と言われることが多いです。
また調査を行ううえで、費用との兼ね合いも発生するので、100サンプルを選ばれることが多くあります。
・400サンプル
標本誤差5%に抑えられるため、より詳細な結果を求められる場合は400サンプルの回収をお薦め致します。
統計学では、標本誤差が5%以下だと有意水準であると考えられているので、アンケート結果を経営に関わるような重要な判断に用いる場合などは最低400サンプルに対して調査を実施すると効果的と言われています。
-
信頼できるサンプル数を確保しよう!サーベロイドのモニターについて確認する
実際に調査を実施する場合
「誤差」と「予算」はトレードオフの関係
必要な回収サンプル数がわかり、さあ実際にアンケートを実施しようとなった場合、予算の問題が発生するかと思います。
標本数(=回収人数)が大きい方が誤差は小さくなりますので、より正確な調査を行いたいのであればより多くの回答を集め誤差を小さくすることをお薦め致しますが、多くのアンケートツールや調査会社へ依頼をする場合、設問数と回収する人数で料金が設定される為、回収人数が多くなるほど費用も大きくなります。
その為、「誤差」と「予算」はトレードオフの関係となります。
標本数(=回収人数)が大きい方が誤差は小さくなりますので、より正確な調査を行いたいのであればより多くの回答を集め誤差を小さくすることをお薦め致しますが、多くのアンケートツールや調査会社へ依頼をする場合、設問数と回収する人数で料金が設定される為、回収人数が多くなるほど費用も大きくなります。
その為、「誤差」と「予算」はトレードオフの関係となります。
回収サンプル数の目安は「分析したいところ×100名」
現実的に予算と信憑性を両立する、ビジネス視点では「ちょうどよいところ」を決めたいという場合、「分析したいところ × 100人」が最終的に実施される企業様が多いという事もありお薦めさせて頂いております。
「分析したいところ × 100人」がどのような事かと言うと以下の様になります。
例①20代男性の調理率を調べたい。
→「20代男性」が分析したいところとなるので、アンケートの回収人数は100人。
例②20代男性と20代女性の調理率の差を知りたい。
→「20代男性」と「20代女性」が分析したいところとなるので、それぞれ100人ずつ集めてアンケートの回収人数は200人。
また、実際どの程度の誤差が出るのかと言うと以下の通りとなります。
回答比率:50%(最も誤差が出るところ)
回収人数100人:誤差±9.8(40.2-59.8%)
回収人数500人:誤差±4.4(45.6-54.4%)
回収人数1000人:誤差±3.1(46.9-53.1%)
※信頼度95%
「分析したいところ × 100人」がどのような事かと言うと以下の様になります。
例①20代男性の調理率を調べたい。
→「20代男性」が分析したいところとなるので、アンケートの回収人数は100人。
例②20代男性と20代女性の調理率の差を知りたい。
→「20代男性」と「20代女性」が分析したいところとなるので、それぞれ100人ずつ集めてアンケートの回収人数は200人。
また、実際どの程度の誤差が出るのかと言うと以下の通りとなります。
回答比率:50%(最も誤差が出るところ)
回収人数100人:誤差±9.8(40.2-59.8%)
回収人数500人:誤差±4.4(45.6-54.4%)
回収人数1000人:誤差±3.1(46.9-53.1%)
※信頼度95%
-
200人に5問で1万円アンケート!サーベロイドに登録してみる
アンケート調査で回収可能な回収サンプル数を確認する方法とは?
アンケート調査で回収可能な回収サンプル数を確認する方法は、アンケート調査を繰り返し行い自社でノウハウを蓄積することで把握することもできますが、自社に人や仕組みのリソースがない場合には調査会社に依頼することをおすすめします。調査会社はサンプル数を回収するノウハウや仕組みを構築しているため、回収したい旨を伝えておけば後でまとめてくれるため確認できます。
調査会社にアンケート調査を外注するメリットについては、下記記事もご覧ください。
アンケート調査を外注するメリットとは?調査会社への依頼とセルフの選び方も解説!
調査会社にアンケート調査を外注するメリットについては、下記記事もご覧ください。
アンケート調査を外注するメリットとは?調査会社への依頼とセルフの選び方も解説!
セルフ型アンケートツールで調査を実施する
セルフ型アンケートツールで調査を実施することで、対象者を自力で集めるコストを限りなく減らすことが出来ます。また、調査会社にかかる費用を削減しながら、早く安価に調査結果を手に入れることが可能です。
セルフ型アンケートツールのメリットや比較については、下記記事もご覧ください。
セルフ型アンケートツールの徹底比較【料金、操作感、サポート】
セルフ型アンケートツールのメリットや比較については、下記記事もご覧ください。
セルフ型アンケートツールの徹底比較【料金、操作感、サポート】
-
ターゲットの回収予測数が事前確認できる!サーベロイドに登録してみる
まとめ
「サンプル数」と「サンプルサイズ」の違いから、アンケート調査で信頼性の高い結果を得るために必要なサンプル数の考え方を解説しました。
適切なサンプルサイズを決めるためには、誤差許容範囲や信頼度、回答比率を考慮する必要があります。
一般的に、信頼度95%の調査では、許容誤差5%で400サンプルが推奨されます。実際の調査では、予算と誤差のバランスを取りながら、必要なサンプル数を確保することが重要です。
適切なサンプルサイズを決めるためには、誤差許容範囲や信頼度、回答比率を考慮する必要があります。
一般的に、信頼度95%の調査では、許容誤差5%で400サンプルが推奨されます。実際の調査では、予算と誤差のバランスを取りながら、必要なサンプル数を確保することが重要です。
43 件
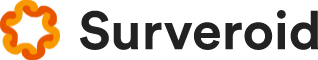 サーベロイドでリサーチをはじめませんか?
サーベロイドでリサーチをはじめませんか?




