目次
アンケートを外注したいけれど、どの方法がベストか悩んでいませんか?本記事では、企業がアンケートを外注する際に信頼性が高い「調査会社外注」について、そのメリット・デメリット、料金相場、依頼手順を詳しく解説します。コストを抑えつつ高品質なデータを得たい方や、信頼できる調査会社を見つけたい方はぜひ参考にしてください。

アンケート外注の方法は調査会社がベストな理由
企業がアンケートを外注する際、最も信頼性が高く、品質を確保できる方法は「調査会社に依頼すること」です。調査会社は専門知識を持つリサーチャーが対応し、調査設計からデータ収集、分析まで一貫したサポートを提供します。これにより、正確で信頼性の高いデータを得ることが可能です。
調査設計・実施・集計をプロのリサーチャーに任せられる
調査会社に依頼する最大のメリットは、プロフェッショナルであるリサーチャーが調査を担当する点です。リサーチャーは調査目的に応じた最適な質問設計を行い、回答者の選定も適切に管理します。これにより、無効回答や偏りのあるデータを排除し、正確な結果を得ることができます。調査後のデータ集計や分析も、因子分析やクロス集計といった専門的な手法で実施され、視覚的にわかりやすいレポートとして提供されます。企業はこのレポートをもとに、信頼性のある意思決定が可能です。
安全なデータ管理と契約での保証
調査会社に外注することで、データの安全性も確保されます。契約書にはデータの所有権や利用権が明記され、収集したデータは契約に基づいて適切に管理されます。これにより、企業はデータ漏洩や不正利用のリスクを最小限に抑えられます。また、個人情報保護法に準拠した取り扱いが徹底され、回答者のプライバシーも保護されます。調査終了後もデータは適切に処理され、再利用や不正利用は防止されます。企業は安心して調査結果を活用できます。

アンケート外注のメリット
調査会社に外注すれば、 調査目的の明確化、適切な設計、信頼性の高いデータ、専門的な分析 を一度に確保できるというメリットがあります。特に調査企画段階での設計が調査の成功を左右するため、プロによる設計は非常に重要です。
調査背景から設計まで一貫してサポート
調査会社にアンケートを外注する最大のメリットは、 調査背景や目的を整理し、リサーチ課題に落とし込み、適切な設計を行ってくれること です。企業が漠然とした調査目的を持っている場合でも、調査会社はプロのリサーチャーがその目的を明確化し、具体的な質問や調査手法に落とし込みます。これは「調査企画段階で調査の成否の8割が決まる」と言われるほど重要なプロセスです。
信頼性の高いデータが得られる設問設計
たとえば、消費者アンケートを実施する場合、購買行動やブランド認知度を正確に測るには、質問の順序や選択肢の設計が重要になります。調査会社は、調査目的に応じた最適な質問構成やフィルタリング設計を提案し、無効回答やバイアスを最小限に抑える工夫を行います。これにより、信頼性と再現性の高いデータを効率よく収集することができます。
ターゲット層へのアクセスが容易
調査会社は豊富なパネル(回答者データベース)を保有しており、企業が指定するターゲット層に精度高くアクセスできます。たとえば、「20代女性」「都内在住」「購入経験あり」といった条件に合致した回答者を短期間で確保することが可能です。これにより、より自社商品やサービスに近い属性の消費者の声を集めやすくなります。
高度な分析と活用しやすいレポート
収集したデータは、調査設計を担当したリサーチャーが分析を行います。クロス集計、因子分析、回帰分析などの高度な統計手法を用いて、調査目的に沿った結果を導き出します。結果はグラフや図表を交えて視覚的に整理され、企業はそのレポートをもとにマーケティング戦略や商品改善に具体的に活用することができます。
アンケート外注のデメリット
調査会社に外注する際には「コスト」「納期」「カスタマイズ対応」「コミュニケーション」などの面で負担が生じることがあります。しかし、これらを事前に理解し、適切に計画・調整することで、調査会社の専門性を最大限に活かすことができます。特に精度の高いデータが求められる場面では、十分に価値のある投資と言えるでしょう。
コストがかかる
調査会社にアンケートを外注する際の大きなデメリットの一つは、費用負担が大きいことです。調査設計、回答者募集、データ収集、分析、レポート作成といった各工程で費用が発生し、すべてをフルサポートで依頼すると、トータルで高額になることもあります。特に、カスタマイズや専門的な分析が必要な調査では、想定以上のコストになるケースもあります。
納期がかかる
プロによる設計と分析を含むため、調査全体のスケジュールには一定の時間が必要です。一般的には、調査設計から結果の納品までに1〜4週間を要します。調査の内容が複雑だったり、確認・修正のやり取りが多く発生する場合は、それ以上かかることもあります。短期間で結果を求めたい場合は注意が必要です。
コミュニケーションコストがかかる
調査会社は調査のプロですが、対象となる業界や商材について最も詳しいのは発注元である企業側です。そのため、調査目的や背景、意図を正確に伝えるためのコミュニケーションが不可欠です。企業側が目的を曖昧なまま依頼すると、期待したような調査結果が得られないこともあります。設計前の情報共有や、実施中の確認対応など、一定の時間と労力が必要となります。

調査会社に外注する場合の費用
調査設計費
調査設計費とは、アンケート調査を効果的に実施するための「質問設計」「構造設計」「ロジック設定」を行うための費用です。調査の成功は設計段階で決まると言われるほど重要で、この段階での設計が正確であればあるほど、信頼性の高いデータを得ることができます。調査会社の専門リサーチャーが、企業の調査目的を明確にし、その目的に基づいて最適な調査票を作成します。
簡易設計(5問以内):¥30,000〜¥50,000
・シンプルな質問設計(例:満足度調査、簡易な認知度調査)
・定型質問を組み合わせた構成。
標準設計(10〜20問):¥50,000〜¥100,000
・調査目的に応じたカスタマイズ設計(例:商品比較調査、購買意向調査)
・質問の順序やロジック(スキップロジック、条件分岐)を設定。
簡易設計(5問以内):¥30,000〜¥50,000
・シンプルな質問設計(例:満足度調査、簡易な認知度調査)
・定型質問を組み合わせた構成。
標準設計(10〜20問):¥50,000〜¥100,000
・調査目的に応じたカスタマイズ設計(例:商品比較調査、購買意向調査)
・質問の順序やロジック(スキップロジック、条件分岐)を設定。
実査(スクリーニング調査と本調査)費
実査費とは、アンケート調査における「スクリーニング調査」と「本調査」の回答を集めるためにかかる費用を指します。スクリーニング調査は特定の条件に合致する回答者を選別し、本調査はその条件を満たした回答者に詳細な質問を行う調査です。実査費はこの2つの調査に分かれており、費用体系も各調査会社で様々ですが、目安としては以下です。
スクリーニング調査の費用相場
費用相場:1回答あたり5円〜20円
例:10,000サンプル回収 → 約¥100,000
出現率やターゲットの絞り込み度合いによって必要な回答数が決まります。
本調査の費用相場
費用相場:1回答あたり100円~500円
例:500サンプル × ¥300/回答 → ¥150,000
例:1,000サンプル × ¥200/回答 → ¥200,000
専門性が高いターゲットや詳細な質問が多い場合、費用は上昇します。
スクリーニング調査の費用相場
費用相場:1回答あたり5円〜20円
例:10,000サンプル回収 → 約¥100,000
出現率やターゲットの絞り込み度合いによって必要な回答数が決まります。
本調査の費用相場
費用相場:1回答あたり100円~500円
例:500サンプル × ¥300/回答 → ¥150,000
例:1,000サンプル × ¥200/回答 → ¥200,000
専門性が高いターゲットや詳細な質問が多い場合、費用は上昇します。
データ集計費
データ集計費とは、アンケートで収集した回答データを集計・分析し、結果をわかりやすい形にまとめるための費用です。調査会社では、収集した回答を単純集計するだけでなく、クロス集計やグラフ化、表形式での整理、さらには因子分析や回帰分析などの高度な分析を行うこともあります。これらはすべて企業の調査目的に合わせて実施され、集計方法や分析手法によって費用が変動します。
単純集計:¥30,000〜¥50,000
回答データを設問ごとに集計し、各選択肢の回答数や割合を示す基本的な集計方法です。
クロス集計:¥50,000〜¥100,000
年齢、性別、地域などの属性ごとに回答を比較し、傾向を把握できます。「分析軸1つにつき〇万円」といった費用体系を採用していることが多く、複数軸の分析はその分費用が増加します。
高度な分析(因子分析、回帰分析):¥100,000〜¥300,000
消費者の行動要因や購買意向の要因を明らかにする専門的な分析。例えば、「購買意向に影響を与える要因は何か?」「ブランド認知度と購買意向の関係は?」といったテーマを解析できます。
単純集計:¥30,000〜¥50,000
回答データを設問ごとに集計し、各選択肢の回答数や割合を示す基本的な集計方法です。
クロス集計:¥50,000〜¥100,000
年齢、性別、地域などの属性ごとに回答を比較し、傾向を把握できます。「分析軸1つにつき〇万円」といった費用体系を採用していることが多く、複数軸の分析はその分費用が増加します。
高度な分析(因子分析、回帰分析):¥100,000〜¥300,000
消費者の行動要因や購買意向の要因を明らかにする専門的な分析。例えば、「購買意向に影響を与える要因は何か?」「ブランド認知度と購買意向の関係は?」といったテーマを解析できます。
レポート作成費
レポート作成費とは、アンケート調査で収集したデータを集計・分析し、その結果をわかりやすい報告書としてまとめるための費用です。このレポートは企業の意思決定に直結し、調査結果を効果的に活用するための重要なツールです。企業が調査結果を正確に理解し、次のアクションにつなげるために欠かせません。
調査会社では、レポート作成費は 設問数や分析内容に応じて変動 することが一般的です。また、クロス集計結果以外の高度な分析を追加する場合は、別途料金が発生します。
例:15問以内→10~15万円
例:25問以内→15~20万円
調査会社では、レポート作成費は 設問数や分析内容に応じて変動 することが一般的です。また、クロス集計結果以外の高度な分析を追加する場合は、別途料金が発生します。
例:15問以内→10~15万円
例:25問以内→15~20万円

調査会社に依頼する場合の流れ
企業がアンケート調査を実施する際、調査会社に外注することで専門的なサポートを受けられますが、依頼から調査結果の受け取りまでには明確なステップがあります。以下は、調査会社に依頼する一般的な流れです。
調査目的の明確化
まず最初に、企業は 調査の目的を明確化 する必要があります。たとえば、「新商品に対する消費者の反応を知りたい」「既存顧客の満足度を測りたい」など、調査結果をどのように活用するかを明確にし、調査目的を言語化します。この目的が不明確だと、質問設計や回答者の選定が適切に行えず、結果も期待通りにならないことがあります。
信頼できる調査会社の選定
次に、企業は 信頼できる調査会社を選定 します。調査会社ごとに対応可能な調査手法や回答者パネルの規模、料金体系が異なるため、自社の調査目的に合った調査会社を選ぶことが重要です。実績や口コミ、サービス内容を確認し、複数社から見積もりを取ることで、比較検討が可能です。
日本では「一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会(JMRA)」という業界団体があり、リサーチ業務の品質や倫理を保つためのガイドラインを整備しています。加盟企業は、個人情報保護や調査手法に関して一定の基準を満たしていることが多く、調査会社を選ぶ際の判断材料の一つとして参考になります。
日本では「一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会(JMRA)」という業界団体があり、リサーチ業務の品質や倫理を保つためのガイドラインを整備しています。加盟企業は、個人情報保護や調査手法に関して一定の基準を満たしていることが多く、調査会社を選ぶ際の判断材料の一つとして参考になります。
見積もり・契約の確認
調査会社が決まったら、 見積もりを確認し、契約を締結 します。見積もりには以下の費用が含まれることが一般的です。
・調査設計費(質問設計、ロジック設定)
・実査費(スクリーニング調査、本調査の回答収集費)
・データ集計費(クロス集計、単純集計、分析費)
・レポート作成費(結果の視覚化、インサイト提示)
企業は見積もりの各費用項目を確認し、必要に応じて調整を依頼します。また、契約書にはデータ所有権、納期、機密保持などが明記されます。
・調査設計費(質問設計、ロジック設定)
・実査費(スクリーニング調査、本調査の回答収集費)
・データ集計費(クロス集計、単純集計、分析費)
・レポート作成費(結果の視覚化、インサイト提示)
企業は見積もりの各費用項目を確認し、必要に応じて調整を依頼します。また、契約書にはデータ所有権、納期、機密保持などが明記されます。
調査設計と質問作成
契約後、調査会社は 調査設計と質問作成 を進めます。企業の調査目的に基づき、以下の要素が設計されます。
・調査対象者の条件設定(年齢、性別、地域、職業など)
・質問の構成と順序(単一回答、複数回答、マトリクス設問)
・ロジック設定(スキップロジック、条件分岐)
企業は質問案を確認し、修正や追加の希望があればフィードバックを行います。
・調査対象者の条件設定(年齢、性別、地域、職業など)
・質問の構成と順序(単一回答、複数回答、マトリクス設問)
・ロジック設定(スキップロジック、条件分岐)
企業は質問案を確認し、修正や追加の希望があればフィードバックを行います。
調査実施・データ収集
調査設計が確定すると、調査会社は アンケートを実施し、データ収集を行います。スクリーニング調査(対象者を絞り込む調査)を実施し、その後本調査に進みます。調査会社は回答者パネルを通じて指定のサンプル数を確保し、データの品質を管理します。
結果の集計とレポート作成
最後に、調査会社は収集したデータを集計・分析 し、レポートを作成します。
・単純集計:設問ごとの回答数や割合を集計。
・クロス集計:属性(年齢、性別)ごとの回答傾向を比較。
・高度な分析(因子分析、回帰分析):調査目的に応じた専門的な分析。
レポートはグラフや表を用いて視覚化され、企業が理解しやすい形で提供されます。報告書には、調査結果に基づくインサイトや提言が記載され、企業はこれをもとにマーケティング戦略やサービス改善を検討できます。
・単純集計:設問ごとの回答数や割合を集計。
・クロス集計:属性(年齢、性別)ごとの回答傾向を比較。
・高度な分析(因子分析、回帰分析):調査目的に応じた専門的な分析。
レポートはグラフや表を用いて視覚化され、企業が理解しやすい形で提供されます。報告書には、調査結果に基づくインサイトや提言が記載され、企業はこれをもとにマーケティング戦略やサービス改善を検討できます。
調査会社外注が難しい場合はセルフ型ツールも検討
企業がアンケート調査を実施したいものの、調査会社に依頼するコストや納期、柔軟性に課題を感じる場合は、 セルフ型ツールを検討することも一つの選択肢です。セルフ型ツールは、自社でアンケートを設計し、回答を収集・分析できるプラットフォームで、低コストかつ迅速に調査を実施できます。
コストを抑えたい場合
セルフ型ツールは調査会社に依頼する場合と比べ、圧倒的にコストを抑えられます。調査設計、回答収集、データ集計を自社で行うため、設計費やレポート作成費が不要です。たとえば、1,000サンプルの調査をセルフ型ツールで実施する場合、実査費は回答者インセンティブのみで済みます。
例:100人回収/10問の場合
セルフ型ツールで実施 →10,000円
調査会社外注 → 100,000円
例:100人回収/10問の場合
セルフ型ツールで実施 →10,000円
調査会社外注 → 100,000円
短期間で結果が欲しい場合
セルフ型ツールは、自社で調査を設計し、即座に配信できるため、納期を大幅に短縮できます。調査会社を介した場合、設計からレポート納品まで数週間かかることがありますが、セルフ型ツールなら即日開始、数日で結果を確認できます。
例:明日の会議・提案資料に載せるエビデンスデータの収集
例:商品企画の方向性があっているか、ちょっと消費者の声を聞いてみたいときに収集
例:新商品のフィードバックを1週間以内に収集
例:明日の会議・提案資料に載せるエビデンスデータの収集
例:商品企画の方向性があっているか、ちょっと消費者の声を聞いてみたいときに収集
例:新商品のフィードバックを1週間以内に収集
自社で柔軟に設計・運用したい場合
セルフ型ツールは、企業が自社で調査を設計し、運用できるため柔軟性があります。調査会社に依頼する場合とは異なり、質問内容や設計を自由に変更できるため、目的に応じた最適な調査をスピーディに実施可能です。
たとえば、以下のような調査設計が自社で可能です。
質問形式の多様性:単一回答、複数回答、マトリクス設問、スライダー設問など、ツールの機能に応じた様々な形式を使用できます。
回答ロジック設定:回答内容に応じたスキップロジックや条件分岐も、自社で設定可能です。
リアルタイム集計:回答が集まるごとに自動で集計し、視覚化された結果を即座に確認できます。
たとえば、以下のような調査設計が自社で可能です。
質問形式の多様性:単一回答、複数回答、マトリクス設問、スライダー設問など、ツールの機能に応じた様々な形式を使用できます。
回答ロジック設定:回答内容に応じたスキップロジックや条件分岐も、自社で設定可能です。
リアルタイム集計:回答が集まるごとに自動で集計し、視覚化された結果を即座に確認できます。
まとめ
アンケートを外注する際は、調査会社に依頼することで、調査設計から実施・分析までを一貫して任せることができ、高度な分析や専門的なレポートが必要な調査に適しています。特に、調査目的が明確で、専門性が求められる内容であれば、プロのリサーチャーによる設計・運用が大きな価値を発揮します。
一方で、セルフ型アンケートツールでも、適切な設計と運用がなされていれば、十分に信頼性の高いデータを得ることが可能です。調査目的を自社で明確にし、設問設計や対象者の条件設定を丁寧に行うことで、専門的な外注に劣らない実用的な調査結果を導くことができます。また、セルフ型はコスト面・スピード・設計の自由度の面でも優れており、社内で調査経験がある企業にとっては非常に有効な選択肢です。
重要なのは、「誰に、何を、どのように聞くのか」という調査の基本を正しく押さえることです。調査の目的や社内リソースに応じて、調査会社への外注とセルフ型ツールの使い分けを柔軟に行うことが、良質なデータと納得感のある意思決定につながります。
一方で、セルフ型アンケートツールでも、適切な設計と運用がなされていれば、十分に信頼性の高いデータを得ることが可能です。調査目的を自社で明確にし、設問設計や対象者の条件設定を丁寧に行うことで、専門的な外注に劣らない実用的な調査結果を導くことができます。また、セルフ型はコスト面・スピード・設計の自由度の面でも優れており、社内で調査経験がある企業にとっては非常に有効な選択肢です。
重要なのは、「誰に、何を、どのように聞くのか」という調査の基本を正しく押さえることです。調査の目的や社内リソースに応じて、調査会社への外注とセルフ型ツールの使い分けを柔軟に行うことが、良質なデータと納得感のある意思決定につながります。
64 件

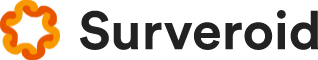 サーベロイドでリサーチをはじめませんか?
サーベロイドでリサーチをはじめませんか?




