目次

食品アンケートの意義と活用メリット
食品業界では、顧客の声を的確に拾い上げることが顧客満足・売上向上につながる鍵です。特に食の好みは個人差が大きく、時代やトレンドの影響を受けやすい分野であるため、商品がいくら開発担当者の自信作でも、実際に口にする人たちの率直な声を把握しなければ、せっかくのアイデアがマーケットに受け入れられない可能性が高まります。また、消費者の意識として食品への安全性や健康への影響なども重視されるようになり、購買に至るまで様々な要素で検討されるようになりました。そこで役立つのが、顧客のリアルな意見を定量的かつ定性的に得られるアンケート調査です。数字やデータをベースに商品の魅力や改善点を浮き彫りにすることで、開発・販売戦略の精度を高められるのが最大のメリットだといえます。
食品市場における顧客の声の重要性
日本国内だけを見ても、食に対するニーズや嗜好は地域性や世代によって千差万別です。例えば東京で評価が高かった新商品が、地方ではまったく響かないということも珍しくありません。そうした食の多様性を可視化するには、実際の消費者が何を求め、何に満足し、どこに不満を感じているのかを正確に把握する必要があります。たとえば味つけの濃さをどう感じているか、パッケージの印象がどうなのか、あるいは価格帯が適切だと感じるかどうかなど、どれだけ事前に現場の声を反映できるかが商品成功の鍵を握ります。多様化する社会において、消費者の行動やその行動に至った背景などを理解することは不可欠となっており、これこそまさにアンケートで補うべきポイントといえるでしょう。
アンケート結果を活かした事例紹介
実際にアンケートを活用して成功した企業の例を挙げると、新商品発売前の段階で味わいやパッケージデザインを細かく調査し、消費者が「もう少し甘さを控えめにしてほしい」と意見した結果を踏まえてレシピを微調整したケースがあります。この商品は発売後、競合と差別化された独自の甘味バランスが評価されてヒットにつながりました。さらには、既存商品のリニューアルに際し「量はちょうど良いがパッケージが手に取りづらい」という声をもとに容器の形状を変更し、売上が大幅に回復した例も見受けられます。こうした成功事例はすべてアンケートで抽出したデータを基に仮説を立て、検証を重ねるプロセスがあったからこそ生まれたものです。食品市場では一度マイナス評価がつくとイメージ回復に時間がかかるだけに、アンケート結果を初期段階で活かす意義は非常に大きいといえるでしょう。
セルフ型アンケートツール「Surveroid」を使った食品業界の事例
エバラ食品工業株式会社様_商品企画においてアンケートで受容性を確認
セルフ型アンケートツール「Surveroid」を使った食品業界の事例
エバラ食品工業株式会社様_商品企画においてアンケートで受容性を確認
食品アンケートのアンケート例・テンプレート
ここでは実際に食品業界におけるアンケート例・テンプレートを紹介します。
コンセプト調査を行いたい場合のテンプレート

パッケージ調査を行いたい場合のテンプレート

-
汎用的な調査テンプレ(Excel)はこちらテンプレートをダウンロードする

食品アンケートの設計ステップと必須項目
効果的なアンケートを作り上げるには、どの段階でどのような設問を入れるかといった設計の手順をしっかり押さえる必要があります。漠然と「顧客の声を聞くためにアンケートをとる」という発想だけでは、回収したデータをどのように分析すればよいか分からず、結局は社内で活用しきれないという残念な結果になりがちです。そこで最初にやるべきことは、アンケートの目的を明確に定義し、ネクストアクションが取れる状態に設計しておくことです。想定するターゲットの属性や聴取項目、調査手段、回答目標数の設定をおこないます。
設計ステップの全体像
食品アンケートの設計は、目的設定、ターゲット選定、設問作成、配信方法の決定、回収と分析という流れで進みます。新商品の開発が目的なのか、既存商品の改善が目的なのかによって、設問の内容やターゲットが異なることを常に意識しましょう。目的がはっきりしていないと、質問内容が偏ったり、自購入者へ質問すべき内容を(食べているが)非購入者に質問をしたりすると、重要な情報を収集しそこねるリスクが高まります。想定回答数が少なすぎてもデータに偏りが生じやすくなるため、ある程度のサンプルサイズを確保できるよう配信計画を立てることが大切です。
▼関連記事
アンケートの作り方とは?コツや流れをテンプレート10個とともに紹介!
アンケートの回収サンプル数の決め方について信頼できるデータ数は?
分析の段階では、社内プレゼンの場を想定しながらグラフや表を使って分かりやすく整理し、経営陣や開発チームに見せられる形に仕上げると、アンケート結果がよりスピーディーに意思決定につながります。
▼関連記事
アンケート調査結果の6つのまとめ方 流れや作成のポイントも紹介
▼関連記事
アンケートの作り方とは?コツや流れをテンプレート10個とともに紹介!
アンケートの回収サンプル数の決め方について信頼できるデータ数は?
分析の段階では、社内プレゼンの場を想定しながらグラフや表を使って分かりやすく整理し、経営陣や開発チームに見せられる形に仕上げると、アンケート結果がよりスピーディーに意思決定につながります。
▼関連記事
アンケート調査結果の6つのまとめ方 流れや作成のポイントも紹介
設問の種類と使い分け
食品アンケートでは、目的に応じて単一回答や複数回答、自由記述形式などを組み合わせるのが一般的です。
例えば、購入意向については、「購入したい、購入したくない」といった単純な二択だと回答者の曖昧な感覚がうまく拾えないため、5段階で回答できるようにするなど、回答しやすいように工夫することが必要になります。また、5段階の購入意向は、TOP2計が●%以上あれば開発に進めるなどの意思決定に使用している企業もいます。
一方でパッケージや見た目に関する評価は、写真を提示して自由記述で感想を求めるといった方法も有効的です。定量的データのほうが分析しやすい場合もありますが、自由記述欄で得られる「このデザインだと手に取りにくい」「色が好みではない」などの生の声は、改善策を考える際にとても役立ちます。
例えば、購入意向については、「購入したい、購入したくない」といった単純な二択だと回答者の曖昧な感覚がうまく拾えないため、5段階で回答できるようにするなど、回答しやすいように工夫することが必要になります。また、5段階の購入意向は、TOP2計が●%以上あれば開発に進めるなどの意思決定に使用している企業もいます。
一方でパッケージや見た目に関する評価は、写真を提示して自由記述で感想を求めるといった方法も有効的です。定量的データのほうが分析しやすい場合もありますが、自由記述欄で得られる「このデザインだと手に取りにくい」「色が好みではない」などの生の声は、改善策を考える際にとても役立ちます。
設問例:味・見た目・価格・喫食シーン・購入状況
たとえば、味に関する質問では甘さや辛さ、後味の好みまで踏み込むことで、単なる「おいしい」「まずい」の評価だけでは見えてこない細やかなニーズをとらえられます。
見た目については、パッケージデザインや盛り付け写真を提示し、第一印象や手に取る際の感覚を率直に尋ねることで、売り場での購買行動をイメージしやすくなります。
価格設定については、購入を検討する際に「いくらまでなら購入を検討するか」「この商品にいくらまで払えるか」など、具体的な価格レンジを選択肢で尋ねると、商品設計に直結するデータが得られます。
さらに健康志向が高まる市場トレンドを踏まえ、原材料や栄養成分に対する関心の度合い、アレルギー表示の分かりやすさなどの重視点を聞いておくと、今後の改良点や新たなマーケティング戦略のヒントに結びつく可能性があります。
また、喫食シーンや購入状況などから、その商品がどのような価値を持っているのか、競合との差別化ポイントを見出したり、施策の優先度付けをしたりするなど、マーケティング視点でヒントを得ることができるでしょう。
見た目については、パッケージデザインや盛り付け写真を提示し、第一印象や手に取る際の感覚を率直に尋ねることで、売り場での購買行動をイメージしやすくなります。
価格設定については、購入を検討する際に「いくらまでなら購入を検討するか」「この商品にいくらまで払えるか」など、具体的な価格レンジを選択肢で尋ねると、商品設計に直結するデータが得られます。
さらに健康志向が高まる市場トレンドを踏まえ、原材料や栄養成分に対する関心の度合い、アレルギー表示の分かりやすさなどの重視点を聞いておくと、今後の改良点や新たなマーケティング戦略のヒントに結びつく可能性があります。
また、喫食シーンや購入状況などから、その商品がどのような価値を持っているのか、競合との差別化ポイントを見出したり、施策の優先度付けをしたりするなど、マーケティング視点でヒントを得ることができるでしょう。

回答率を高めるためのテクニック
アンケートの質を高めるためには、できるだけ多くの回答者から生の声を集めることが欠かせません。ところが実際には、回収率が伸びずに分析に足るデータが集まらないケースもしばしば見受けられます。そうした事態を防ぐには、回答者の負担を軽減する設問数の工夫や、アンケートに協力するメリットを感じてもらう仕掛けが必要です。
設問数と回答時間の最適化
調査の目的を絞り込んだうえで、なるべく短時間で回答できる構成を心がけることがまず大切です。質問が多すぎると回答者は途中で疲れて離脱しやすくなり、結果的に有効回答数が減ってしまいます。食品に関するアンケートでも、つい欲張って味やデザイン、価格、購入意向など多岐にわたる質問を詰め込みたくなるものですが、次のアクションにつなげることができるのか?と立ち止まって考え、厳選した設問を作ることが重要です。設問数を減らすのが難しい場合には、回答画面に進捗状況を表示したり、選択肢を見やすく配置したりして回答のストレスを和らげる工夫をすると、最後まで回答してもらえる可能性が高まります。
インセンティブや魅力的な特典
食品企業ならではのアイデアとしては、試作品の無料サンプルをプレゼントすることや、新商品発売時に使える割引クーポンを配布するといった仕組みが挙げられます。実際に商品を体験してもらったうえで回答してもらえると、回答内容がより具体的になりやすくなり、企業側にとっても信頼度の高いデータを得ることができます。さらに小規模な調査では、抽選でギフト券やポイントを付与するなど、回答者がワクワクするインセンティブを用意している企業もあります。あくまでもアンケートの主目的は顧客の本音を集めることですので、高価すぎる特典を用意して「目当ては特典のみ」という回答者を増やさないよう、バランス感覚を保つことも大切です。

注意すべきポイントと失敗事例
アンケート調査は便利な反面、設問の作り方や配信の仕方を誤ると、得られるはずのデータを無駄にしてしまう可能性があります。実際の企業事例を振り返ってみると、曖昧な表現によって回答者を混乱させたり、そもそも意図したターゲットにアンケートが届かなかったりといった失敗談が少なくありません。こうした落とし穴を事前に知っておけば、同じミスを繰り返さずに済むはずです。
設問の曖昧さやバイアスのリスク
食品アンケートでありがちな失敗の一つに、主観的な表現が多く含まれたり、回答者にとって意味が分かりづらい単語を使いすぎるケースが挙げられます。たとえば「美味しいと思いましたか?」という聞き方だけだと、回答者によって「美味しい」の基準があまりにも異なるため、結果の解釈が難しくなりがちです。さらに「この商品は健康的ですよね?」のように、すでに商品を肯定する前提が込められた質問をしてしまうと、回答者の中には否定しづらいと感じる人が出てきます。こうしたバイアスが入り込むと、集計結果が本来の顧客心理を反映しにくくなるので、なるべく客観的かつ具体的な表現を使うのが望ましいです。
分析ミスや結果の誤読
十分な数の回答が集まったとしても、データの見方を誤ってしまうと正しい結論にたどり着けません。例えば、特定の年代に偏った人だけが多く回答していた場合、全体の市場ニーズとは異なる結果になる可能性があります。こうした集計の偏りを防ぐためには、回答者の属性を把握しながらクロス集計などを行い、視点を広げてデータを読み解くことが必要です。また、ポジティブな意見だけに目を向けてネガティブな指摘を無視してしまうと、商品開発の改善ポイントを見逃してしまう恐れがあります。そうした危険を回避するには、初期段階でデータ分析のスキルやツールの活用法を学んでおくことが大切です。
個人情報保護・コンプライアンスへの配慮
食品アンケートでも、回答者の名前や連絡先、性別や年齢といった個人情報を収集することがしばしばあります。とくにサンプルを郵送する場合などは住所が必要になりますが、その際には個人情報保護法などの法律に基づいた取り扱いが欠かせません。プライバシーポリシーを明示し、利用目的をきちんと説明したうえで同意を得るプロセスを踏まないと、信頼を損ねるばかりか法的リスクを負う可能性もあります。最近ではオンラインでアンケートを配信する企業が増えているため、ツール選定の段階からセキュリティ面を確認し、収集したデータが安全に保管される環境を整えておくことが企業イメージの向上にもつながるでしょう。

食品アンケートで使えるツール比較
実際にアンケートを実施しようと考えたとき、どのツールを利用するのが最適かで悩む方も多いのではないでしょうか。とくに初めて担当する場合は、無料で使えるツールと有料の専門サービスとの違いや、操作性の容易さなどを比較検討してから導入を決めたいと思うのは自然なことです。そこで代表的な無料ツールの特徴を知っておくと、サービスの選択肢がぐっと絞りやすくなります。
代表的なアンケートツールの特徴
たとえばGoogleフォームは、手軽に始められて基本的なアンケート機能が充実しており、集計結果をスプレッドシートと連動して簡単に閲覧できる点が魅力です。
SurveyMonkeyは海外での利用実績が豊富で、多彩なアンケートテンプレートを提供していますが、日本語サポートや日本向けのテンプレートが限定的なケースがあるため、食品に関する具体的な質問例を自分でカスタマイズする必要がある場合もあります。
Surveroidでは600万名の回答モニターに向けてアンケート配信ができるツールです。商品開発前などに受容性を把握するために調査を行う企業は多いかと思いますが、セルフ型アンケートツールでコンセプトやパッケージなどの調査をスピード感を持ってアンケートを実施することが可能です。
自社顧客にアンケートを行う場合のように、アンケート作成のみ行う場合は無料で行えるツールもあります。
ただし、回答者へアンケート協力のお礼を行う場合は、謝礼を自社で用意しておく必要があります。
一方でSurveroidのように回答モニターに対して配信できるツールは謝礼込みの費用となっており、回答率を考慮してアンケート配信されるため、自社顧客に対してアンケートを実施する場合と比べてあまり回答率を気にしなくても問題ないです。
SurveyMonkeyは海外での利用実績が豊富で、多彩なアンケートテンプレートを提供していますが、日本語サポートや日本向けのテンプレートが限定的なケースがあるため、食品に関する具体的な質問例を自分でカスタマイズする必要がある場合もあります。
Surveroidでは600万名の回答モニターに向けてアンケート配信ができるツールです。商品開発前などに受容性を把握するために調査を行う企業は多いかと思いますが、セルフ型アンケートツールでコンセプトやパッケージなどの調査をスピード感を持ってアンケートを実施することが可能です。
自社顧客にアンケートを行う場合のように、アンケート作成のみ行う場合は無料で行えるツールもあります。
ただし、回答者へアンケート協力のお礼を行う場合は、謝礼を自社で用意しておく必要があります。
一方でSurveroidのように回答モニターに対して配信できるツールは謝礼込みの費用となっており、回答率を考慮してアンケート配信されるため、自社顧客に対してアンケートを実施する場合と比べてあまり回答率を気にしなくても問題ないです。
Surveroidを使ったアンケート作成と登録の流れ
実際にアンケートツールを活用してみようと考えたとき、多くの担当者が気にするのは「どのくらいのステップ数で作成できるのか」という手軽さではないでしょうか。Surveroidの場合は、会員登録からテンプレート選択、設問の微調整、配信まですべてオンラインで完結できるため、調査票が固まっていれば初心者でも、1営業日程度でアンケート画面作成~配信まで行うことができます。手軽に活用できるため多くの食品メーカ様が利用しています。
結果分析とレポート作成
アンケートを配信した後は、集まった回答を分析し、レポート化して社内や関係部署に共有します。
Surveroidに付随する集計ツール「for Analysis」は、無料でアンケート結果を集計することができます。集計ツールではGT集計、クロス集計など自由に集計をすることができるため、アンケートを行った後もExcelを使って複雑な集計作業を行うなどの必要はなくなります。アンケート結果をもとに素早い改善や新商品開発の方向性が固まれば、競合他社との違いを生み出す大きな一歩につながるでしょう。
Surveroidに付随する集計ツール「for Analysis」は、無料でアンケート結果を集計することができます。集計ツールではGT集計、クロス集計など自由に集計をすることができるため、アンケートを行った後もExcelを使って複雑な集計作業を行うなどの必要はなくなります。アンケート結果をもとに素早い改善や新商品開発の方向性が固まれば、競合他社との違いを生み出す大きな一歩につながるでしょう。
まとめ
Surveroidでは無料会員登録で実際の画面をご覧いただくことや回収予測数の確認ができます。
スピード感を持って顧客の声を知り、商品開発やマーケティング施策の実行につなげていきましょう。
スピード感を持って顧客の声を知り、商品開発やマーケティング施策の実行につなげていきましょう。
51 件
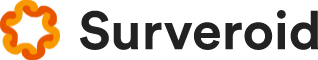 サーベロイドでリサーチをはじめませんか?
サーベロイドでリサーチをはじめませんか?




