目次
認知度調査とは、ブランドがどの程度市場に浸透しているかを確認する調査です。
市場のコモデティ化が進む中で、ブランド力が高いと競争力が高まり、顧客ロイヤルティの向上やLTV(顧客生涯価値)の最大化などにつながることから、安定した収益基盤の構築を期待できます。企業が成長するにはブランド力の強化が必須といえ、ブランド認知度調査により自社のブランドポジションを確認しながら対策を打つことは、重要なマーケティング戦略となるでしょう。
本記事では、認知度調査の活用法や重視される指標、実査の注意点、アンケート項目例などを解説します。
市場のコモデティ化が進む中で、ブランド力が高いと競争力が高まり、顧客ロイヤルティの向上やLTV(顧客生涯価値)の最大化などにつながることから、安定した収益基盤の構築を期待できます。企業が成長するにはブランド力の強化が必須といえ、ブランド認知度調査により自社のブランドポジションを確認しながら対策を打つことは、重要なマーケティング戦略となるでしょう。
本記事では、認知度調査の活用法や重視される指標、実査の注意点、アンケート項目例などを解説します。

認知度調査とは?
認知度調査とは、特定のブランドが世間や市場においてどのぐらい浸透しているかを調べる調査です。
よく似た言葉に「知名度」がありますが、違いとしては下記になります。
知名度:商品やサービスの名前を知っている
認知度:名前だけでなく、その強みや価値を理解している
今回の認知度調査では、特定のブランドがどれだけ中身まで理解されているかを調査していきます。
認知度がわかれば市場におけるポジションを把握できるほか、マーケティング活動の改善点を可視化できるため、ブランド価値の向上や競争力の強化など、効果的なブランディング戦略の実現が可能となります。
認知度調査はブランドがどれだけ知られているかを確認することが目的であるため、大量のデータを集められる定量調査を行うのが一般的です。また調査設計では、できるだけ回答者に偏りが出ないようにすることが、データの精度を高めるポイントとなります。
よく似た言葉に「知名度」がありますが、違いとしては下記になります。
知名度:商品やサービスの名前を知っている
認知度:名前だけでなく、その強みや価値を理解している
今回の認知度調査では、特定のブランドがどれだけ中身まで理解されているかを調査していきます。
認知度がわかれば市場におけるポジションを把握できるほか、マーケティング活動の改善点を可視化できるため、ブランド価値の向上や競争力の強化など、効果的なブランディング戦略の実現が可能となります。
認知度調査はブランドがどれだけ知られているかを確認することが目的であるため、大量のデータを集められる定量調査を行うのが一般的です。また調査設計では、できるだけ回答者に偏りが出ないようにすることが、データの精度を高めるポイントとなります。
認知度調査を活用するには?
ブランド認知度調査は、主にマーケティング戦略の策定やマーケティング施策の効果測定などに用いられます。以下で詳しく解説します。
マーケティング戦略の策定
ブランド認知度調査を行うことで、市場における占有率やポジションを把握できます。性、年代、職業といった属性別の認知分析や競合との比較などにより、自社ブランドの強み・弱みが明確になるでしょう。
またブランドの認知経路や購入意向など詳細なデータ収集することで、より精度の高いブランディング戦略やブランドリフトのためのマーケティング戦略策定に役立てられます。
マーケティング施策の効果確認
認知度調査によりマーケティング施策の効果を可視化できるため、次のアクションへと活かしやすくなります。たとえばキャンペーン前後で調査を行い、キャンペーン後に認知度が上がっていれば、成功要因を次期施策へ反映できるでしょう。仮に認知度が下がっても失敗要因を課題として認識できるため、迅速な対処が可能となります。
また定期的に認知度や効果をモニタリングすると、長期的なブランディング戦略に活用できます。
ブランド認知度調査を行うことで、市場における占有率やポジションを把握できます。性、年代、職業といった属性別の認知分析や競合との比較などにより、自社ブランドの強み・弱みが明確になるでしょう。
またブランドの認知経路や購入意向など詳細なデータ収集することで、より精度の高いブランディング戦略やブランドリフトのためのマーケティング戦略策定に役立てられます。
マーケティング施策の効果確認
認知度調査によりマーケティング施策の効果を可視化できるため、次のアクションへと活かしやすくなります。たとえばキャンペーン前後で調査を行い、キャンペーン後に認知度が上がっていれば、成功要因を次期施策へ反映できるでしょう。仮に認知度が下がっても失敗要因を課題として認識できるため、迅速な対処が可能となります。
また定期的に認知度や効果をモニタリングすると、長期的なブランディング戦略に活用できます。
認知度調査を実施するおすすめのタイミング
認知度調査は、新商品発売やリニューアル時、売上が伸び悩んでいる時、企業のブランディングなどのタイミングで行うと、効果を最大限活用できます。以下で詳しく解説します。
新商品ローンチ時やリブランディングのタイミング
認知度調査は新商品を発売する際やリニューアル時に行うと、市場での認知度や浸透具合、競合との比較によるポジションなどを把握できます。また課題も発見できるため、以降の効果的なマーケティング施策に活かすことが可能です。
商品の売上が伸びなくなった時
認知度調査は、自社商品やサービスの売上が頭打ちになっている場合や伸び悩んでいる時にも有効活用できます。
認知度調査では、消費者の購買プロセスを理解するマーケティングファネルである「Attention(認知)」→「Interest(興味)」→「Desire(欲求)」→「Memory(記憶)」→「Action(行動)」→購入後の「継続」→「好意・愛着」→「共有・紹介」→「発信」に沿って、どのプロセスがボトルネックになているかを把握できます。改善すべきポイントがわかれば、即効性のある対策を講じられるでしょう。
認知度調査では、消費者の購買プロセスを理解するマーケティングファネルである「Attention(認知)」→「Interest(興味)」→「Desire(欲求)」→「Memory(記憶)」→「Action(行動)」→購入後の「継続」→「好意・愛着」→「共有・紹介」→「発信」に沿って、どのプロセスがボトルネックになているかを把握できます。改善すべきポイントがわかれば、即効性のある対策を講じられるでしょう。
企業のブランディングやリブランディング時
認知度調査は、企業のブランディング、リブランディングを行う際にも適しています。
調査により自社の認知状況や好感度、イメージなどを把握できれば、最適なブランディング施策を構築できます。自社の認知度や好感度を高め、ロイヤルティの高い顧客やファンを増やせれば、継続的で安定した収益獲得を期待できるでしょう。
調査により自社の認知状況や好感度、イメージなどを把握できれば、最適なブランディング施策を構築できます。自社の認知度や好感度を高め、ロイヤルティの高い顧客やファンを増やせれば、継続的で安定した収益獲得を期待できるでしょう。
-
定量・定性データの取得が出来るサーベロイドのサービスを見る
認知度調査を実施するには?
認知度調査は、商品やサービス、ブランドが消費者にどの程度認知されているかを調べるため、定量調査で行うのが一般的です。インターネットリサーチや郵送調査、電話調査、会場調査などで行いますが、スピーディに回答を集められ低コストで実施できるインターネットリサーチが主流となっています。
また商品やブランドに対するイメージや使用感、購入に至った経緯など、心理的な要素を深堀りしたい場合は、インタビュー調査も併用するとよいでしょう。インタビュー調査により数量では把握できない深層心理を知れるほか、想定外の情報や消費者ニーズを発見できる可能性があります。単なる解答だけでなく、参加者の声の調子や表情、身振りなどの非言語的な情報も同時に観察できるのも特徴です。
また調査は自社で行うパターンと、調査会社に委託して実施する方法があります。それぞれの実査方法やメリットは以下の通りです。
また商品やブランドに対するイメージや使用感、購入に至った経緯など、心理的な要素を深堀りしたい場合は、インタビュー調査も併用するとよいでしょう。インタビュー調査により数量では把握できない深層心理を知れるほか、想定外の情報や消費者ニーズを発見できる可能性があります。単なる解答だけでなく、参加者の声の調子や表情、身振りなどの非言語的な情報も同時に観察できるのも特徴です。
また調査は自社で行うパターンと、調査会社に委託して実施する方法があります。それぞれの実査方法やメリットは以下の通りです。
自社で実施する
認知度調査は回答者を数多く集める必要があるため、自社で実施する場合はモニターを保有している調査会社の、セルフでインターネットリサーチを行えるサービス(セルフ型ネットリサーチ)を活用するとよいでしょう。
セルフ型ネットリサーチでは、実査は調査会社のサービスを利用するものの調査票の作成や集計・分析は自社で行うため、自社のニーズに適した情報を集めることができコストを抑えられるメリットがあります。また機密情報の流出を防ぎ、自社にノウハウが蓄積するのも魅力といえるでしょう。
認知度調査は回答者を数多く集める必要があるため、自社で実施する場合はモニターを保有している調査会社の、セルフでインターネットリサーチを行えるサービス(セルフ型ネットリサーチ)を活用するとよいでしょう。
セルフ型ネットリサーチでは、実査は調査会社のサービスを利用するものの調査票の作成や集計・分析は自社で行うため、自社のニーズに適した情報を集めることができコストを抑えられるメリットがあります。また機密情報の流出を防ぎ、自社にノウハウが蓄積するのも魅力といえるでしょう。
-
はじめての認知度調査にもおすすめ!資料をダウンロードする
-
今すぐ調査を始められます!サーベロイドに登録してみる
調査会社に委託する
自社に調査のノウハウやリソースが不足している場合は、調査会社に依頼する方法もあります。設問設計や集計・分析も全て任せられるため、手間をかけずにさまざまな調査を行えます。
また調査会社は専門的な知識やノウハウを有しているため、質の高いサービスを利用できます。自社が求める精度の高い情報やデータをスピーディに入手できるでしょう。
自社に調査のノウハウやリソースが不足している場合は、調査会社に依頼する方法もあります。設問設計や集計・分析も全て任せられるため、手間をかけずにさまざまな調査を行えます。
また調査会社は専門的な知識やノウハウを有しているため、質の高いサービスを利用できます。自社が求める精度の高い情報やデータをスピーディに入手できるでしょう。
認知度調査の調査対象者の設計のポイント
認知度調査では、その目的や用途によって調査対象者を正確に設計、調整する必要があります。
たとえば市場において自社商品やサービスがどの程度浸透しているかを知りたいなら、回答者に偏りが出ないように、対象となるエリアの人口構成比に合わせた調査対象者を抽出する必要があります。回答者の性年代の構成比を、市場の構成比に合うように回収できるように設計しなければなりません。
一方調査対象者を、自社商材の顧客に限定する場合もあります。たとえば化粧品のメーカーが自社の顧客それぞれのロイヤルティやLTVを調べたいのであれば、顧客のみが調査対象となります。
調査によって対象者が異なるため、自社で準備できない場合は調査会社のモニターを活用するなどを行って、正しい結果を得られるようにしましょう。
たとえば市場において自社商品やサービスがどの程度浸透しているかを知りたいなら、回答者に偏りが出ないように、対象となるエリアの人口構成比に合わせた調査対象者を抽出する必要があります。回答者の性年代の構成比を、市場の構成比に合うように回収できるように設計しなければなりません。
一方調査対象者を、自社商材の顧客に限定する場合もあります。たとえば化粧品のメーカーが自社の顧客それぞれのロイヤルティやLTVを調べたいのであれば、顧客のみが調査対象となります。
調査によって対象者が異なるため、自社で準備できない場合は調査会社のモニターを活用するなどを行って、正しい結果を得られるようにしましょう。
-
人口構成比回収やスクリーニングも可能!サーベロイドのサービスを見る

認知度調査で質問をする代表的な項目
認知度調査ではその目的や用途によって設問項目が変わりますが、「純粋想起率」「助成想起率」「認知・購買プロセス」「商品特徴の理解」「広告やプロモーションの接触状況」などが、よく用いられる項目です。詳しく解説しましょう。
純粋想起率
純粋想起率とは、回答者に選択肢やヒントを与えずに思いつくまま答えてもらった回答率で、「再生知名率」ともいいます。たとえば、「ノンアルコールビールといえば、どの銘柄を思い浮かべますか?」などが、純粋想起を導く設問となります。また純粋想起の中でも一番先に挙がった銘柄を、トップオブマインド(第一想起)といいます。
純粋想起率が高いということは記憶に深く定着していると考えられ、購買時の銘柄選択への影響度が大きいとされています。
純粋想起率が高いということは記憶に深く定着していると考えられ、購買時の銘柄選択への影響度が大きいとされています。
-
【例】
- 〇〇カテゴリーの商品について知っている商品名をお書きください。
※知っている商品がない場合は「なし」と入力してください。
助成想起率
助成想起率とは、いくつかの選択肢を提示するなどのヒントを与えた際の回答率のことで、「再認知名率」ともいいます。たとえば選択肢を提示しながら、「知っているノンアルコールビールの銘柄を全て選んでください。」と聞きます。
純粋想起率よりは購買時の影響度が低いとされているものの、日用品や消耗品など比較的消費者のこだわりが少なく気軽に選ぶ製品は、助成想起率が高い方が購買につながりやすいとされています。
純粋想起率よりは購買時の影響度が低いとされているものの、日用品や消耗品など比較的消費者のこだわりが少なく気軽に選ぶ製品は、助成想起率が高い方が購買につながりやすいとされています。
純粋想起と助成想起の違いとは?用語の意味から適切な使い分けまで解説

アンケートで認知度を聴取する際には純粋想起、助成想起の2種類があります。それぞれの想起はどう違うのか、またどのように使い分けるのが正解なのかを分かりやすく解説しています。
認知・購買プロセス
認知度調査では、消費者の購買プロセスであるマーケティングファネルに基づいて、どこで商品を知ったか、何がきっかけで購入したかといった認知・購入経路や、自社・競合商品の各プロセスにおける課題を把握するための設問もよく使われます。
-
【例】
- 自社商品/競合商品を知ったメディアを教えてください。
- 次の中で「知っているもの」「興味/関心のあるもの」「買ったことがあるもの」「継続して買っているもの」を選んでください。
これにより、自社商品ではどのプロセスがボトルネックになっているかを可視化できます。また、自社商品だけではなく競合商品の調査も行うことで自社のポジションを把握でき、適切な差別化対策につなげられるでしょう。
Surveroidなら、認知度調査テンプレートをそのままアンケートに反映可能です。
面倒な設問設計は不要。テンプレートを選ぶだけで、すぐに配信準備が整います。
面倒な設問設計は不要。テンプレートを選ぶだけで、すぐに配信準備が整います。
-
テンプレートでカンタン調査認知度調査テンプレートを見る
-
最短即日で配信もOK!アンケートを作成してみる
商品特徴の理解
ブランド認知度調査では、商品やブランドを知っているかだけではなく、その特徴まで理解しているかも確認するとよいでしょう。
-
【例】
- この商品についてご存じのことを、以下の中からすべてお選びください。
- この商品についてどのような印象をお持ちですか。自由にお書きください。
- この商品を使ってよかったこと、不満に思うことを教えてください。
これにより自社商品の理解されている特徴と伝わっていない特徴を把握でき、アピールポイントや差別化要素が消費者にきちんと伝わっていなければ、対策を組まねばなりません。また商品に対するイメージや印象を自由回答で聞くと、思いがけない情報を得られることがあります。さらに消費者にとってのベネフィットや不満点がわかれば、商品改善のヒントにもなるでしょう。
広告やプロモーションの接触状況
調査対象となる商品やサービス、ブランドの、広告やプロモーションの接触状況も、ブランド認知度調査ではよく使われる項目です。
-
【例】
- あなたはこの広告を見たことがありますか。
- この広告をどこで見ましたか。
- この広告を見て、商品を調べよう、買おうなどと思いましたか。あなたにあてはまる行動や考え方の変化をお選びください。
こうした質問をすることで、広告やプロモーションが認知や理解、購買行動にどのように影響したかなどを把握できます。また広告やプロモーションの好き嫌いや印象、インパクトなどを聞けば、以降の効果的な対策につなげられるでしょう。
認知度調査の具体的な設問例については下記記事で紹介しています。
認知度調査の具体的な設問例については下記記事で紹介しています。
今すぐ実践可能!認知度調査を成功に導く設問例と実施方法

認知度調査を成功させるための設問例や実施方法をわかりやすく解説。自社の立ち位置を把握し、効果的なマーケティング施策を立てるためのヒントが得られます。

認知調査結果の活用方法
調査結果を活用してマーケティング戦略を立案する際には、調査結果をいくつかの段階に分けたうえで施策を打っていく必要があります。
今回はユーザーの心理フェーズを4段階に分け、対処法をまとめました。
今回はユーザーの心理フェーズを4段階に分け、対処法をまとめました。
認知度が低い場合
認知度調査の結果、商品やサービスの認知度が低い場合、新規市場へのアプローチやプロモーション活動を強化することで、消費者の目に留まる機会を増やすことが有効です。
まずは、認知されていない理由やターゲット層の情報接触メディアを分析し、効果的な広告戦略を練りましょう。たとえば、SNS広告やインフルエンサーとのタイアップなど、特定のターゲット層に向けた訴求が可能になります。
さらに、消費者の関心を引くためのキャンペーンや、他ブランドとのコラボレーション企画を実施することで、消費者の注目を集め、ブランドの認知拡大が期待できます。
中でも、SNSを活用したプロモーションは、短期間でターゲット層へのリーチを大きく広げられるため、認知度が低い商品・サービスにとって非常に有力な打ち手と言えるでしょう。
まずは、認知されていない理由やターゲット層の情報接触メディアを分析し、効果的な広告戦略を練りましょう。たとえば、SNS広告やインフルエンサーとのタイアップなど、特定のターゲット層に向けた訴求が可能になります。
さらに、消費者の関心を引くためのキャンペーンや、他ブランドとのコラボレーション企画を実施することで、消費者の注目を集め、ブランドの認知拡大が期待できます。
中でも、SNSを活用したプロモーションは、短期間でターゲット層へのリーチを大きく広げられるため、認知度が低い商品・サービスにとって非常に有力な打ち手と言えるでしょう。
認知度はあるが、興味関心を惹けていない場合
認知度調査の結果、「ブランドの名前は知られているが、興味・関心を持たれていない」ことが分かった場合は、次のステップとして“関心を引く工夫”が必要です。
消費者にブランドの価値を伝えるには、興味を惹くストーリーや共感を生むコンテンツの提供が効果的です。たとえば、ブランドの背景や開発秘話、ユーザーの声などをブログ記事やSNSで発信し、ブランドの世界観に引き込むような工夫をしましょう。
また、ブランドの魅力を一貫して伝えることも重要です。ビジュアルや言葉づかい、投稿のトーンなどを統一し、ブランドアイデンティティを明確に打ち出すことで、消費者からの信頼感を醸成しやすくなります。
「認知はされているが関心が低い」という課題には、共感と体験を重視した情報発信が有効です。単なる情報提供ではなく、心を動かすブランド体験の設計を意識しましょう。
消費者にブランドの価値を伝えるには、興味を惹くストーリーや共感を生むコンテンツの提供が効果的です。たとえば、ブランドの背景や開発秘話、ユーザーの声などをブログ記事やSNSで発信し、ブランドの世界観に引き込むような工夫をしましょう。
また、ブランドの魅力を一貫して伝えることも重要です。ビジュアルや言葉づかい、投稿のトーンなどを統一し、ブランドアイデンティティを明確に打ち出すことで、消費者からの信頼感を醸成しやすくなります。
「認知はされているが関心が低い」という課題には、共感と体験を重視した情報発信が有効です。単なる情報提供ではなく、心を動かすブランド体験の設計を意識しましょう。
興味関心もあるが、商品購入に繋がっていない場合
認知度もあり、消費者の興味関心も得られているにもかかわらず、商品購入に繋がっていない場合は、購買行動を後押しする施策が重要になります。
まず、購買意欲を高めるには、「期間限定のキャンペーン」や「割引クーポン」といったインセンティブの提供が効果的です。今すぐ購入する理由を明確に提示することで、検討中のユーザーを動かすきっかけになります。
加えて、商品情報をわかりやすく整理し、購入までの導線をスムーズに整えることも重要です。たとえば、オンラインショップでは「送料」「返品条件」「サイズ感」などの詳細を明示することで、購入への不安を軽減できます。
また、ユーザーレビューや実際の購入者の声を掲載することで、商品への信頼感を高めることができます。レビュー機能の充実は、購買の最終決定を後押しするだけでなく、購入後の満足度向上にもつながります。
さらに、消費者のフィードバックをもとにした商品改善を継続的に行えば、リピート購入やファン化を促進する好循環を生み出すことが可能です。
まず、購買意欲を高めるには、「期間限定のキャンペーン」や「割引クーポン」といったインセンティブの提供が効果的です。今すぐ購入する理由を明確に提示することで、検討中のユーザーを動かすきっかけになります。
加えて、商品情報をわかりやすく整理し、購入までの導線をスムーズに整えることも重要です。たとえば、オンラインショップでは「送料」「返品条件」「サイズ感」などの詳細を明示することで、購入への不安を軽減できます。
また、ユーザーレビューや実際の購入者の声を掲載することで、商品への信頼感を高めることができます。レビュー機能の充実は、購買の最終決定を後押しするだけでなく、購入後の満足度向上にもつながります。
さらに、消費者のフィードバックをもとにした商品改善を継続的に行えば、リピート購入やファン化を促進する好循環を生み出すことが可能です。
商品購入はあるが、リピート購入に繋がっていない場合
認知度や初回購入には成功していても、リピート購入が伸び悩んでいる場合は、購入後の顧客フォローが鍵となります。リピート購入を促進するには、顧客満足度の向上と継続的な関係構築が不可欠です。
まず重要なのは、購入後のフォローアップ施策です。丁寧なカスタマーサポートや、使い方の案内・活用提案など、アフターサービスを充実させることで「また買いたい」と思ってもらえる体験を提供できます。
さらに、ポイント制度や会員限定の特典、定期的なメールマガジンなどを活用し、顧客との接点を持ち続けることがリピート率の向上につながります。購入履歴に基づいたパーソナライズドな提案も効果的です。
加えて、リピート購入を増やすためには、顧客の声を継続的に収集し、商品やサービスの改善に反映する姿勢も重要です。信頼関係を築き、長期的なファンを育てることで、安定したリピート購買を実現できるでしょう。
まず重要なのは、購入後のフォローアップ施策です。丁寧なカスタマーサポートや、使い方の案内・活用提案など、アフターサービスを充実させることで「また買いたい」と思ってもらえる体験を提供できます。
さらに、ポイント制度や会員限定の特典、定期的なメールマガジンなどを活用し、顧客との接点を持ち続けることがリピート率の向上につながります。購入履歴に基づいたパーソナライズドな提案も効果的です。
加えて、リピート購入を増やすためには、顧客の声を継続的に収集し、商品やサービスの改善に反映する姿勢も重要です。信頼関係を築き、長期的なファンを育てることで、安定したリピート購買を実現できるでしょう。
まとめ
認知度調査とは市場におけるブランドの浸透度を確認する調査で、主にマーケティング施策効果の確認やマーケティング戦略策定時に活用できます。
認知度調査を実施するには、自社で対応する場合と調査会社に依頼する方法があります。自社で行う場合は、調査会社が提供するサービスで数多くのモニターを利用できる「セルフ型ネットリサーチ」をおすすめします。
認知度調査を実施するには、自社で対応する場合と調査会社に依頼する方法があります。自社で行う場合は、調査会社が提供するサービスで数多くのモニターを利用できる「セルフ型ネットリサーチ」をおすすめします。
アンケートで市場調査を始めよう
セルフ型ネットリサーチツール「Surveroid(サーベロイド)」では、500万人以上の消費者モニターを保有しており、調査設計から面作成、配信、集計まで全ての業務をWeb上で完結できます。直感操作で利用でき、サポート体制も充実しているため、初めてアンケートを作成される方でも安心してご利用いただけます。
また「Surveroid」は初期費用・固定費が0円で、必要な時に必要な分だけ使える従量課金制を採用しております。
認知度調査をはじめリサーチ実施を検討しているなら、「Surveroid」のサービス内容をご確認ください。
また「Surveroid」は初期費用・固定費が0円で、必要な時に必要な分だけ使える従量課金制を採用しております。
認知度調査をはじめリサーチ実施を検討しているなら、「Surveroid」のサービス内容をご確認ください。
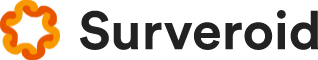 サーベロイドでリサーチをはじめませんか?
サーベロイドでリサーチをはじめませんか?
-
サービス概要・事例がわかる資料ダウンロード
-
ターゲットの声がすぐに聴ける登録してみる(無料)
65 件





