目次
インタビュー調査は、調査対象者の行動の理由や考え、インサイトなどを深く知るための調査です。インタビュー調査の分析は数字で表せない心理をまとめるため、わかりやすくまとめるにはポイントとなる発言や情報をカテゴライズ化して関係性を整理する必要があります。
本記事では、インタビュー調査の分析手法や分析の流れ、インタビュー調査を成功させるコツを解説します。
本記事では、インタビュー調査の分析手法や分析の流れ、インタビュー調査を成功させるコツを解説します。
-
定量・定性調査をワンストップで実施可能サービス詳細を見る

インタビュー調査における4つの分析方法
インタビュー調査の分析は、調査対象者の発言からポイントとなる言葉や情報を抽出してカテゴライズする必要があり、その手法としてコーディングやKJ法などが挙げられます。これらの手法を用いることで個々の発言に関係性を見い出すことができ、調査結果の分析や解釈がスムーズに行えるようになります。
主な分析手法を以下で詳しく解説します。
主な分析手法を以下で詳しく解説します。
テキストのコーディング
コーディングとは、調査対象者の発言を抽象化する短いフレーズや記号に置き換えて、データを体系的に整理・分類することです。これにより対象者がバラバラに発言している膨大な情報の中から、なんらかのパターンやテーマ、概念を見い出すことができます。
たとえば、「自分が自慢できること」をインタビューした結果を、その内容に応じて「仕事」「家族」「趣味」などでコーディングしたのが以下となります。
たとえば、「自分が自慢できること」をインタビューした結果を、その内容に応じて「仕事」「家族」「趣味」などでコーディングしたのが以下となります。

コーディングをする際にはコードNO.を付けたり、色分けしたりするとわかりやすいでしょう。
KJ法
定性情報を効率よく整理する手法として、「KJ法」もよく使われます。KJ法では、発言などの情報を1つずつ付箋などに書き込み、付箋を並べ替えたり類似したものをグループ化したりすることで情報を整理していきます。
前述のコーディングと組み合わせると効率的に情報整理ができ、発言の関係性や構造をわかりやすく可視化できるでしょう。また複数人で付箋を見ながら分析することで多様な意見が集まり、偏った解釈を避けることができます。
前述のコーディングと組み合わせると効率的に情報整理ができ、発言の関係性や構造をわかりやすく可視化できるでしょう。また複数人で付箋を見ながら分析することで多様な意見が集まり、偏った解釈を避けることができます。
KJ法の進め方
①コーディングで使ったコード(フレーズ、テーマなど)を付箋に書き込む

②類似した付箋をグループ化して名前を付ける

③グループ間の関係性やつながりを抽出・分析する
④導かれた構造や相関関係、包含関係などを図解で可視化する
④導かれた構造や相関関係、包含関係などを図解で可視化する

インサイトを読み取る
インタビュー調査の目的は、調査対象者の考えや深層心理を汲み取ることです。発言をそのままうのみにするのではなく、その言葉がうまれた背景や行動の理由なども意識することが重要です。
たとえば、「商品Aが使いづらかったので他人に譲った」は、言葉通りだと「商品Aが気に入らなくて他人にあげた」 ですが、このままだとなぜ使いづらいと感じたか、なぜ他人に譲ったのかがわかりません。
使いづらいと感じたのは、以前に使っていた同様の商品との比較したのかもしれません。また他人に譲るという選択肢となったのは、欲しいと思っている人がいたからかもしれません。これらの背景がわかれば、分析結果も深みのある内容となるでしょう。
分析者の主観による偏った判断を避けるためにも、言葉の影に隠れた調査対象者のインサイトを洞察する分析を心がけましょう。
たとえば、「商品Aが使いづらかったので他人に譲った」は、言葉通りだと「商品Aが気に入らなくて他人にあげた」 ですが、このままだとなぜ使いづらいと感じたか、なぜ他人に譲ったのかがわかりません。
使いづらいと感じたのは、以前に使っていた同様の商品との比較したのかもしれません。また他人に譲るという選択肢となったのは、欲しいと思っている人がいたからかもしれません。これらの背景がわかれば、分析結果も深みのある内容となるでしょう。
分析者の主観による偏った判断を避けるためにも、言葉の影に隠れた調査対象者のインサイトを洞察する分析を心がけましょう。
話し言葉を論理的な言葉に変更する
インタビューで得られた発言は、現場ならではの話し言葉であり、回答者が見たり考えたりしたことをその人自身の言葉で語ったものです。このままでは論理が曖昧で伝わりにくいため、内容を整理し、筋道の通った論理的な文章に変換することが重要です。
話し言葉を論理的な表現に置き換えることで、メッセージや主張がより明確に伝わり、一貫性のある読みやすい文章になります。
話し言葉を論理的な表現に置き換えることで、メッセージや主張がより明確に伝わり、一貫性のある読みやすい文章になります。
-
調査対象者を集めて深掘りできる!オンラインインタビューツールを見る

インタビュー調査後に実施する分析の流れ
続いて、インタビュー調査後に行う分析の流れをステップに分けて解説します。大きく「逐語録作成」「情報整理と分析」「レポート作成」に分かれます。
それぞれのステップを理解し、インタビュー後の分析に役立てましょう。
それぞれのステップを理解し、インタビュー後の分析に役立てましょう。
STEP1.逐語録を作成する
最初に逐語録を作成します。逐語録は会話内容をそのまま文字に起こして記録するもので、対象者の言葉の一つひとつを詳細に記録します。定性調査ではちょっとした言葉にインサイトが隠れている可能性があるため、冗長的な表現以外は一語たらずとも取りこぼさないよう心がけましょう。
また誰が何を発言したかがわかるように、Excelなどで表形式にまとめるとよいでしょう。逐語録はインタビュー中の考えや感情を忘れないうちにできるだけ早めに作成をして、必ずバックアップを取っておくことをおすすめします。
また誰が何を発言したかがわかるように、Excelなどで表形式にまとめるとよいでしょう。逐語録はインタビュー中の考えや感情を忘れないうちにできるだけ早めに作成をして、必ずバックアップを取っておくことをおすすめします。
| 項目 | 具体的なポイント・理由 |
|---|---|
| 記録の正確性・網羅性 | 一語一句、聞き取れる限り正確に文字起こしします。言い間違いや繰り返し、冗長な表現以外の「ちょっとした言葉」もインサイトに繋がるため、取りこぼさないようにします。 |
| 発言者の明確化 | 誰が何を発言したかを明確に区別して記録します(例:インタビュアー、A氏)。Excelなどの表形式でまとめると整理しやすくなります。 |
| タイムスタンプの活用 | 音声データの特定部分と照合しやすくするため、重要な発言や一定間隔でタイムスタンプ(例:[00:05:30])を付記します。 |
| ケバ取りルールの統一 | 「えーと」「あのー」といった意味のない言葉(ケバ)をどのように処理するか(全て残す、削除するなど)のルールを事前に決め、一貫して適用します。 |
| 作成タイミング | インタビュー中の対象者の考えや感情、場の雰囲気などを忘れないうちに、できるだけ早めに作成に着手します。 |
| データ管理 | 作成した逐語録データは、消失リスクを避けるために必ずバックアップを取っておきます。 |
| 効率化ツールの活用 | AI文字起こしツールや専門サービスを利用することで作成時間を短縮できます。ただし、ツール使用後も必ず人の目で確認し、修正を行うことが重要です。 |
STEP2.情報を整理して分析する
続いてまとめた逐語録をもとに、コーディングやKJ法により情報を整理・分類していきます。整理した情報間の関係性などから得られる気づきや示唆を元に、分析を進めていきましょう。
分析は原則として、調査の目的や仮説に沿って行います。目的や仮説に対する結果の確認や検証を行いつつ、目的・仮説とは直接関連はないものの新たな発見もあれば、しっかりと検証・考察をしておきましょう。
また整理や分類をした後、下記の点をポイントとして、まとめると更に情報が整理しやすくなります。
分析は原則として、調査の目的や仮説に沿って行います。目的や仮説に対する結果の確認や検証を行いつつ、目的・仮説とは直接関連はないものの新たな発見もあれば、しっかりと検証・考察をしておきましょう。
また整理や分類をした後、下記の点をポイントとして、まとめると更に情報が整理しやすくなります。
| 整理項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 頻出するキーワード・トピック | インタビュー全体を通して、複数の対象者から繰り返し出現する単語、フレーズ、話題などを抽出します。これらは参加者共通の関心事や重要なテーマを示唆している可能性が高いです。 |
| ポジティブ/ネガティブな発言 | 対象者が何に対して肯定的(満足、良い点、期待など)な感情を抱いているか、あるいは否定的(不満、悪い点、懸念など)な感情を抱いているかを明確に整理します。これはニーズや課題発見の直接的な手がかりとなります。 |
| 共感や類似した意見・経験 | 複数の対象者が同じような意見、感想、体験談、行動パターンなどを語っている箇所をグループ化します。これにより、共通性の高い見解や行動の傾向を把握できます。 |
| 印象的な発言やエピソード | 聞き手の記憶に強く残るような具体的なエピソード、感情が豊かに表現されている言葉、ユニークな比喩表現などをピックアップします。これらは、インサイトの発見や報告時の具体例として役立ちます。 |
STEP3.レポートを作成する
最後に分析した結果をレポートにまとめます。レポートは調査目的や仮説、調査方法、得られた気づきや結果などで構成するとよいでしょう。またグループインタビューならグループごとの特徴や発言の傾向、グループ間の違いを、デプスインタビューなら調査対象者のペルソナやインサイトが把握できるようにまとめましょう。
レポートは、グラフや図表、チャート、イラストなどを多用してビジュアル化すると、メッセージ性が高まります。
本質的なメッセージを直感的にわかりやすく伝えられるでしょう。
レポートは、グラフや図表、チャート、イラストなどを多用してビジュアル化すると、メッセージ性が高まります。
本質的なメッセージを直感的にわかりやすく伝えられるでしょう。

インタビュー調査を成功させるためのコツ
インタビュー調査を実際に行うには、以下の点に注意するとよいでしょう。
話しやすい雰囲気を作る
インタビュー調査で重要なことの一つに、相手との信頼関係を結ぶことが挙げられます。これを心理学用語で「ラポール(Rapport)」を形成するといいます。
インタビュー調査ではモデレーターと調査対象者は初対面であることが多く、対象者が緊張している状態では有益な発言を引き出すことが難しくなります。そのため最初にラポールを形成して、緊張を和らげ、話しやすい雰囲気を作ることが重要です。
たとえば、調査とは関係のない話から始める、適度に相槌や共感を示すなど、回答者の心理的な壁を取り除き気持ちよく話せるように促す行動を意識するとよいでしょう。
以下はその例になります。是非参考にしてみてください。
インタビュー調査ではモデレーターと調査対象者は初対面であることが多く、対象者が緊張している状態では有益な発言を引き出すことが難しくなります。そのため最初にラポールを形成して、緊張を和らげ、話しやすい雰囲気を作ることが重要です。
たとえば、調査とは関係のない話から始める、適度に相槌や共感を示すなど、回答者の心理的な壁を取り除き気持ちよく話せるように促す行動を意識するとよいでしょう。
以下はその例になります。是非参考にしてみてください。
インサイトを引き出す
インタビュー調査の最大の目的は、定量調査では見えにくい深層心理や本音を引き出すことです。そのためには、表面的な「はい」「いいえ」で終わらず、発言の背景や感情に迫る深掘り質問が欠かせません。
モデレーターは、回答者の言葉や反応をよく観察しながら、気になる発言があれば臨機応変に質問を重ねていきます。たとえば、「そのとき、どんな場面でしたか?」と具体的なエピソードを聞いたり、「どう感じましたか?」と感情に焦点を当てたり、「他の商品と比べてどう違いましたか?」と比較を促すことで、より深い気づきを得ることができます。
このような問いかけによって、表面的な情報ではなく、回答者の価値観や行動の理由といった、より本質的なインサイトを引き出すことができるのです。
モデレーターは、回答者の言葉や反応をよく観察しながら、気になる発言があれば臨機応変に質問を重ねていきます。たとえば、「そのとき、どんな場面でしたか?」と具体的なエピソードを聞いたり、「どう感じましたか?」と感情に焦点を当てたり、「他の商品と比べてどう違いましたか?」と比較を促すことで、より深い気づきを得ることができます。
このような問いかけによって、表面的な情報ではなく、回答者の価値観や行動の理由といった、より本質的なインサイトを引き出すことができるのです。
表情や感情を汲み取る
インタビュー調査は対話形式で行うため、回答者の言葉だけでなく、表情や声のトーン、場の雰囲気も観察しながら進められる点が特徴です。とくにグループインタビューでは、発言内容に加えて、他の参加者との関係性や空気感も、深い考えや感情を把握する手がかりになります。
こうした非言語情報を丁寧に読み取ることで、表面的な発言の奥にある本音や価値観が見えてくることもあります。インタビューの質を高めるためには、相手の反応を見ながら、話しやすいタイミングや自然な誘導の仕方を意識して対話を進めることが大切です。
こうした非言語情報を丁寧に読み取ることで、表面的な発言の奥にある本音や価値観が見えてくることもあります。インタビューの質を高めるためには、相手の反応を見ながら、話しやすいタイミングや自然な誘導の仕方を意識して対話を進めることが大切です。

インタビュー結果をうまくまとめるためのポイント
最後に、インタビュー調査の結果をわかりやすく上手にまとめるコツを解説します。
デブリーフィングの内容を活かす
デブリーフィングとは、インタビュー終了後にモデレーターやリサーチャー、モニタールームに控えていた関係者などが集まり、結果を振り返るミーティングのことです。参加者全員でインタビューの発言や反応を共有しながら、その背景にある意図や感情、仮説の妥当性について意見を交わす場となります。
この場では、インタビュー中に見落としがちな重要な示唆や気づきが浮かび上がることも多く、次回以降の調査設計の改善にもつながります。
調査結果をより深く解釈し、有意義な分析につなげるためにも、デブリーフィングはインタビュー直後に必ず実施し、その内容をレポートや考察に活用することが効果的です。
この場では、インタビュー中に見落としがちな重要な示唆や気づきが浮かび上がることも多く、次回以降の調査設計の改善にもつながります。
調査結果をより深く解釈し、有意義な分析につなげるためにも、デブリーフィングはインタビュー直後に必ず実施し、その内容をレポートや考察に活用することが効果的です。
目的や仮説に沿ってまとめる
インタビュー調査を効果的にまとめるためには、事前に設定した目的や仮説に沿って情報を整理することが大切です。
インタビューでは多くの自由な発言が得られますが、中には調査の目的から外れた内容や、重要度の低い意見も含まれています。そうした情報まで網羅的にまとめてしまうと、論点がぶれてしまい、伝えたい示唆がぼやけてしまう恐れがあります。
たとえば「新機能Xの改善点を探る」という目的であれば、機能Xの使い勝手に関する課題や要望に焦点を当てて整理することが重要です。目的に合った情報を優先的に取り上げることで、分析に一貫性が生まれ、本当に価値のある洞察を導き出すことができます。
このように、目的意識をもって取捨選択しながら整理することで、レポートの明確性が高まり、具体的な改善提案や次のアクションにもつながりやすくなります。
インタビューでは多くの自由な発言が得られますが、中には調査の目的から外れた内容や、重要度の低い意見も含まれています。そうした情報まで網羅的にまとめてしまうと、論点がぶれてしまい、伝えたい示唆がぼやけてしまう恐れがあります。
たとえば「新機能Xの改善点を探る」という目的であれば、機能Xの使い勝手に関する課題や要望に焦点を当てて整理することが重要です。目的に合った情報を優先的に取り上げることで、分析に一貫性が生まれ、本当に価値のある洞察を導き出すことができます。
このように、目的意識をもって取捨選択しながら整理することで、レポートの明確性が高まり、具体的な改善提案や次のアクションにもつながりやすくなります。
分析結果を検証する
インタビュー調査の分析結果は、担当者の視点によって解釈が異なることがあります。そのため、複数のメンバーで結果を共有し、第三者の視点から検証を行うことが重要です。
たとえば、「主観的な解釈に偏っていないか」「仮説に沿って論理的に構成されているか」「主張に対する根拠が明確か」といった観点でチェックを行うと、分析の精度と説得力が高まります。
このような検証を通じて、仮説が支持されるかどうかを客観的に確認できるだけでなく、調査手法やレポート構成の改善点も見えてきます。
また、レポートの信頼性と妥当性を担保する意味でも、分析後の検証プロセスは必ず組み込むべきステップです。
たとえば、「主観的な解釈に偏っていないか」「仮説に沿って論理的に構成されているか」「主張に対する根拠が明確か」といった観点でチェックを行うと、分析の精度と説得力が高まります。
このような検証を通じて、仮説が支持されるかどうかを客観的に確認できるだけでなく、調査手法やレポート構成の改善点も見えてきます。
また、レポートの信頼性と妥当性を担保する意味でも、分析後の検証プロセスは必ず組み込むべきステップです。
インタビュー結果を図解で整理する
インタビュー調査では、多様な発言や意見が得られる一方で、情報が複雑に入り組みやすく、文章だけでは伝えきれないこともあります。そこで、発言の整理や示唆の可視化には図解が効果的です。
たとえば、以下のような図解方法がよく使われます。
・テーマごとの発言分類図:意見をカテゴリ別に分け、共通点や相違点を視覚化する
・ペルソナ別のニーズ比較表:異なるタイプのユーザーごとに発言傾向を並べて整理する
・カスタマージャーニー図:利用体験に沿って感情や課題の変化を時系列で示す
このような図を用いることで、読み手が全体像や背景の構造を直感的に理解できるようになります。特にチーム内での共有や関係者への報告では、理解のスピードと納得感を高める効果があります。
ただし、定量データのような「数値的な正確さ」を示す意図ではないことを明記することが重要です。誤解を避けるためにも、「図は傾向の整理を目的とした参考資料である」と補足しておくと良いでしょう。
たとえば、以下のような図解方法がよく使われます。
・テーマごとの発言分類図:意見をカテゴリ別に分け、共通点や相違点を視覚化する
・ペルソナ別のニーズ比較表:異なるタイプのユーザーごとに発言傾向を並べて整理する
・カスタマージャーニー図:利用体験に沿って感情や課題の変化を時系列で示す
このような図を用いることで、読み手が全体像や背景の構造を直感的に理解できるようになります。特にチーム内での共有や関係者への報告では、理解のスピードと納得感を高める効果があります。
ただし、定量データのような「数値的な正確さ」を示す意図ではないことを明記することが重要です。誤解を避けるためにも、「図は傾向の整理を目的とした参考資料である」と補足しておくと良いでしょう。
-
データ+本音で納得とアクションにつなげるSurveroidに登録してみる
まとめ
インタビュー調査は、調査対象者の考えや心理など数字で表せないことを知る調査であるため、その分析は、ポイントとなる発言や情報をグループ化して関係性を整理しながら気づきや示唆を探していきます。また定量調査と組み合わせればより深い分析が可能となり、自社のさまざまなマーケティング活動に活用できるでしょう。
仮説検証もインタビューも、ワンストップで完結するSurveroid
定量調査と定性調査を組み合わせて、より深いインサイトを得たい場合には、セルフ型アンケートツール「Surveroid(サーベロイド)」の活用がおすすめです。
Surveroidでは、アンケートによる定量的なリサーチだけでなく、特定の条件を満たす回答者(モニタ)をリクルーティングし、インタビュー調査につなげることも可能です。たとえば、アンケートの結果から気になる回答傾向があった層に対して、そのまま深掘りインタビューを依頼する流れがスムーズに設計できます。
また、以下のような特長があります。
・調査対象者の条件設定や回収管理が簡単にできる
・全国600万人のパネルから目的に合ったモニタをリクルート可能
・アンケート後のインタビュー実施も柔軟に対応
定量→定性という調査プロセスをワンストップで進行できるため、仮説の検証から深掘りまでを一貫して行いたいプロジェクトに非常に適しています。
Surveroidでは、アンケートによる定量的なリサーチだけでなく、特定の条件を満たす回答者(モニタ)をリクルーティングし、インタビュー調査につなげることも可能です。たとえば、アンケートの結果から気になる回答傾向があった層に対して、そのまま深掘りインタビューを依頼する流れがスムーズに設計できます。
また、以下のような特長があります。
・調査対象者の条件設定や回収管理が簡単にできる
・全国600万人のパネルから目的に合ったモニタをリクルート可能
・アンケート後のインタビュー実施も柔軟に対応
定量→定性という調査プロセスをワンストップで進行できるため、仮説の検証から深掘りまでを一貫して行いたいプロジェクトに非常に適しています。
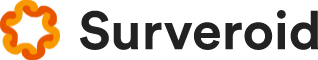 定量も、インタビューも。まとめてできるサーベロイド
定量も、インタビューも。まとめてできるサーベロイド
-
サービス概要・事例がわかるサービス資料を見る
-
ターゲットの声がすぐに聴ける登録してみる(無料)
63 件





