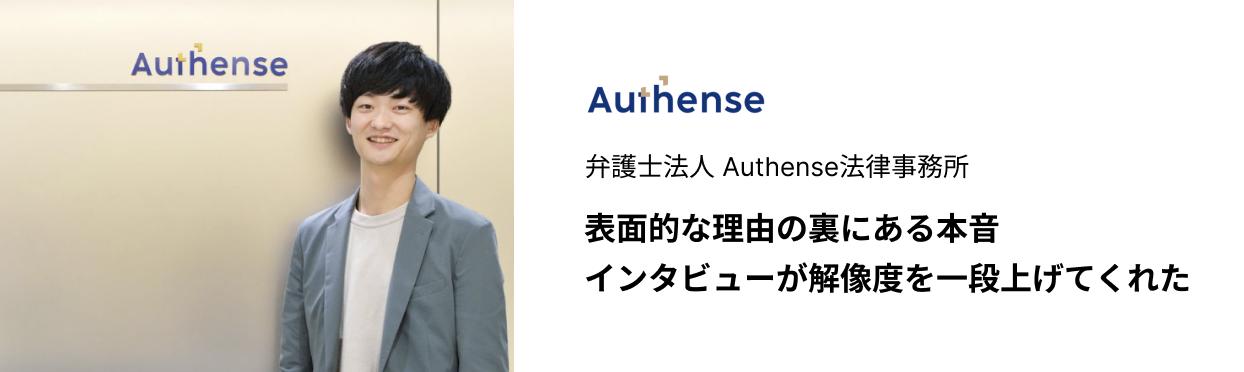目次
インタビュー調査は、数量で表せない消費者心理やニーズ、行動の背景などを深く理解したい場合に適しています。グループインタビューとデプスインタビューがあり、それぞれの特徴を活かして調査を行うと、購買プロセスやカスタマージャーニーの把握、新商品・サービスの仮説構築など、あらゆるマーケティング活動に役立てられます。
本記事では、インタビュー調査の効果的な活用方法やグループインタビュー・デプスインタビューのメリット・デメリット、インタビュー調査を実施する手順などを解説します。
本記事では、インタビュー調査の効果的な活用方法やグループインタビュー・デプスインタビューのメリット・デメリット、インタビュー調査を実施する手順などを解説します。

インタビュー調査とは?
インタビュー調査とは、あるテーマについてインタビュアーが個人やグループを対象に直接質問して、情報を集め分析する手法です。インタビュー調査は定性調査の一種で、対象者のリアルな声から消費者心理や行動の理由、インサイト、感情の変化といった数量で表せない情報を把握する際に適しています。
インタビュー調査には、4~6名程度のグループを対象に行う「グループインタビュー」と、1対1でヒアリングを行う「デプスインタビュー」があります。従来は対面で行われていましたが、近年はそれぞれオンラインで行うことも増えています。
インタビュー調査には、4~6名程度のグループを対象に行う「グループインタビュー」と、1対1でヒアリングを行う「デプスインタビュー」があります。従来は対面で行われていましたが、近年はそれぞれオンラインで行うことも増えています。
ユーザーの深層心理を理解する定性調査
インタビュー調査の最大の特徴は、対象者の言葉や表情、しぐさから、その背景にある深層心理やインサイトを読み取れる点にあります。
例えば、「なぜこの製品を選んだのか」「どのような点に不満を感じているのか」といった問いに対して、深く掘り下げて質問することで、本人も意識していなかったような潜在的なニーズや課題を発見できる可能性があります。このようにして得られた情報は、新しい商品開発のアイデアや、既存サービスの改善点を具体的に見つけ出す上で役立ちます。
例えば、「なぜこの製品を選んだのか」「どのような点に不満を感じているのか」といった問いに対して、深く掘り下げて質問することで、本人も意識していなかったような潜在的なニーズや課題を発見できる可能性があります。このようにして得られた情報は、新しい商品開発のアイデアや、既存サービスの改善点を具体的に見つけ出す上で役立ちます。
アンケート調査との違い
インタビュー調査とよく比較されるのが、アンケート調査です。アンケート調査は、多数の対象者から定量的なデータを効率的に集めることに適した「定量調査」です。一方、インタビュー調査は、少数の対象者から定性的な情報を深く収集することに重点を置いています。
| 項目 | インタビュー調査(定性調査) | アンケート調査(定量調査) |
|---|---|---|
| 目的 | 深層心理の理解、仮説発見 | 実態把握、仮説検証 |
| 対象者数 | 数名~数十名 | 数百名~数千名 |
| 収集データ | 発言、行動、文脈 | 数値、選択肢 |
| 分析方法 | 発言の解釈、構造化 | 統計解析 |
| メリット | 予期せぬ発見がある、深い情報が得られる | 結果を一般化しやすい、傾向が見やすい、コストが安い |
| デメリット | 結果の一般化が難しい、コストが高い | 浅い情報しか得られない、質問設計が難しい |
インタビュー調査が適しているケース
人数や規模、割合といった数量を調べて傾向を知る定量調査と異なり、インタビュー調査を含む定性調査では、数量では把握できづらい深層心理や本音に迫ることができます。そのためインタビュー調査は、以下のようなマーケティング活動や課題解決に適しています。
①実態把握やターゲットインサイトの発掘
インタビュー調査では微妙な感情の変化や態度も重要なデータとして回収できるため、より深い実態把握やターゲット理解が実現します。
単純に回答を集めるだけではなく、発言で気になった内容を深掘りできるほか、具体的なエピソードなど派生した質問も可能です。そのため商品の購入検討プロセスや意思決定の過程などを順を追って理解したい場合や、商品利用にまつわるエピソード、使う場面ごとの感情の把握などに役立つでしょう。これらのデータを得ることで、最適なカスタマージャーニーの作成や顧客が望むCX提供が可能となります。
また対象者の声や表情、身振りといった非言語情報も観察でき、より深い行動心理や対象者自身も気づいていないインサイトを汲み取ることもできます。
単純に回答を集めるだけではなく、発言で気になった内容を深掘りできるほか、具体的なエピソードなど派生した質問も可能です。そのため商品の購入検討プロセスや意思決定の過程などを順を追って理解したい場合や、商品利用にまつわるエピソード、使う場面ごとの感情の把握などに役立つでしょう。これらのデータを得ることで、最適なカスタマージャーニーの作成や顧客が望むCX提供が可能となります。
また対象者の声や表情、身振りといった非言語情報も観察でき、より深い行動心理や対象者自身も気づいていないインサイトを汲み取ることもできます。
②商品開発や試作品に対する反応の確認
新商品開発のためのヒントを得たい場合や、新サービスが市場で受け入れられるかを確認したい際にもインタビュー調査が有効です。対象者の素直な意見や細かな指摘などを掘り下げて聞けるため、新たなニーズやアイデアの手がかりが見つかります。
③仮説の構築
消費者の行動や態度を量的に把握できる定量調査は、主に「仮説の検証」で使われます。一方インタビュー調査などの定性調査では、行動や態度の背景にある心理や感情、隠れた意識などを探ることができるため、「仮説の構築」や「仮説の見直し」などで活用できます。
定量調査と定性調査の違いは、以下の記事でも詳しく解説していますので参考にしてください。
【関連記事】定量調査とは?定性調査との違いからやり方まで紹介
定量調査と定性調査の違いは、以下の記事でも詳しく解説していますので参考にしてください。
【関連記事】定量調査とは?定性調査との違いからやり方まで紹介
-
セルフでオンラインインタビューができるセルフ型リサーチツール「Surveroid」
インタビュー調査のメリット
インタビュー調査を実施することで、企業は多くのメリットを得ることができます。ここでは、主な3つのメリットについて解説します。
数値では見えない生の声が聞ける
インタビュー調査最大のメリットは、アンケートの数値データだけでは決して分からない、ユーザーの「生の声」を聞ける点です。製品やサービスに対する満足・不満の理由、利用シーンにおける具体的なエピソード、言葉のニュアンスなど、定性的な情報を得ることで、ユーザーをより深く、立体的に理解することができます。
予期せぬ発見やアイデアが得られる
構造化されたアンケートとは異なり、インタビュー調査では対話の流れに応じて柔軟に質問を変えることができます。その過程で、企業側が全く想定していなかったような、新しい発見や製品開発のヒント、改善のアイデアが得られることが少なくありません。この「偶発性」こそが、イノベーションのきっかけとなることがあります。
顧客との関係性を構築できる
一人の顧客と真摯に向き合い、じっくりと話を聞くという行為は、顧客ロイヤルティの向上にも繋がります。「自分の意見が企業に届いている」という実感は、顧客にとって特別な体験となり、企業やブランドへの愛着を深めるきっかけになります。これは、長期的な顧客関係を構築する上で重要です。
インタビュー調査のデメリット
多くのメリットがある一方で、インタビュー調査にはいくつかのデメリットも存在します。計画段階でこれらの点を十分に理解しておくことが重要です。
調査コストが高くなりやすい
インタビュー調査は、対象者のリクルーティング費用や謝礼、会場費、インタビュアーの人件費、文字起こし費用など、アンケート調査に比べてコストが高くなる傾向があります。特に、専門性の高い対象者や、出現率の低い条件の対象者を探す場合は、リクルーティング費用がさらに高額になる可能性があります。
対象者の選定が難しい
調査の成否は、適切な対象者を選定できるかどうかに大きく左右されます。設定した条件に合致し、かつ調査に協力的で、自分の意見を的確に言語化できる人を探し出すのは容易ではありません。対象者の選定を誤ると、調査の目的からずれた、価値の低い情報しか得られない結果になりかねません。
結果の一般化が困難
インタビュー調査は、あくまで少数の個人を対象とした調査であるため、その結果を市場全体の意見として一般化することはできません。得られた定性的な情報は、あくまで「仮説の発見」や「インサイトの抽出」を目的とするものであり、その仮説が市場全体に当てはまるかどうかを検証するためには、別途アンケート調査などの定量調査が必要になります。
-
インタビュー後の検証までスムーズにできるインタビュー調査で深掘りする方法を見る

インタビュー調査の種類【メリット・デメリット・活用例】
ここからは「グループインタビュー」と「デプスインタビュー」について、それぞれの活用例やメリット・デメリットを解説します。それぞれの特徴を理解して、自社の課題解決に合った手法を選択しましょう。
①グループインタビュー
グループインタビュー(FGI:Focus Group Interview)は、モデレーターと呼ばれる司会者が調査テーマに基づいた設問を対象者に投げかけ、座談会形式で自由に発言してもらいながら進めていく手法です。一般的には4~6名で1グループを構成し、120分程度で行います。複数人が参加するため多くの情報を収集でき、商品評価などでは多面的・多角的な意見を得られるのが特徴です。
また事前に参加する対象者にアンケート調査を行い、その内容に沿ってグループインタビューで深掘りして聞くと効率よく進められます。
1つのグループは属性や価値観が近い人、商品の使用状況が同程度の人同士などで構成すると、意見交換が活発になる傾向があります。調査テーマに応じて、以下のような要素で分類するとよいでしょう。
また事前に参加する対象者にアンケート調査を行い、その内容に沿ってグループインタビューで深掘りして聞くと効率よく進められます。
1つのグループは属性や価値観が近い人、商品の使用状況が同程度の人同士などで構成すると、意見交換が活発になる傾向があります。調査テーマに応じて、以下のような要素で分類するとよいでしょう。
グループの分類要素例
- 性別、年齢、未既婚、子どもの有無
- 専業主婦、パート、フルタイム職
- 商品やサービスの利用頻度、満足度 など
同じような年代や境遇の参加者同士の意見が集められるため、以下のような調査に適しています。
グループインタビューに適した活用例
- 商品・サービスの評価、改善要望
- 商品コンセプトやパッケージデザイン、広告の評価
- 競合商品ユーザーの利用実態把握
- 属性別の消費傾向、価値観把握 など
グループインタビューは、複数人が参加するためほかの人の意見に刺激されて思いがけない発言がうまれやすくなる反面、1つの意見を掘り下げて聞くのは難しいといったデメリットもあります。
グループインタビューの主なメリット・デメリットは以下となります。
グループインタビューの主なメリット・デメリットは以下となります。
メリット
|
デメリット
|
②デプスインタビュー
デプスインタビュー(DI:Depth Interview)は、モデレーターと1人の調査対象者が面談方式で行う手法です。「深層面接法」とも呼ばれ、30~90分程度の時間をかけてじっくりと深掘りしながら意見を聞けるのが特徴です。
1対1の対談なので、グループインタビューでは話しづらいデリケートなテーマを対象にでき、他人の意見に左右されない本音を引き出すことができます。個人の意志決定プロセスや感情の動きをていねいに知りたい場合や、パーソナルなことを深く掘り下げたいシーンに適しています。
1対1の対談なので、グループインタビューでは話しづらいデリケートなテーマを対象にでき、他人の意見に左右されない本音を引き出すことができます。個人の意志決定プロセスや感情の動きをていねいに知りたい場合や、パーソナルなことを深く掘り下げたいシーンに適しています。
デプスインタビューに適した活用例
- 購買プロセスやカスタマージャーニーの把握
- 新商品やサービスの仮説構築、コンセプトのブラッシュアップ
- ターゲットの深層心理やインサイトの把握
- デリケートなテーマの調査 など
デプスインタビューは1人の意見を掘り下げて聞ける反面、対象者が緊張して本音を話しづらくなる可能性もあるため、リラックスした環境づくりが重要です。また対象者の感情や態度に合わせた臨機応変な対応が必要なので、モデレーターには高いスキルが求められます。
以下にデプスインタビューのメリット・デメリットをまとめたので参考にしてください。
以下にデプスインタビューのメリット・デメリットをまとめたので参考にしてください。
メリット
|
デメリット
|
③オンラインインタビュー
オンラインインタビューはZoomやMicrosoft Teams、Google Meet、Skypeなどのビデオ会議ツールや、電話、チャットアプリを通じて行われるインタビューです。地理的な制約を超えて、遠隔地にいる参加者の情報を収集できるのが特徴です。
オンラインインタビューに適した活用例
- 遠隔地に住むターゲットのインサイトの収集
- 広告メッセージ評価の地域による比較
- リモートワークの従業員満足度調査
- 社会的なテーマや問題について広範な地域から意見を求める社会調査、教育研究 など
オンラインインタビューは、地理的な制約のない広範な情報を収集できるものの、技術的な問題や非対面コミュニケーションによるデメリットもあります。これらを理解し適切に対策を講じることで、効果的なインタビューを実施できます。
以下にオンラインインタビューのメリット・デメリットをまとめたので参考にしてください。
以下にオンラインインタビューのメリット・デメリットをまとめたので参考にしてください。
メリット
|
デメリット
|
-
セルフでオンラインインタビューが出来る!サーベロイドへ登録する(無料)
インタビュー調査の事例を紹介
事例1: 新商品開発のための消費者インサイト収集
背景と方法:
ある飲料メーカーが新商品を開発する際、消費者のニーズや嗜好を深く理解するためにインタビュー調査を実施しました。ターゲットとなる消費者を年齢、性別、ライフスタイルでセグメント分けし、それぞれのグループから代表者を選んで対面インタビューを行いました。調査の焦点は、日常生活での飲料の選び方、好みのフレーバー、新しい飲料に求める機能など、消費者の潜在的なニーズを探ることでした。
効果:
インタビュー調査を通じて、従来の市場調査では得られなかった消費者の生の声や感情が浮き彫りになりました。これにより、メーカーは消費者が求める具体的なフレーバーやパッケージデザインを明確に把握でき、商品コンセプトの設計に役立てることができました。結果として、新商品はターゲット消費者に高く評価され、発売後すぐに売上が好調に推移しました。
ある飲料メーカーが新商品を開発する際、消費者のニーズや嗜好を深く理解するためにインタビュー調査を実施しました。ターゲットとなる消費者を年齢、性別、ライフスタイルでセグメント分けし、それぞれのグループから代表者を選んで対面インタビューを行いました。調査の焦点は、日常生活での飲料の選び方、好みのフレーバー、新しい飲料に求める機能など、消費者の潜在的なニーズを探ることでした。
効果:
インタビュー調査を通じて、従来の市場調査では得られなかった消費者の生の声や感情が浮き彫りになりました。これにより、メーカーは消費者が求める具体的なフレーバーやパッケージデザインを明確に把握でき、商品コンセプトの設計に役立てることができました。結果として、新商品はターゲット消費者に高く評価され、発売後すぐに売上が好調に推移しました。
事例2: 新しいモバイルアプリのユーザビリティテスト
背景と方法:
あるスタートアップ企業が新しいモバイルアプリの開発を進めており、正式リリース前にユーザビリティテストを行うことにしました。ターゲットユーザー層の意見を直接聞くために、オンラインインタビューを実施することが決定されました。テストには、事前にリクルートしたターゲットユーザー(10代から30代の若者)をリモートで参加させ、画面共有を通じてアプリの使用状況を観察しながら質問を行いました。インタビューはビデオ通話を利用して行い、参加者の表情やリアクションもリアルタイムで確認できるようにしました。
効果:
オンラインインタビューを通じて、ユーザーがアプリを操作する際のリアルな体験や問題点が明らかになりました。特に、特定の機能が使いにくいと感じる部分や、ナビゲーションのわかりにくさが指摘されました。また、ユーザーが実際にどういう場面でアプリを使おうとしているのかといった、実利用シーンについての具体的なフィードバックも得られました。これらのフィードバックをもとに、開発チームはアプリのUI/UXを改善し、リリース後のユーザー満足度の向上に成功しました。
あるスタートアップ企業が新しいモバイルアプリの開発を進めており、正式リリース前にユーザビリティテストを行うことにしました。ターゲットユーザー層の意見を直接聞くために、オンラインインタビューを実施することが決定されました。テストには、事前にリクルートしたターゲットユーザー(10代から30代の若者)をリモートで参加させ、画面共有を通じてアプリの使用状況を観察しながら質問を行いました。インタビューはビデオ通話を利用して行い、参加者の表情やリアクションもリアルタイムで確認できるようにしました。
効果:
オンラインインタビューを通じて、ユーザーがアプリを操作する際のリアルな体験や問題点が明らかになりました。特に、特定の機能が使いにくいと感じる部分や、ナビゲーションのわかりにくさが指摘されました。また、ユーザーが実際にどういう場面でアプリを使おうとしているのかといった、実利用シーンについての具体的なフィードバックも得られました。これらのフィードバックをもとに、開発チームはアプリのUI/UXを改善し、リリース後のユーザー満足度の向上に成功しました。
Surveroidならインタビューとアンケートを一気通貫で実施できる
セルフ型アンケートツールの「Surveroid(サーベロイド)」なら、オンラインインタビュー(デプス)とアンケート調査を同じツール上で組み合わせたリサーチをセルフで簡単に実施でき、目的に合わせた自由な設計が可能です。
ワンストップで実施できるため、欲しい結果を迅速に得られるでしょう。
アンケートとインタビュー調査を活用したユーザー事例も公開しています。ぜひご覧ください。
ワンストップで実施できるため、欲しい結果を迅速に得られるでしょう。
アンケートとインタビュー調査を活用したユーザー事例も公開しています。ぜひご覧ください。

インタビュー調査の実施手順
ここからは、インタビュー調査を実施する手順とコツを7つのステップ別に解説します。
手順1.調査の目的を明確にする
インタビュー調査を行うには、最初にその目的を明確にしましょう。
「調査により何を明らかにするのか」「調査結果をどう活用するか」といった目的をはっきりさせることで、調査設計をブレることなく進められます。得られた結果も有効活用できるでしょう。
また目的や用途を明文化して関係者間で共有しておくと、調査進行や意思決定をスムーズに進められます。
「調査により何を明らかにするのか」「調査結果をどう活用するか」といった目的をはっきりさせることで、調査設計をブレることなく進められます。得られた結果も有効活用できるでしょう。
また目的や用途を明文化して関係者間で共有しておくと、調査進行や意思決定をスムーズに進められます。
手順2.調査の概要を策定する
続いて調査概要を作ります。概要策定にあたって決めておきたいことは以下となります。
調査概要の項目
- 調査の目的、用途
- 調査の種類(グループインタビューorデプスインタビュー)
- 実施形態(オフライン・オンライン)
- 対象者人数
- 実査日時、スケジュール(準備~実施~分析・レポート作成)
- 実査場所(オフラインの場合)
- 必要備品(撮影・記録機材、謝礼、茶菓など)
- 予算
- 管理者、実査機関 など
調査は目的や用途に応じて、グループインタビューにするかデプスインタビューにするのか、またオンラインかオフラインかを決めます。オフラインの場合は、会場も用意しなければなりません。
グループインタビューの場合は1グループの人数や何グループにするのか、またデプスインタビューの場合は何人に聞くのかといった対象者人数も決めておきましょう。
続いて調査日時や1回あたりの所要時間、準備期間や調査後の分析・レポート作成まで、どのくらいの期間で行うかをスケジューリングします。調査結果を基に意思決定をする日程に間に合うように、スケジュールを組みましょう。
一連の業務を予算内に収めることも重要です。また調査の管理者や実査機関も決めておくことで、役割と責任体制が明確になります。
グループインタビューの場合は1グループの人数や何グループにするのか、またデプスインタビューの場合は何人に聞くのかといった対象者人数も決めておきましょう。
続いて調査日時や1回あたりの所要時間、準備期間や調査後の分析・レポート作成まで、どのくらいの期間で行うかをスケジューリングします。調査結果を基に意思決定をする日程に間に合うように、スケジュールを組みましょう。
一連の業務を予算内に収めることも重要です。また調査の管理者や実査機関も決めておくことで、役割と責任体制が明確になります。
手順3.調査を具体的に設計する
概要ができたら、詳細な調査設計に移ります。設計のポイントは、「誰に聞くか」「何を聞くか」を明らかにすることです。
対象者条件を決める
まず概要で決めた対象人数に応じて、実際に「誰に聞くか」といった対象条件を具体化します。
インタビュー調査は発言者の言葉や態度、深層心理などを確認するため、対象者選びが重要です。属性や生活環境、価値観、対象となる商品・サービスの利用実態など、調査目的やその後の用途に適した対象条件を選択しましょう。
グループインタビューでは属性や価値観が近い人を1つのグループにまとめ、意見が異なることが想定される対象者は別グループに分けておきましょう。
インタビュー調査は発言者の言葉や態度、深層心理などを確認するため、対象者選びが重要です。属性や生活環境、価値観、対象となる商品・サービスの利用実態など、調査目的やその後の用途に適した対象条件を選択しましょう。
グループインタビューでは属性や価値観が近い人を1つのグループにまとめ、意見が異なることが想定される対象者は別グループに分けておきましょう。
聴取内容を決める
続いて、「何を聞くか」といった聴取内容を決めます。調査目的や用途に応じて、聞くべき要素や何を明らかにするかを具体的に書き出します。
また事前に立てた仮説を検証できる内容か、対象者の思考や感情をしっかりと引き出せる内容になっているかなどに留意して、質問項目を作るとよいでしょう。
また事前に立てた仮説を検証できる内容か、対象者の思考や感情をしっかりと引き出せる内容になっているかなどに留意して、質問項目を作るとよいでしょう。
手順4.インタビューフローを作成する
対象者条件や聴取内容が決まったら、インタビューフローを作成します。インタビューフローとは、質問する順番や時間配分などをまとめた台本のことで、決められた時間内でどのように進行するかを整理しましょう。
インタビューフローの構成例
- モデレーター開始挨拶(調査の目的、インタビューにあたってのお願いなど)
- 対象者自己紹介
- インタビュー調査開始
- 質問の優先順位を決め順番を決めておく
- 各質問にかける時間を決めておく
- アイスブレイク的な質問から始めるとよい
- モデレーター終了挨拶(インタビューのお礼、言い足りないことの確認、謝礼がある場合はその案内など)
一般的にグループインタビューは120分程度、デプスインタビューは30~90分程度となり、その時間内におさまるように整理しましょう。
手順5.対象者をリクルートする
インタビューフローができたら、対象者のリクルートに移ります。対象者を選別する際には、条件に合致していることはもちろん、調査テーマに対して関心が高い人の方が適しています。関心がある分活発な意見を期待でき、想定以上の効果を得られる可能性が高まります。
リクルートの方法は、自社のモニターや知り合いの中から探すほか、幅広い調査モニターを有する調査会社の活用も効果的です。数多くのモニターから選出できるため効率的なリクルート業務となり、調査結果のクオリティアップも期待できます。
また絞り込んだ対象者には、録音や記録をすることの許可、個人情報活用に関する承諾などを事前に取る必要があります。忘れずに対処しましょう。
リクルートの方法は、自社のモニターや知り合いの中から探すほか、幅広い調査モニターを有する調査会社の活用も効果的です。数多くのモニターから選出できるため効率的なリクルート業務となり、調査結果のクオリティアップも期待できます。
また絞り込んだ対象者には、録音や記録をすることの許可、個人情報活用に関する承諾などを事前に取る必要があります。忘れずに対処しましょう。
手順6.インタビューを実施する
対象者が決まったら関係者への連絡、会場や録音・記録用機材の準備などを経て、実際の調査実施となります。
インタビュー調査では、最初の段階における話しやすい雰囲気づくりが重要です。モデレーターの最初の挨拶でジョークを交えたりアイスブレイクを入れたりなどで、対象者の緊張感をほぐしましょう。また回答には正解や不正解、良い・悪いがないことを伝え、対象者が自由に発言できるようにすることもポイントです。
モデレーターは常にフラットな立場で、対象者の回答を誘導しないように注意します。回答者が話しやすくするには回答に相づちを打つ、共感するなどもテクニックの1つです。
またインタビューは流れやリズムが重要で、特にグループインタビューでは1人の意見に集中するのではなく、全員がまんべんなく回答できるようにしましょう。
流れをスムーズにするには対象者の回答に応じた柔軟な対応が必要で、時間内で予定の質問を聞かねばならないため、モデレーターには高いスキルが求められます。必要であれば専門家に依頼することも検討しましょう。
インタビュー調査では、最初の段階における話しやすい雰囲気づくりが重要です。モデレーターの最初の挨拶でジョークを交えたりアイスブレイクを入れたりなどで、対象者の緊張感をほぐしましょう。また回答には正解や不正解、良い・悪いがないことを伝え、対象者が自由に発言できるようにすることもポイントです。
モデレーターは常にフラットな立場で、対象者の回答を誘導しないように注意します。回答者が話しやすくするには回答に相づちを打つ、共感するなどもテクニックの1つです。
またインタビューは流れやリズムが重要で、特にグループインタビューでは1人の意見に集中するのではなく、全員がまんべんなく回答できるようにしましょう。
流れをスムーズにするには対象者の回答に応じた柔軟な対応が必要で、時間内で予定の質問を聞かねばならないため、モデレーターには高いスキルが求められます。必要であれば専門家に依頼することも検討しましょう。
手順7.分析、レポートを作成する
インタビュー調査終了後は発言録の作成や、インタビューで得られた気づきや発見、調査目的に応じた分析、調査結果を今後どう活かすかといった内容でレポートを作成します。まとめるコツは、「目的に応じた結果の検証」と「調査結果の活用に関する提案」です。
インタビュー調査のレポートでは、調査で明確にしたいテーマや目的に沿って発言や情報を抽出してカテゴライズを行い、結論をまとめあげていきます。インタビューだからこそ聞き出せた意識や感情、購買の背景などをロジカルに構造化することを心がけましょう。
また調査結果をどのように活用するか、調査結果から優先的に何に取り組むべきかの提案などを含めると、良いレポートになるでしょう。
インタビュー調査のレポートでは、調査で明確にしたいテーマや目的に沿って発言や情報を抽出してカテゴライズを行い、結論をまとめあげていきます。インタビューだからこそ聞き出せた意識や感情、購買の背景などをロジカルに構造化することを心がけましょう。
また調査結果をどのように活用するか、調査結果から優先的に何に取り組むべきかの提案などを含めると、良いレポートになるでしょう。
インタビュー調査の分析については、以下の記事でも詳しく解説していますので参考にしてください。
インタビュー調査の分析方法は?分析の流れや成功のポイントも紹介
インタビュー調査の分析方法は?分析の流れや成功のポイントも紹介
定量調査・定性調査にはセルフ型アンケートツールもおすすめ
インタビュー調査などの定性調査は定量調査と組み合わせて行うと、より深いターゲットの理解や分析、洞察が可能となります。これらの調査には専門的なノウハウがある方がより質の高い結果を得られるため、自社にこうしたスキルや人材、時間などのリソースが不足している場合は、セルフ型アンケートツールの活用をおすすめします。
セルフ型アンケートツールを使うと、アンケート画面作成~配信~集計まで全ての業務をWeb上で完結できるため、御社の目的に合った調査をスピーディに実現できます。プロクォリティの調査を容易に実施できるため、調査実施を考えているならセルフ型アンケートツールの活用を検討しましょう。
セルフ型アンケートツールを使うと、アンケート画面作成~配信~集計まで全ての業務をWeb上で完結できるため、御社の目的に合った調査をスピーディに実現できます。プロクォリティの調査を容易に実施できるため、調査実施を考えているならセルフ型アンケートツールの活用を検討しましょう。
-
定量・定性調査がセルフで出来る!サービス内容を確認する

インタビュー調査のポイント
消費者が購買行動に至る背景には、製品を選ぶ欲求や価値観といった「意識」があり、これが「態度」として表れて「行動」に移ります。そのため購買行動の心理変化をインタビュー調査で明らかにするなら、対象者の「意識」「態度」「行動」の3要素を導き出すことが重要です。またインタビュー調査で調査対象者から上手に深層心理を引き出すには、「行動」に関する質問から始めて「態度」の変化を聞き、最終的に「意識」について触れると効率よく進められます。
「行動」「態度」「意識」に関するインタビューを上手に進めるコツを、以下で詳しく解説します。
「行動」「態度」「意識」に関するインタビューを上手に進めるコツを、以下で詳しく解説します。
行動に関するインタビュー調査
最初に、調査対象者も話しやすい「行動」に関する要素を聞いていきます。行動の背景にある態度や意識も見逃さないようにしましょう。
消費行動の背景に気を配る
まず行動に至った背景を浮き彫りにするため、日ごろの消費行動を確認します。普段なにげなく行っている行動は考えても回答しづらいため、日常生活のルーティンや買い物の行動パターンなどを丁寧に聞いていきます。買い物をする曜日やパターン、該当カテゴリーの購入頻度や場所、情報収集や検討プロセスなどを掘り下げながら、背景にある態度や意識を探り出していきます。
購買決定の経緯を考える
購買に至るまでのプロセスも確認しておきましょう。消費者の購買行動プロセスを説明する代表的モデルである「AISASモデル(Attention:注意→ Interest:関心→ Search:検索→ Action:購買→ Share:情報共有)」に沿って、該当製品を知った・興味をもったきっかけや情報源、比較検討したブランド、比較検討時の重視点、最終的に選んだ製品と理由、価格の評価などを聞き出します。購買決定に影響を与える要素を明確にすることで、行動の裏側にある深層意識や価値観に迫ることができます。
態度に関するインタビュー調査
続く「態度」に関するインタビューでは、自社及び競合製品についての評価や満足度、要望などを明らかにしていきます。
自社製品への評価を聞く
まず自社製品の選択理由や満足度、評価、改善要望点などを聞き出します。
満足度を聞く際に、「購入してよかったと思いますか?」「満足したところ、不満に思ったことは何ですか?」と質問すると、全体的な評価を確認できます。また「点数を付けるなら何点ですか?」と尋ねると、高評価でも満点に至らなかったネガティブポイントを引き出すことができます。
満足度を聞く際に、「購入してよかったと思いますか?」「満足したところ、不満に思ったことは何ですか?」と質問すると、全体的な評価を確認できます。また「点数を付けるなら何点ですか?」と尋ねると、高評価でも満点に至らなかったネガティブポイントを引き出すことができます。
競合製品への評価を聞く
自社製品だけではなく、競合製品の評価も聞いておきましょう。
他社製品と比較した良い点・悪い点、他社製品と比較して購入を迷ったポイント、最終的にその製品に決定したポイントなど、本音を引き出す工夫が必要となります。
他社製品と比較した良い点・悪い点、他社製品と比較して購入を迷ったポイント、最終的にその製品に決定したポイントなど、本音を引き出す工夫が必要となります。
スイッチングの可能性を探る
今は自社製品の顧客であっても、将来的に他社製品に乗り換え(スイッチ)する可能性があります。その逆のパターンもあり、スイッチングの可能性を知ることは、自社・競合製品の改善につながる消費者心理を知る良いきっかけとなります。
次回も同じ製品を購入するか、現在関心がある他社製品があるかなどと尋ねることで、継続利用の決め手や他社製品への興味を把握できるでしょう。
次回も同じ製品を購入するか、現在関心がある他社製品があるかなどと尋ねることで、継続利用の決め手や他社製品への興味を把握できるでしょう。
意識に関するインタビュー調査
行動や態度を引き出したのちに、「意識」を聞き出す質問に進みます。消費者の本当の欲求や価値観を明らかにできるインタビュー調査の核心ともいえるでしょう。
参加者の考えを引き出す
本音や深層心理は、本人が普段自覚していない、あるいは明確に言語化したことが少ないため、意識についての言葉を引き出すことは難しい作業です。上手に聞き出すには、参加者の発言を質問に反映する「つぶやき」方式が効果的です。
「手に入ると自慢したくなるということか・・・」「朝は時間がないので使わない、なるほど!」など参加者のコメントを繰り返すことで、相手は続きを話したくなります。こうしたテクニックも使いながらインタビューを進めれば、本音や価値観を引き出せ、新たなインサイトの発掘につながるでしょう。
「手に入ると自慢したくなるということか・・・」「朝は時間がないので使わない、なるほど!」など参加者のコメントを繰り返すことで、相手は続きを話したくなります。こうしたテクニックも使いながらインタビューを進めれば、本音や価値観を引き出せ、新たなインサイトの発掘につながるでしょう。
インタビュー調査の費用相場
インタビュー調査の費用は、調査会社に依頼するか、自社で実施するかによって大きく異なります。
調査会社に依頼する場合の費用内訳
調査会社に依頼する場合、企画設計からリクルーティング、実査、分析、報告までを一括で委託することが可能です。費用は調査の規模や対象者の条件によって変動しますが、一般的な費用の内訳は以下のようになります。
| 項目 | 費用相場の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 調査設計費 | 10万円~30万円 | 調査票やインタビューフローの作成など |
| リクルーティング費 | 1人あたり1万円~3万円 | 対象者の募集・スクリーニング費用 |
| 対象者謝礼 | 1人あたり3千円~2万円 | 拘束時間や条件によって変動 |
| 会場費 | 1時間あたり1万円~3万円 | インタビュー会場のレンタル費用 |
| インタビュアー費 | 5万円~15万円 | 専門のモデレーターに依頼する場合の費用 |
| 分析・レポート費 | 20万円~50万円 | 発言録作成、分析、報告書作成など |
自社で実施する場合の費用
自社でインタビュー調査を実施する場合、調査設計費やインタビュアー費などを抑えることができます。主な費用は、対象者のリクルーティング費用と謝礼になります。コストを抑えられる反面、調査設計のノウハウやリクルーティングの工数、分析スキルなどが社内で必要になります。
まとめ
インタビュー調査は、定量調査では得られない消費者の深層心理や行動の背景、インサイトなどを把握できるため、購買プロセスやカスタマージャーニーの理解、仮説の構築などに適しています。インタビュー調査にはグループインタビューとデプスインタビューがあるため、調査目的に応じて適切な手法を選ぶとよいでしょう。
インタビュー調査を実施するには調査設計から対象者のリクルーティング、インタビューフローの作成、結果分析・レポート作成など、専門的なノウハウやモデレーターのスキルが必要となります。自社で対応できない場合は調査会社に依頼するかセルフ型アンケートツールを活用する方が、質の高い結果を得られるでしょう。
インタビュー調査を実施するには調査設計から対象者のリクルーティング、インタビューフローの作成、結果分析・レポート作成など、専門的なノウハウやモデレーターのスキルが必要となります。自社で対応できない場合は調査会社に依頼するかセルフ型アンケートツールを活用する方が、質の高い結果を得られるでしょう。
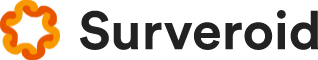 オンラインインタビューでスピーディーに意思決定!
オンラインインタビューでスピーディーに意思決定!
-
サービス概要・事例がわかる資料ダウンロード
-
ターゲットの声がすぐに聴ける登録してみる(無料)
127 件