目次
インタビューを成功させる鍵は、事前の「質問準備」にあります。
良い質問は、相手の深い考えや本音を引き出し、読者や聞き手にとって価値のある情報をもたらします。
しかし、いざ質問を作成しようとすると、「何から始めればいいのか」「どんな質問をすれば良いのか」と悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
この記事では、取材・面談・モニター調査など、目的の異なるインタビューすべてに共通する「質問設計の考え方」を解説します。
基本的な手順から、相手の心を開くコツ、そして様々なシーンでそのまま使える具体的な質問例まで、網羅的に紹介します。
良い質問は、相手の深い考えや本音を引き出し、読者や聞き手にとって価値のある情報をもたらします。
しかし、いざ質問を作成しようとすると、「何から始めればいいのか」「どんな質問をすれば良いのか」と悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。
この記事では、取材・面談・モニター調査など、目的の異なるインタビューすべてに共通する「質問設計の考え方」を解説します。
基本的な手順から、相手の心を開くコツ、そして様々なシーンでそのまま使える具体的な質問例まで、網羅的に紹介します。
インタビューにおける質問の事前準備の大切さ
そもそも、なぜインタビューにおいて質問を事前にしっかりと準備する必要があるのでしょうか。背景には、主に2つの側面があります。質の高いインタビューを実現するために、まずは質問の役割を理解することから始めましょう。
【関連記事】インタビュー調査とは?種類やメリット・デメリット、手順を事例付きで解説
【関連記事】インタビュー調査とは?種類やメリット・デメリット、手順を事例付きで解説
対象者との信頼関係を築くため
良いインタビューの第一歩は、対象者との信頼関係づくりです。
取材や採用面接などでは、事前に相手の活動内容や発言をリサーチしておくことで、「自分に関心を持ってくれている」と感じてもらえます。丁寧な準備は誠実さの証となり、相手の心を開くきっかけになります。
一方、モニター調査のように対象者が匿名の場合は、事前に個人を調べることはできません。その場合は、当日の進め方や質問の仕方そのものが信頼構築の手段になります。
「どんな回答も正解・不正解はありません」「率直なご意見を伺いたいです」といった前置きをし、安心して話せる空気を作りましょう。
いずれの場合も共通するのは、「相手への敬意」と「安心感のある対話姿勢」です。準備と場づくりの両面から、信頼関係を築くことが良質なインタビューの前提になります。
取材や採用面接などでは、事前に相手の活動内容や発言をリサーチしておくことで、「自分に関心を持ってくれている」と感じてもらえます。丁寧な準備は誠実さの証となり、相手の心を開くきっかけになります。
一方、モニター調査のように対象者が匿名の場合は、事前に個人を調べることはできません。その場合は、当日の進め方や質問の仕方そのものが信頼構築の手段になります。
「どんな回答も正解・不正解はありません」「率直なご意見を伺いたいです」といった前置きをし、安心して話せる空気を作りましょう。
いずれの場合も共通するのは、「相手への敬意」と「安心感のある対話姿勢」です。準備と場づくりの両面から、信頼関係を築くことが良質なインタビューの前提になります。
記事や面談の質を高めるため
インタビューの目的やテーマが明確であれば、それに沿った質問を準備することで、話が脱線することを防ぎ、一貫性のある内容を引き出せます。行き当たりばったりの質問では、本来聞きたかった情報を聞き漏らしたり、話が散漫になったりするリスクが高まります。事前に質問の構成を練っておくことで、インタビュー全体の質を担保し、最終的なアウトプット(記事、採用判断、顧客理解など)の精度を高めることができるのです。

インタビューの質問を作成する4つのステップ
質の高いインタビュー質問は、思いつきで生まれるものではありません。明確な目的意識に基づいた、体系的なプロセスを経て作成されます。ここでは、誰でも実践できる、インタビュー質問作成の4つの基本的なステップを紹介します。
【関連記事】アンケートの作り方|実施方法や回答率アップのコツも解説
【関連記事】アンケートの作り方|実施方法や回答率アップのコツも解説
ステップ1:インタビューの目的を明確にする
最初に、「何のためにインタビューを行うのか」という目的を明確に設定します。例えば、採用面接であれば「候補者の価値観と自社のカルチャーのマッチ度を見極める」、顧客インタビューであれば「自社サービスの具体的な導入効果と改善点を把握する」といった具合です。全ての土台となり、どのような情報を引き出すべきか、質問の方向性を決定づけます。
ステップ2:対象者について徹底的にリサーチする
インタビュー前のリサーチは、質問の質を大きく左右します。
取材・広報・採用インタビューでは、、対象者を深く理解するほど、質問の精度と独自性が高まります。
公式サイト・SNS・過去の登壇・記事などから、相手の経歴・考え方・発言傾向を調べ、質問の切り口を工夫しましょう。既出情報を避けることで、独自性の高いインタビューになります。
また、事前リサーチが行き届いていると、相手に「自分のことをよく調べてくれている」という安心感を与え、信頼関係の構築にもつながります。
一方、モニター調査の場合は、個人を特定してリサーチすることができないケースが多いです。、「誰が」ではなく「どんな属性・行動特性の人から何を引き出したいか」を明確にすることが重要です。
年齢・性別・購買頻度などのスクリーナー条件を整理し、既存アンケートやレビューなどの定量データを読み解いて仮説を立てることで、「どの層から何を聞き出すべきか」を明確にします。
つまり、取材では「人を知るためのリサーチ」、モニター調査では「集団を理解するためのリサーチ」。
どちらも“聞く準備”として欠かせないプロセスです。
取材・広報・採用インタビューでは、、対象者を深く理解するほど、質問の精度と独自性が高まります。
公式サイト・SNS・過去の登壇・記事などから、相手の経歴・考え方・発言傾向を調べ、質問の切り口を工夫しましょう。既出情報を避けることで、独自性の高いインタビューになります。
また、事前リサーチが行き届いていると、相手に「自分のことをよく調べてくれている」という安心感を与え、信頼関係の構築にもつながります。
一方、モニター調査の場合は、個人を特定してリサーチすることができないケースが多いです。、「誰が」ではなく「どんな属性・行動特性の人から何を引き出したいか」を明確にすることが重要です。
年齢・性別・購買頻度などのスクリーナー条件を整理し、既存アンケートやレビューなどの定量データを読み解いて仮説を立てることで、「どの層から何を聞き出すべきか」を明確にします。
つまり、取材では「人を知るためのリサーチ」、モニター調査では「集団を理解するためのリサーチ」。
どちらも“聞く準備”として欠かせないプロセスです。
ステップ3:質問項目を洗い出して整理する
目的の明確化とリサーチが終わったら、具体的な質問項目を洗い出していきます。
質問作りでは、まず目的に沿って思いつく質問をすべて書き出し、優先順位をつけましょう。
取材や採用インタビューでは、テーマごとに整理して「絶対に聞きたい質問」と「時間があれば聞きたい質問」を分けることで、構成に一貫性を持たせられます。
一方、モニター調査インタビューでは、あらかじめすべてを固定するよりも、柔軟に深掘りできる構成にするのがポイントです。
たとえば、「もう少し詳しく教えてください」「それはどうしてそう思われたのですか?」などのプロービング質問を事前に用意し、参加者の発言に合わせて掘り下げていく設計を意識しましょう。
つまり、取材は“構造を組み立てる準備”、モニター調査は“自由に深掘れる余白づくり”。
目的に応じて質問設計の精度と柔軟性のバランスを取ることが重要です。
質問作りでは、まず目的に沿って思いつく質問をすべて書き出し、優先順位をつけましょう。
取材や採用インタビューでは、テーマごとに整理して「絶対に聞きたい質問」と「時間があれば聞きたい質問」を分けることで、構成に一貫性を持たせられます。
一方、モニター調査インタビューでは、あらかじめすべてを固定するよりも、柔軟に深掘りできる構成にするのがポイントです。
たとえば、「もう少し詳しく教えてください」「それはどうしてそう思われたのですか?」などのプロービング質問を事前に用意し、参加者の発言に合わせて掘り下げていく設計を意識しましょう。
つまり、取材は“構造を組み立てる準備”、モニター調査は“自由に深掘れる余白づくり”。
目的に応じて質問設計の精度と柔軟性のバランスを取ることが重要です。
ステップ4:事前に質問リストを共有する
質問リストの共有方法も、インタビューの種類によって異なります。
取材や採用面接の場合、質問を事前共有しておくと相手が安心して準備でき、回答の精度も上がります。特に数字やデータを伴う質問は、事前に伝えておくとスムーズです。
ただし、すべてを共有すると形式的な回答になりがちなので、「主要テーマのみ」や「質問の方向性だけ」を伝えるのが理想です。
一方、モニター調査では、回答を誘導しないように、詳細な質問の事前共有は避けます。
その代わり、参加者の不安を減らすために、以下のような“概要レベル”の案内を伝えます。
・インタビューの目的とテーマ範囲
・所要時間・進行方法・録音録画の有無
・想定する話題例(1〜2項目)
・準備物(例:使用中の商品やアプリなど)
つまり、取材では「考えを整理してもらうための共有」、モニター調査では「自然な発言を引き出すための最小限共有」と捉えましょう。
取材や採用面接の場合、質問を事前共有しておくと相手が安心して準備でき、回答の精度も上がります。特に数字やデータを伴う質問は、事前に伝えておくとスムーズです。
ただし、すべてを共有すると形式的な回答になりがちなので、「主要テーマのみ」や「質問の方向性だけ」を伝えるのが理想です。
一方、モニター調査では、回答を誘導しないように、詳細な質問の事前共有は避けます。
その代わり、参加者の不安を減らすために、以下のような“概要レベル”の案内を伝えます。
・インタビューの目的とテーマ範囲
・所要時間・進行方法・録音録画の有無
・想定する話題例(1〜2項目)
・準備物(例:使用中の商品やアプリなど)
つまり、取材では「考えを整理してもらうための共有」、モニター調査では「自然な発言を引き出すための最小限共有」と捉えましょう。

質の高い質問を作るための3つのコツ
効果的な質問を作成するには、いくつかのテクニックがあります。ここでは、相手からより豊かな回答を引き出すための3つの重要なコツを紹介します。意識することで、インタビューの質を格段に向上させることができます。
その前提として大切なのが、「教えてください」ではなく「聞かせてください」という姿勢です。
調査でも取材でも、インタビュアーが答えを導くのではなく、「このテーマについて、あなたの体験や考えをぜひ聞かせてください」と伝えることで、相手は安心して自分の言葉で語ることができます。
この“聞かせてください”のスタンスこそが、相手のリアルな声を引き出し、真の理解やインサイトにつながります。
その前提として大切なのが、「教えてください」ではなく「聞かせてください」という姿勢です。
調査でも取材でも、インタビュアーが答えを導くのではなく、「このテーマについて、あなたの体験や考えをぜひ聞かせてください」と伝えることで、相手は安心して自分の言葉で語ることができます。
この“聞かせてください”のスタンスこそが、相手のリアルな声を引き出し、真の理解やインサイトにつながります。
コツ1:「オープンクエスチョン」と「クローズドクエスチョン」を使い分ける
質問には大きく分けて2つの種類があります。それぞれの特徴を理解し、状況に応じて使い分けることが、会話を弾ませる鍵となります。
| 質問の種類 | 特徴 | メリット | デメリット | 活用シーン |
|---|---|---|---|---|
| オープンクエスチョン |
「はい/いいえ」で答えられず、相手が自由に回答できる質問。 「なぜ」「どのように」などを使う。 |
相手の考えや感情、背景にあるストーリーなどを深く引き出せる。 話が広がりやすい。 |
回答に時間がかかることがある。 話が脱線する可能性がある。 |
インタビューの中盤以降、特定のテーマを深掘りしたい時。 |
| クローズドクエスチョン | 「はい/いいえ」や、一言で答えられる質問。 |
事実確認や意思確認が簡潔にできる。 会話のテンポを作りやすい。 |
話が広がりにくい。 多用すると尋問のようになってしまう。 |
インタビューの冒頭、アイスブレイクや事実確認の時。 |
インタビューの序盤では、答えやすいクローズドクエスチョンで場の空気を和ませ、対象者の話が乗ってきたところでオープンクエスチョンを投げかけて深掘りしていくのが効果的な使い方です。
コツ2:「6W2H」を意識して質問を具体化する
質問が抽象的すぎると、相手は何をどう答えればいいか迷ってしまいます。質問を作成する際は、「6W2H」のフレームワークを意識することで、具体的で分かりやすい質問になります。
・When(いつ):その出来事が起こったのはいつですか?
・Where(どこで):それはどこでの話ですか?
・Who(誰が):誰が関わっていましたか?
・Whom(誰に):誰に向けたものですか?
・What(何を):最も重要だったことは何ですか?
・Why(なぜ):なぜそうしようと思ったのですか?
・How(どのように):どのようにしてそれを乗り越えましたか?
・HowMuch/Many(いくら/どのくらい):どのくらいの期間がかかりましたか?
これらの要素を質問に組み込むことで、より詳細で具体的なエピソードを引き出すことができます。
・When(いつ):その出来事が起こったのはいつですか?
・Where(どこで):それはどこでの話ですか?
・Who(誰が):誰が関わっていましたか?
・Whom(誰に):誰に向けたものですか?
・What(何を):最も重要だったことは何ですか?
・Why(なぜ):なぜそうしようと思ったのですか?
・How(どのように):どのようにしてそれを乗り越えましたか?
・HowMuch/Many(いくら/どのくらい):どのくらいの期間がかかりましたか?
これらの要素を質問に組み込むことで、より詳細で具体的なエピソードを引き出すことができます。
コツ3:時系列(過去・現在・未来)を意識して話の流れを作る
話を構成するうえで、時系列を意識すると流れが自然になります。
取材インタビューでは、「現在」→「過去」→「未来」の順で話すと、相手のキャリアや考えの背景が分かりやすく、読者にもストーリーとして伝わりやすくなります。
一方、モニター調査では、購買・利用のプロセスに沿った「過去(検討前)」→「現在(利用中)」→「未来(期待・要望)」という流れを意識することで、行動と心理の変化を明確に整理できます。
どちらの場合も、時系列を軸にすることで「経験の流れ」を自然に引き出すことができ、回答の背景理解につながります。
取材インタビューでは、「現在」→「過去」→「未来」の順で話すと、相手のキャリアや考えの背景が分かりやすく、読者にもストーリーとして伝わりやすくなります。
一方、モニター調査では、購買・利用のプロセスに沿った「過去(検討前)」→「現在(利用中)」→「未来(期待・要望)」という流れを意識することで、行動と心理の変化を明確に整理できます。
どちらの場合も、時系列を軸にすることで「経験の流れ」を自然に引き出すことができ、回答の背景理解につながります。
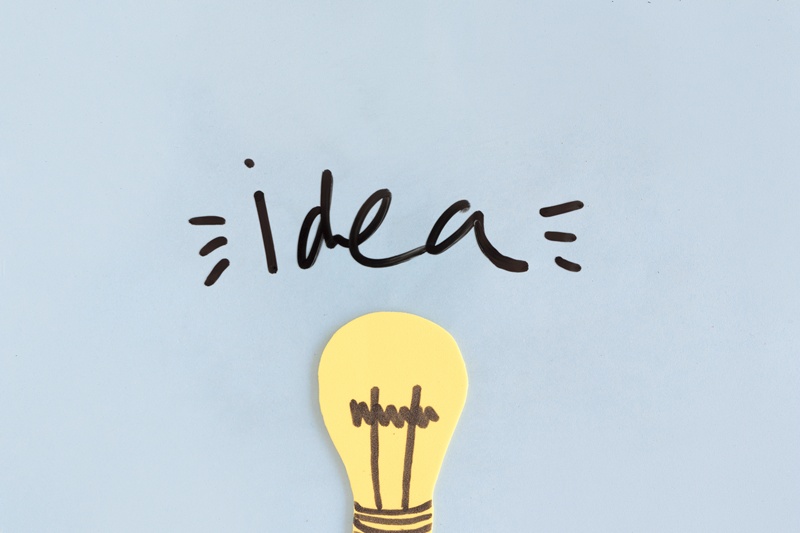
【目的別】すぐに使えるインタビュー質問例
ここからは、様々なビジネスシーンでそのまま使えるインタビューの質問例を目的別にご紹介します。質問作りの時間を短縮し、より質の高いインタビューを実現するために、ぜひ参考にしてください。
社員インタビュー向けの質問例
| 項目 | 質問内容 |
|---|---|
| アイスブレイク・現在について |
・ 本日はお時間をいただきありがとうございます。まずは自己紹介をお願いできますでしょうか? ・ 現在の所属部署と、具体的な仕事内容を教えてください。 ・ 一日の典型的な仕事の流れを教えていただけますか? ・ 今の仕事で一番「楽しい」「やりがいがある」と感じるのはどんな時ですか? |
| 過去・経緯について |
・ ○○(自社)に入社する前は、どのようなお仕事をされていたのですか? ・ 転職を考えたきっかけや、当社に興味を持った理由は何でしたか? ・ 入社の決め手になったことがあれば教えてください。 ・ 入社してから最も大変だったことや、それをどう乗り越えたかというエピソードはありますか? |
| 人柄・価値観について |
・ 仕事をする上で、最も大切にしている価値観は何ですか? ・ 休日はどのように過ごされることが多いですか? ・ ご自身の性格を自己分析すると、どのようなタイプだと思いますか? ・ 尊敬する人や、目標としている人はいますか? |
| 未来・キャリアについて |
・ 今後、この会社で挑戦してみたいことや、実現したい目標はありますか? ・ ご自身のキャリアプランについて、どのように考えていますか? ・ 5年後、10年後はどのようになっていたいですか? |
| 会社・組織について |
・ 所属しているチームや部署はどのような雰囲気ですか? ・ ○○(自社)の「ここが好きだ」という点を教えてください。 ・ この会社で働くことで、どのようなスキルが身につくと思いますか? ・ 未来の仲間になるかもしれない求職者の方へ、メッセージをお願いします。 |
自社製品の導入事例インタビュー向けの質問例
自社製品やサービスの導入事例インタビューは、見込み顧客に対して具体的な成功イメージを提示し、導入を後押しすることを目的としています。利用者のリアルな声を通して、製品の価値を証明するための質問を準備しましょう。特に、導入前後の変化を具体的に聞き出すことがポイントです。
| 項目 | 質問内容 |
|---|---|
| 導入前の状況に関する質問 |
・ どのような業務課題を抱えていらっしゃいましたか? ・ その課題によって、具体的にどのような問題が発生していましたか? ・ 当社の製品を知っていただいたきっかけは何でしたか? ・ 製品導入を検討するにあたり、他に比較されたサービスはありましたか? |
| 導入の決め手に関する質問 |
・ 数あるサービスの中から、最終的に当社の製品を選んでいただいた決め手は何だったのでしょうか? ・ 導入前に、何か不安や懸念点はありましたか? ・ 導入プロセスはスムーズに進みましたか? |
| 導入後の効果に関する質問 |
・ 製品を導入したことで、課題はどのように解決されましたか? ・ 具体的な数値で示せるような、定量的な変化はありましたか?(例:作業時間が〇%削減、コストが〇円削減など) ・ 数値以外で感じた、定性的な変化やメリットがあれば教えてください。(例:社員のモチベーションが上がった、コミュニケーションが円滑になったなど) ・ 特に便利だと感じている機能や、お気に入りのポイントはどこですか? |
| 未来に関する質問 |
・ 今後、当社の製品をどのように活用していきたいですか? ・ 製品やサポートに対して、何か期待することや要望はありますか? ・ 同じような課題を抱えている他の企業様へ、アドバイスがあればお願いします。 |
採用面接向けの質問例
採用面接は、候補者のスキルや経験、人柄が自社の求める人物像とマッチしているかを見極める重要な場です。経歴書だけでは分からない候補者の本質を引き出すために、多角的な質問を投げかける必要があります。「オープンクエスチョン(自由に回答できる質問)」と「クローズドクエスチョン(はい/いいえで答えられる質問)」を効果的に使い分けることで、対話を深めていきましょう。
| 項目 | 質問内容 |
|---|---|
| 経験・スキルに関する質問 |
・ これまでのご経歴について、自己紹介をお願いします。 ・ 前職(現職)で最も大きな成果を上げたと考えるプロジェクトについて、具体的に教えてください。その中であなたの役割は何でしたか? ・ 逆に、仕事で経験した大きな失敗と、そこから学んだことは何ですか? ・ 当社の〇〇という業務で、あなたのどのような経験やスキルが活かせるとお考えですか? |
| 志望動機に関する質問 |
・ なぜ、この業界や職種に興味を持たれたのでしょうか? ・ 数ある企業の中で、なぜ当社を志望されたのですか? ・ 当社の事業内容について、どのような点に魅力を感じますか? |
| 価値観・人柄に関する質問 |
・ 仕事において、チームで成果を出すために最も重要だと思うことは何ですか? ・ 周囲の方からは、どのような人だと言われることが多いですか? ・ ストレスを感じた時、どのように解消していますか? |
| キャリアプランに関する質問 |
・ 入社後、まずはどのような仕事に取り組みたいですか? ・ 5年後、どのようなスキルを身につけ、どのようなポジションで活躍していたいですか? ・ あなたのキャリアにおける最終的な目標は何ですか? |
市場調査(モニター)インタビュー向けの質問例
市場調査インタビューの目的は、ターゲットとなる顧客層のニーズや課題、行動、価値観を深く理解することです。アンケートでは得られないような、定性的な情報を引き出すことを意識しましょう。回答を誘導せず、対象者の自然な意見や本音を聞き出すための質問が求められます。
| 項目 | 質問内容 |
|---|---|
| 対象者の属性・ライフスタイルに関する質問 |
・ 普段、平日はどのようなスケジュールで過ごされることが多いですか? ・ 休日の過ごし方について教えてください。 ・ 情報収集をする際、どのようなメディア(Webサイト、SNS、雑誌など)を参考にしますか? |
| 製品・サービスカテゴリに関する質問 |
・ 〇〇(調査対象のカテゴリ)について、普段どのくらいの頻度で利用・購入されますか? ・ 〇〇を選ぶ際に、最も重視するポイントは何ですか?(例:価格、品質、ブランドなど) ・ 〇〇に関して、現在何か不便に感じていることや、「もっとこうだったら良いのに」と思う点はありますか? |
| 課題・ニーズに関する質問 |
・ 最近、日常生活や仕事の中で「困ったな」と感じたことは何ですか? ・ その課題を解決するために、何か試したことはありますか? ・ もし、〇〇(課題を解決する新しい製品・サービスのコンセプト)があったとしたら、利用してみたいと思いますか? ・ その製品・サービスに、いくらまでなら支払えると感じますか? |
| 競合・既存サービスに関する質問 |
・ 現在、〇〇(競合サービス名)を利用されていますか?利用されている場合、その理由や満足している点を教えてください。 ・ 逆に、〇〇(競合サービス名)の不満な点や改善してほしい点はありますか? |
-
潜在層へのインタビューに使える!サーベロイドについて確認する
インタビュー当日に質問する際のポイント
入念な準備をしても、当日の振る舞い次第でインタビューの成果は大きく変わります。対象者がリラックスして本音を話せるような雰囲気作りと、柔軟な対応が求められます。ここでは、インタビュー当日に心がけたい3つのポイントを解説します。
ポイント1:アイスブレイクで緊張をほぐす
インタビューの冒頭では、本題に入る前に関係のない雑談、いわゆる「アイスブレイク」を挟むことが非常に重要です。
取材なら軽い雑談から、調査なら「今日はこのテーマについて、皆さんの率直な意見を聞かせてください」と伝えるのが効果的です。話しやすい雰囲気を作ることで、相手はリラックスし、その後の質問にも心を開いて答えやすくなります。
取材なら軽い雑談から、調査なら「今日はこのテーマについて、皆さんの率直な意見を聞かせてください」と伝えるのが効果的です。話しやすい雰囲気を作ることで、相手はリラックスし、その後の質問にも心を開いて答えやすくなります。
ポイント2:尋問ではなく「会話」を心がける
質問を“投げる”のではなく、相手の言葉を“受け止める”姿勢を意識しましょう。
相手の回答に真摯に耳を傾け、共感やうなずきを交えながら、「それはどういうきっかけでしたか?」と自然に掘り下げていくことで、本音や具体的なエピソードを引き出せます。
インタビュアーの関心よりも、対象者の経験を中心に置く姿勢が、自然で豊かなインサイトを引き出します。
また、調査では特に、誘導的にならないように気をつけましょう。
相手の回答に真摯に耳を傾け、共感やうなずきを交えながら、「それはどういうきっかけでしたか?」と自然に掘り下げていくことで、本音や具体的なエピソードを引き出せます。
インタビュアーの関心よりも、対象者の経験を中心に置く姿勢が、自然で豊かなインサイトを引き出します。
また、調査では特に、誘導的にならないように気をつけましょう。
ポイント3:準備した質問に固執しすぎない
事前に質問リストを準備しておくことももちろん重要ですが、会話の流れの中で思わぬ発言が出たら、柔軟に質問を変える勇気も必要です。流れを無視して自分の聞きたいことだけを聞こうとすると、せっかくのチャンスを逃してしまいます。
取材なら「その背景をもう少し伺えますか?」、調査なら「そのときどんな気持ちでしたか?」など、流れを活かした深掘りを行いましょう。
良いインタビューは、“流れを作る”より“流れに乗る”ことで生まれます。準備した質問はあくまで「道しるべ」と考え、相手の話の流れに乗りながら、臨機応変に質問を追加したり、順番を変えたりする柔軟性を持ちましょう。
取材なら「その背景をもう少し伺えますか?」、調査なら「そのときどんな気持ちでしたか?」など、流れを活かした深掘りを行いましょう。
良いインタビューは、“流れを作る”より“流れに乗る”ことで生まれます。準備した質問はあくまで「道しるべ」と考え、相手の話の流れに乗りながら、臨機応変に質問を追加したり、順番を変えたりする柔軟性を持ちましょう。
まとめ
取材インタビューもモニター調査インタビューも、目的や進め方は異なりますが、本質的には「相手を理解し、信頼関係を築き、本音を引き出す」という点で共通しています。
取材では、相手の想いやストーリーを伝えるための構成力。
モニター調査では、生活者のリアルな声を自然に引き出すための質問設計力とモデレーション力。
いずれの場面でも、最も重要なのはテクニックではなく、「相手の言葉を本気で聴きたい」という姿勢です。
準備と誠意をもって臨むことで、インタビューは必ず“データ以上の価値”をもたらします。
取材では、相手の想いやストーリーを伝えるための構成力。
モニター調査では、生活者のリアルな声を自然に引き出すための質問設計力とモデレーション力。
いずれの場面でも、最も重要なのはテクニックではなく、「相手の言葉を本気で聴きたい」という姿勢です。
準備と誠意をもって臨むことで、インタビューは必ず“データ以上の価値”をもたらします。
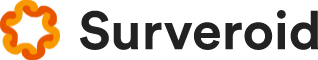 まずはセルフ型リサーチを一度体験してみませんか?
まずはセルフ型リサーチを一度体験してみませんか?
-
サービス概要・事例がわかる資料をダウンロードする
-
登録は無料・最短1分で完了します登録してみる(無料)
58 件




