目次
新商品やサービスを市場に出す前に、「本当に受け入れられるのか?」を確かめるのが「受容性調査」です。ユーザーの反応やニーズとのズレを事前に把握できるため、開発の方向性を見極める重要なプロセスとして活用されています。
この記事では、「受容性調査とは?」の基本から、調査の種類・手法・設問例・費用感までをわかりやすく解説します。調査を検討している方はもちろん、初めて知る方にも役立つ内容です。
この記事では、「受容性調査とは?」の基本から、調査の種類・手法・設問例・費用感までをわかりやすく解説します。調査を検討している方はもちろん、初めて知る方にも役立つ内容です。

受容性調査とは?
受容性調査とは、商品やサービスのコンセプトがターゲットとなる生活者にどの程度受け入れられるか(=受容性)を測定する調査です。
この調査を行うことで、以下のような視点から生活者のリアルな受け止め方を数値化・比較できます。
・関心や共感を持たれるか
・新しさや魅力を感じてもらえるか
・具体的に購入したいと思われるか
新商品を世に出す前にこうした反応を可視化しておくことで、リリース後の失敗リスクを未然に防ぐことができます。また、複数のコンセプト案から最も高く評価されるものを選定するなど、開発判断のエビデンスとしても活用されます。
特に最近では、セルフ型アンケートツールを使ったスピーディーな実施も増えており、初期検証から改善までの意思決定がしやすくなっています。
この調査を行うことで、以下のような視点から生活者のリアルな受け止め方を数値化・比較できます。
・関心や共感を持たれるか
・新しさや魅力を感じてもらえるか
・具体的に購入したいと思われるか
新商品を世に出す前にこうした反応を可視化しておくことで、リリース後の失敗リスクを未然に防ぐことができます。また、複数のコンセプト案から最も高く評価されるものを選定するなど、開発判断のエビデンスとしても活用されます。
特に最近では、セルフ型アンケートツールを使ったスピーディーな実施も増えており、初期検証から改善までの意思決定がしやすくなっています。
商品・サービスの市場受容性を測る調査
商品やサービスに込めた意図がターゲットにどのように受け止められるかを定量的に確認できます。「興味を持たれるか」「理解されやすいか」「使ってみたいと思われるか」といった反応を複数の指標で評価することで、その商品が市場で受け入れられる可能性=受容性を明確に把握できます。
調査は一般的に、評価項目(例:新奇性、共感性、信頼性、購入意向など)ごとにスコアを収集し、複数の案を比較・選定したり、改善点を発見したりするために活用されます。
調査は一般的に、評価項目(例:新奇性、共感性、信頼性、購入意向など)ごとにスコアを収集し、複数の案を比較・選定したり、改善点を発見したりするために活用されます。
新商品開発やブランド刷新の初期段階で活用
新商品の企画段階やブランドのリニューアル初期に特に有効です。開発やマーケティングの意思決定を、担当者の勘や主観だけに頼るのではなく、生活者の声をもとに客観的に判断できるようになります。
たとえば、複数のコンセプト案を同時に提示し、それぞれの反応を比較すれば、「どの案がもっとも魅力的に映るか」「どこを改善すればよいか」が一目でわかります。
つまり、“市場の反応を先に見てから進める”ことで、無駄な修正や方向転換のコストを減らすことができるのです。
たとえば、複数のコンセプト案を同時に提示し、それぞれの反応を比較すれば、「どの案がもっとも魅力的に映るか」「どこを改善すればよいか」が一目でわかります。
つまり、“市場の反応を先に見てから進める”ことで、無駄な修正や方向転換のコストを減らすことができるのです。
調査結果がビジネスにもたらすインパクト
受容性調査の結果は、単なるアンケート結果ではなく、ビジネス戦略そのものに影響を与える材料となります。
たとえば、
・失敗リスクの最小化:市場に響かないコンセプトを早期に発見できる
・自信ある判断:定量データに基づき、開発や広告表現の方向性を明確に決定
・社内・取引先との合意形成:主観ではなく“数字”で語れることで説得力が高まる
このように、調査は開発・マーケティング・営業など複数部門にまたがる意思決定の後押しとなるため、単なる「調査」以上の価値を発揮します。
たとえば、
・失敗リスクの最小化:市場に響かないコンセプトを早期に発見できる
・自信ある判断:定量データに基づき、開発や広告表現の方向性を明確に決定
・社内・取引先との合意形成:主観ではなく“数字”で語れることで説得力が高まる
このように、調査は開発・マーケティング・営業など複数部門にまたがる意思決定の後押しとなるため、単なる「調査」以上の価値を発揮します。
受容性調査の種類
受容性調査にはいくつかの種類があり、調査の目的やフェーズに応じて適切な手法を選ぶことが重要です。特に代表的なのが、「コンセプト受容性調査」と「価格受容性調査」です。それぞれが着目する“受け入れられる対象”が異なります。
コンセプト受容性調査とは
コンセプト受容性調査は、商品やサービスの提供価値(=コンセプト)が消費者にどの程度受け入れられるかを測る調査です。
パッケージや商品名、機能・特長などをまとめた「コンセプト案」を提示し、その魅力度、共感度、新奇性、理解度、購入意向などを評価してもらいます。
コンセプトとは、「この商品は誰に、どんな価値を届けるものなのか」という提供者側の意図やベネフィットを言語化したものです。商品開発やリブランディング、マーケティング施策の設計において、コンセプトは方向性を定める“軸”になります。
パッケージや商品名、機能・特長などをまとめた「コンセプト案」を提示し、その魅力度、共感度、新奇性、理解度、購入意向などを評価してもらいます。
コンセプトとは、「この商品は誰に、どんな価値を届けるものなのか」という提供者側の意図やベネフィットを言語化したものです。商品開発やリブランディング、マーケティング施策の設計において、コンセプトは方向性を定める“軸”になります。
価格受容性調査(PSM分析など)とは
価格受容性調査は、消費者が提示された価格に対してどのように感じるか、「高い」「安い」「妥当」といった印象を測定する調査です。価格が高すぎれば敬遠され、安すぎれば品質に疑問を持たれる可能性があるため、適正価格帯を見極めることが重要です。
代表的な分析手法には以下があります。
・PSM分析(Price Sensitivity Meter)
→ 「高すぎる/安すぎる」などの心理的境界線を使って価格帯を算出
・CVM分析(Conjoint Value Measurement)
→ 属性と価格の組み合わせに基づいて、価格に対する価値の感じ方を比較
これらは、市場投入時の価格戦略設計や価格改定時の判断材料として活用されます。
代表的な分析手法には以下があります。
・PSM分析(Price Sensitivity Meter)
→ 「高すぎる/安すぎる」などの心理的境界線を使って価格帯を算出
・CVM分析(Conjoint Value Measurement)
→ 属性と価格の組み合わせに基づいて、価格に対する価値の感じ方を比較
これらは、市場投入時の価格戦略設計や価格改定時の判断材料として活用されます。
価格調査とは?調査方法とPSM分析・CVM分析について解説

価格は消費者に影響を与える1つの要素であり、ライバル企業よりも高額な設定であれば競争に負けてしまい、利益を損なうこともるため、自社製品や提供するサービスの価格が、適正なのかを調査することが大事です。
受容性調査のメリットとは
受容性調査は、商品やサービスの開発段階における「意思決定の質」を高める重要な手段です。ここでは、主に商品開発・ターゲティング・社内外の調整といった3つの観点から、具体的なメリットを紹介します。
商品開発のリスクを事前に軽減
新商品や新サービスの開発は、多くのコストやリソースがかかる一方で、市場に受け入れられないリスクも伴います。受容性調査を実施すれば、コンセプトの魅力度や関心度を数値化でき、市場投入前に課題や改善点を発見できます。
これにより、
・方向性が間違っていないかの確認ができる
・市場に出す前の軌道修正が可能になる
・開発/広告/販売の一貫性が持てる
といった効果が期待でき、結果として開発投資の無駄を最小限に抑えることができます。
これにより、
・方向性が間違っていないかの確認ができる
・市場に出す前の軌道修正が可能になる
・開発/広告/販売の一貫性が持てる
といった効果が期待でき、結果として開発投資の無駄を最小限に抑えることができます。
ターゲット層とのズレを可視化できる
「良い商品だと思っていたのに、売れなかった」という事例の多くは、ユーザー理解の誤差=ターゲットとのズレに原因があります。受容性調査では、実際のターゲット層から評価を集めるため、自社の想定と市場のリアルな反応とのギャップが明確になります。
・想定ターゲットと実際の高評価層が異なる
・魅力だと思っていた訴求点が響いていない
・意図しない層に評価されている
こうしたズレを早期に認識できれば、訴求メッセージの調整やプロモーション戦略の最適化に活かすことができます。
・想定ターゲットと実際の高評価層が異なる
・魅力だと思っていた訴求点が響いていない
・意図しない層に評価されている
こうしたズレを早期に認識できれば、訴求メッセージの調整やプロモーション戦略の最適化に活かすことができます。
社内外での意思決定を円滑にする材料になる
新商品の企画や改善提案を進める中で、関係者との意見の食い違いや判断の停滞に直面することは少なくありません。受容性調査の結果は、こうした場面で客観的な根拠として非常に有効です。
・消費者視点のデータをベースに議論できる
・感覚ではなく「数字」で説明できる
・上層部や取引先への提案にも説得力が生まれる
調査結果があることで、関係者間の共通認識が生まれ、合意形成がスムーズになるため、プロジェクト全体のスピードと精度が向上します。
・消費者視点のデータをベースに議論できる
・感覚ではなく「数字」で説明できる
・上層部や取引先への提案にも説得力が生まれる
調査結果があることで、関係者間の共通認識が生まれ、合意形成がスムーズになるため、プロジェクト全体のスピードと精度が向上します。
-
コンセプト調査の調査実績多数!サービス内容を確認する
-
初期費用や月額費一切なし!サーベロイドに登録してみる

受容性調査の手法と対象者の設計
ここでは、受容性調査を実施する際に重要となる調査手法の選び方と、調査対象者(パネル)の設定ポイントについて解説します。目的に応じて適切な手法と対象者を設計することで、より信頼性の高い結果が得られます。
受容性調査の代表的な実施方法
受容性調査の調査手法としては、大きく分けて「定量調査」と「定性調査」の2種類があり、数量的に傾向を知る「インターネット定量調査」、心理・行動を深掘りできる「グループインタビュー」、ローンチ時に近い消費者の反応を確認できる「CLT・HUT」などが挙げられます。
インターネット定量調査(Webアンケート)
・回答者の傾向や評価を数値で把握するのに適した手法です。
・比較的短期間・低コストで実施可能で、ニッチなターゲットにもアプローチしやすいのが特長です。
・複数のコンセプト案をスコアで比較したい場合や、ターゲットごとの傾向差を見たい場合に向いています。
・比較的短期間・低コストで実施可能で、ニッチなターゲットにもアプローチしやすいのが特長です。
・複数のコンセプト案をスコアで比較したい場合や、ターゲットごとの傾向差を見たい場合に向いています。
グループインタビュー
・消費者の深層心理や行動の背景を探るのに適しています。
・想定外のアイデアや“気づき”を得られることもあり、定量調査では拾えない洞察を引き出せます。
・想定外のアイデアや“気づき”を得られることもあり、定量調査では拾えない洞察を引き出せます。
グループインタビューとは?調査の流れやメリット・デメリットを徹底解説

グループインタビューは、複数の参加者を集めて座談会形式で行う調査で、定性調査の一つです。対象者の心理や行動の背景を理解するために使われ、ペルソナやカスタマージャーニーマップの作成、仮説の構築などに役立ちます。
CLT(会場テスト)・HUT(ホームユーステスト)
CLT(Central Location Test)やHUT(Home Use Test)は、コンセプトを試作品として具体化できる場合に有効な調査手法です。
・CLT:特定の会場に参加者を集めて、同一条件下で商品やサービスを体験・評価してもらう手法です。使用環境を統一できるため、比較のしやすさや再現性の高さが特長です。
・HUT:商品を実際に自宅で使ってもらい、生活の中での自然な反応や使用感を収集する手法です。よりリアルな評価が得られる反面、家族や同居人の意見が影響する可能性があるため、事前に調査設計で留意が必要です。
・CLT:特定の会場に参加者を集めて、同一条件下で商品やサービスを体験・評価してもらう手法です。使用環境を統一できるため、比較のしやすさや再現性の高さが特長です。
・HUT:商品を実際に自宅で使ってもらい、生活の中での自然な反応や使用感を収集する手法です。よりリアルな評価が得られる反面、家族や同居人の意見が影響する可能性があるため、事前に調査設計で留意が必要です。
オンライン調査のメリットと注意点
近年主流のオンライン調査(Webアンケート)には、以下のような利点があります。
・回答収集のスピードが速く、コストも抑えられる
・地域や属性を問わず、幅広い生活者にアプローチできる
・セルフ型ツールを活用すれば、柔軟な設問設計と分析が可能
一方で注意すべき点もあります。
・回答精度や信頼性は設問設計や対象者管理の工夫が必要
・コンセプトの表現がWeb上に限定されるため、実物の印象と差が出ることもある
これらを踏まえ、調査目的に応じてオンライン/対面調査を使い分ける設計が大切です。
・回答収集のスピードが速く、コストも抑えられる
・地域や属性を問わず、幅広い生活者にアプローチできる
・セルフ型ツールを活用すれば、柔軟な設問設計と分析が可能
一方で注意すべき点もあります。
・回答精度や信頼性は設問設計や対象者管理の工夫が必要
・コンセプトの表現がWeb上に限定されるため、実物の印象と差が出ることもある
これらを踏まえ、調査目的に応じてオンライン/対面調査を使い分ける設計が大切です。
対象者(調査パネル)の選定ポイント
受容性調査では、誰に評価してもらうか=対象者の設計も極めて重要です。
また、LTV(顧客生涯価値)やロイヤリティの高低で層別して評価傾向を比較すれば、より深い示唆が得られます。
セルフ型アンケートツール「サーベロイド」では、ロイヤリティごとのセグメント抽出も可能なため、目的に合わせた精度の高い調査設計が実現できます。
また、LTV(顧客生涯価値)やロイヤリティの高低で層別して評価傾向を比較すれば、より深い示唆が得られます。
セルフ型アンケートツール「サーベロイド」では、ロイヤリティごとのセグメント抽出も可能なため、目的に合わせた精度の高い調査設計が実現できます。
新商品開発フェーズでの対象者
・想定ターゲット層(年齢・性別・ライフスタイル)
・類似カテゴリ商品の購入経験者や、関心が高そうな層
・類似カテゴリ商品の購入経験者や、関心が高そうな層
商品改良・再評価フェーズでの対象者
・既存顧客(利用経験者・ロイヤル層)
・競合商品のユーザー
・競合商品のユーザー

受容性調査の具体的な実施手順
受容性調査を効果的に行うには、事前の設計から結果の活用までを計画的に進めることが重要です。ここでは、実施の流れを6つのステップに分けて紹介します。
ステップ1:ゴールの設定
まずは、「何のために調査を行うのか」=目的と活用シーンを明確にします。
例として、「複数のコンセプトから最も支持される案を選定したい」「改善ポイントを把握してブラッシュアップしたい」といったゴールが考えられます。
ゴールが定まったら、以下のような調査設計の基本項目を整理しましょう。
・調査の目的と活用方針
・調査手法(定量/定性/CLT・HUTなど)
・対象者属性・人数
・実施時期・期間
・必要な準備物(例:試作品、動画など)
・予算と実施体制(社内・外注)
対象者のリクルートは、自社保有の顧客リストやSNS、調査会社のパネルを活用して行います。
例として、「複数のコンセプトから最も支持される案を選定したい」「改善ポイントを把握してブラッシュアップしたい」といったゴールが考えられます。
ゴールが定まったら、以下のような調査設計の基本項目を整理しましょう。
・調査の目的と活用方針
・調査手法(定量/定性/CLT・HUTなど)
・対象者属性・人数
・実施時期・期間
・必要な準備物(例:試作品、動画など)
・予算と実施体制(社内・外注)
対象者のリクルートは、自社保有の顧客リストやSNS、調査会社のパネルを活用して行います。
ステップ2:コンセプトの整理・リスト化
次に、評価したい商品・サービスのコンセプトを具体化し、生活者に提示する内容をリスト化します。コンセプト文は端的かつわかりやすく、誰でも理解できる表現を意識することが重要です。
主な評価対象の例:
・理解度(内容が伝わったか)
・新奇性(目新しさを感じたか)
・興味・魅力(惹きつけられたか)
・信頼度(信頼できそうか)
・購入意欲(試してみたいと思ったか)
・自由記述(気になった点、期待、利用シーンなど)
※定性調査やCLT/HUTの場合は、体験後の感想や使用感への言及も含めるとより深い示唆が得られます。
主な評価対象の例:
・理解度(内容が伝わったか)
・新奇性(目新しさを感じたか)
・興味・魅力(惹きつけられたか)
・信頼度(信頼できそうか)
・購入意欲(試してみたいと思ったか)
・自由記述(気になった点、期待、利用シーンなど)
※定性調査やCLT/HUTの場合は、体験後の感想や使用感への言及も含めるとより深い示唆が得られます。
ステップ3:質問項目の設計
評価軸が定まったら、それに基づく設問の設計を行います。特に定量調査では、5段階評価などを用いたスコアリング形式が一般的です。
設問設計のポイント:
・各評価項目について、選択式+自由回答を組み合わせる
・複数コンセプトがある場合は比較設問(どちらが魅力的かなど)を設ける
・属性情報(年齢・性別・購入頻度など)も取得し、分析の軸にできるようにする
調査票は回答者が理解しやすく、直感的に答えられる構成にすることが重要です。
設問設計のポイント:
・各評価項目について、選択式+自由回答を組み合わせる
・複数コンセプトがある場合は比較設問(どちらが魅力的かなど)を設ける
・属性情報(年齢・性別・購入頻度など)も取得し、分析の軸にできるようにする
調査票は回答者が理解しやすく、直感的に答えられる構成にすることが重要です。
ステップ4:調査の実施と回収
調査票が完成したら、実査(調査の実施)に進みます。オンライン調査であれば配信と同時に回答が集まり始めるため、進捗状況をモニタリングしながら適切に回収を管理します。
調査実施のチェックポイント:
・ターゲット層の条件に沿って回答が集まっているか
・回答数が想定に達しているか
・不適切な回答(極端な偏りや未入力)が含まれていないか
調査実施のチェックポイント:
・ターゲット層の条件に沿って回答が集まっているか
・回答数が想定に達しているか
・不適切な回答(極端な偏りや未入力)が含まれていないか
ステップ5:結果の集計と分析
回収されたデータをもとに、目的に応じた分析を行います。
・各コンセプトの受容スコア(総合評価・個別項目ごと)
・ターゲット別の反応差(年代・性別など)
・コンセプト間の比較(支持が高い/低い案)
・自由記述の傾向把握(不安点・期待値など)
想定ターゲットとは異なる層が好反応を示す場合もあるため、新たな発見やサブターゲットの可能性にも着目します。
・各コンセプトの受容スコア(総合評価・個別項目ごと)
・ターゲット別の反応差(年代・性別など)
・コンセプト間の比較(支持が高い/低い案)
・自由記述の傾向把握(不安点・期待値など)
想定ターゲットとは異なる層が好反応を示す場合もあるため、新たな発見やサブターゲットの可能性にも着目します。
ステップ6:レポート作成と活用方法の検討
最後に、分析結果をもとにレポートを作成し、社内外での活用を進めます。
・調査の背景と目的
・主なファインディングス(評価の高いコンセプト、改善点など)
・推奨アクション(どの案で進めるか、どう改善するか)
定量結果だけでなく、自由回答や定性コメントも引用することで、説得力と納得感のある資料に仕上がります。社内の開発会議や経営層へのプレゼン、外部パートナーとの共有にも有効です。
・調査の背景と目的
・主なファインディングス(評価の高いコンセプト、改善点など)
・推奨アクション(どの案で進めるか、どう改善するか)
定量結果だけでなく、自由回答や定性コメントも引用することで、説得力と納得感のある資料に仕上がります。社内の開発会議や経営層へのプレゼン、外部パートナーとの共有にも有効です。

受容性調査の設問例と評価指標
受容性調査を効果的に実施するためには、調査目的に合った評価指標の設定と、回答しやすい設問設計が欠かせません。ここでは、代表的な評価軸と設問設計のポイント、さらには高度な分析に活用できる手法もご紹介します。
代表的な評価軸(新奇性・信頼性・購入意欲など)
受容性を測る際には、商品やサービスのどのような要素が「受け入れられるか」を多面的に捉える必要があります。以下は、コンセプト評価でよく用いられる主要な評価軸です。
設問設計のポイントと自由回答の使い方
定量調査における設問設計では、以下の点に配慮することで回答者の離脱を防ぎ、質の高いデータ収集が可能になります。
設問設計の基本ポイント
・1設問1評価項目を原則とし、冗長な複合質問は避ける
・「○○と感じましたか?」→「とてもそう思う〜全くそう思わない」で回答誘導を防ぐ
・複数コンセプトを比較する場合は、一貫した尺度・順序で提示
自由回答の活用方法
定量データだけでは見えない“なぜそう感じたか”の背景を探るには、自由回答が有効です。
たとえば、
・「最も印象に残った点は何ですか?」
・「気になった点・不安に感じた点を自由にご記入ください」
・「使用シーンを具体的に想像して記述してください」
こうした回答は、改良のヒントやインサイト発見の素材になります。
設問設計の基本ポイント
・1設問1評価項目を原則とし、冗長な複合質問は避ける
・「○○と感じましたか?」→「とてもそう思う〜全くそう思わない」で回答誘導を防ぐ
・複数コンセプトを比較する場合は、一貫した尺度・順序で提示
自由回答の活用方法
定量データだけでは見えない“なぜそう感じたか”の背景を探るには、自由回答が有効です。
たとえば、
・「最も印象に残った点は何ですか?」
・「気になった点・不安に感じた点を自由にご記入ください」
・「使用シーンを具体的に想像して記述してください」
こうした回答は、改良のヒントやインサイト発見の素材になります。
PSM分析やコンジョイント分析の活用例
より高度な設問設計や分析を行いたい場合、以下のような手法も併用できます。
PSM分析(Price Sensitivity Meter)
価格受容性を測る手法で、以下4つの価格評価を回答してもらい、妥当と感じる価格帯=許容価格ゾーンを導き出します。
・高すぎて購入しない価格
・高いが購入を検討する価格
・安いが品質が不安な価格
・妥当で購入意欲が高まる価格
コンセプトの評価と組み合わせることで、「この魅力ならいくらまで出せるか」が見えてきます。
コンジョイント分析
複数の属性(例:機能、デザイン、価格)を組み合わせたパターンを提示し、どの要素が購買意向に影響を与えているかを定量的に把握できる手法です。
たとえば、
・A案:ナチュラル成分・香り控えめ・価格1,200円
・B案:高保湿・フローラル・価格1,500円
どちらを選ぶかを複数回答させ、重要視される属性(=価値要因)を明らかにすることが可能です。
PSM分析(Price Sensitivity Meter)
価格受容性を測る手法で、以下4つの価格評価を回答してもらい、妥当と感じる価格帯=許容価格ゾーンを導き出します。
・高すぎて購入しない価格
・高いが購入を検討する価格
・安いが品質が不安な価格
・妥当で購入意欲が高まる価格
コンセプトの評価と組み合わせることで、「この魅力ならいくらまで出せるか」が見えてきます。
コンジョイント分析
複数の属性(例:機能、デザイン、価格)を組み合わせたパターンを提示し、どの要素が購買意向に影響を与えているかを定量的に把握できる手法です。
たとえば、
・A案:ナチュラル成分・香り控えめ・価格1,200円
・B案:高保湿・フローラル・価格1,500円
どちらを選ぶかを複数回答させ、重要視される属性(=価値要因)を明らかにすることが可能です。
コンセプト受容性調査のスケジュールと費用相場
コンセプト受容性調査を検討する際、「どれくらいの期間がかかるのか?」「費用はどれくらいかかるのか?」という疑問はつきものです。ここでは、調査手法別のスケジュール感と費用の目安、コストを抑えるための工夫についてご紹介します。
調査規模に応じたスケジュール例(簡易型〜本格型)
調査の内容や手法によって、実施にかかる期間は異なります。以下は、代表的な3パターンのスケジュール例です。
【インターネット定量調査】 1.5か月~
・調査企画・設計 1週間~
・調査票作成~確定 1週間~
・調査画面作成~実査 1週間~
・データ作成 / 集計表作成 3日~
・報告書作成 10日~
【グループインタビュー】 2か月~
・調査企画・設計 1週間~
・対象者リクルート・調査票作成~確定 3週間~
・実査準備・実査 1週間~
・データ作成・集計表作成 1週間~
・報告書作成 2週間~
【CLT・HUT】 2か月~
・調査企画・設計 1週間~
・対象者リクルート・調査票作成~確定 3週間~
・実査準備・実査 1週間~
・データ作成・集計表作成 1週間~
・報告書作成 2週間~
・調査企画・設計 1週間~
・調査票作成~確定 1週間~
・調査画面作成~実査 1週間~
・データ作成 / 集計表作成 3日~
・報告書作成 10日~
【グループインタビュー】 2か月~
・調査企画・設計 1週間~
・対象者リクルート・調査票作成~確定 3週間~
・実査準備・実査 1週間~
・データ作成・集計表作成 1週間~
・報告書作成 2週間~
【CLT・HUT】 2か月~
・調査企画・設計 1週間~
・対象者リクルート・調査票作成~確定 3週間~
・実査準備・実査 1週間~
・データ作成・集計表作成 1週間~
・報告書作成 2週間~
費用の目安と変動要因(対象者数、設問数など)
費用は、調査手法・対象者数・設問数・外部委託範囲によって大きく変動します。以下はあくまで目安です。
【インターネット定量調査】
1000s/スクリーニング10問/本調査30問の場合
100万円~150万円程度
※セルフ型アンケートツール「Surveroid」活用の場合
2000s/スクリーニング10問/本調査10問400人の場合
6万円程度
1000s/スクリーニング10問/本調査30問の場合
100万円~150万円程度
※セルフ型アンケートツール「Surveroid」活用の場合
2000s/スクリーニング10問/本調査10問400人の場合
6万円程度
【グループインタビュー】
オンライングループインタビュー
4名×4グループ 計16人の場合
170万円~200万円程度
【CLT】
100名/15問(スクリーニングを含む)
100万円~200万円程度
オンライングループインタビュー
4名×4グループ 計16人の場合
170万円~200万円程度
【CLT】
100名/15問(スクリーニングを含む)
100万円~200万円程度
コストを抑える工夫とは?
調査費用を抑えるには、以下の工夫が有効です。
・セルフ型調査ツールの活用
→ 調査設計~配信・回収・集計を一元化でき、外注費を大幅削減
・設問数・対象者数の最適化
→ 「必要最低限の設問とセグメント」に絞ることで回答数と分析工数を抑制
・既存リストやオウンドメディアを活用した対象者リクルート
→ パネル費用をかけずに調査実施が可能
・報告書作成や集計を内製化/簡易化
→ 必要な指標に絞れば、報告書作成も省力化できます
コンセプト受容性調査は、コストをかけずに効果を得ることも十分に可能です。
目的に合わせて、「どこに予算をかけ、どこで効率化するか」を見極めることが成功のポイントです。
・セルフ型調査ツールの活用
→ 調査設計~配信・回収・集計を一元化でき、外注費を大幅削減
・設問数・対象者数の最適化
→ 「必要最低限の設問とセグメント」に絞ることで回答数と分析工数を抑制
・既存リストやオウンドメディアを活用した対象者リクルート
→ パネル費用をかけずに調査実施が可能
・報告書作成や集計を内製化/簡易化
→ 必要な指標に絞れば、報告書作成も省力化できます
コンセプト受容性調査は、コストをかけずに効果を得ることも十分に可能です。
目的に合わせて、「どこに予算をかけ、どこで効率化するか」を見極めることが成功のポイントです。
まとめ
コンセプト受容性調査は、商品やサービスのコンセプトが消費者や市場に受け入れられるかを確認する調査です。新商品開発時やブランドリニュアルなどの際に役立つ調査で、ローンチや再販前に失敗するリスクを軽減できるメリットがあります。
調査方法としては定量調査、グループインタビュー、CLT・HUTなどがあり、いずれにしても調査の目的に応じて新規性や関心度、ベネフィットなど、どの評価軸で質問項目を設計するかが重要です。また各調査共に調査会社に依頼すると企画~レポート納品まで1.5ヶ月~2ヶ月ほどかかり、費用も調査の規模によるものの100万円以上の出費となります。
コンセプト受容性調査の調査期間と費用を抑えたいなら、セルフ型アンケートツールの活用をおすすめします。自社で調査概要はコンセプトリストを作らなければならないものの、たとえばインターネットリサーチならアンケート画面作成、配信、集計まで全ての業務をWeb上で完結できるツールもあります。ぜひご検討ください。
調査方法としては定量調査、グループインタビュー、CLT・HUTなどがあり、いずれにしても調査の目的に応じて新規性や関心度、ベネフィットなど、どの評価軸で質問項目を設計するかが重要です。また各調査共に調査会社に依頼すると企画~レポート納品まで1.5ヶ月~2ヶ月ほどかかり、費用も調査の規模によるものの100万円以上の出費となります。
コンセプト受容性調査の調査期間と費用を抑えたいなら、セルフ型アンケートツールの活用をおすすめします。自社で調査概要はコンセプトリストを作らなければならないものの、たとえばインターネットリサーチならアンケート画面作成、配信、集計まで全ての業務をWeb上で完結できるツールもあります。ぜひご検討ください。
受容性調査をするならSurveroid
受容性調査を効率的に、かつ低コストで実施したいなら、セルフ型アンケートツールの「Surveroid(サーベロイド)」の活用がおすすめです。
Surveroidが選ばれる理由
・1問×1人×1円※から始められるシンプルかつ低価格な料金体系
・500万人以上のパネルから、目的に合ったターゲットを柔軟に抽出可能
・初心者でも安心の直感的なUIと充実したサポート体制
・定量調査も定性調査も対応可能(オプションでインタビュー実施も可)
・企画から分析・レポート支援までのオプションサービスも充実
「スピード」「コスト」「品質」のバランスが求められる現代のマーケティングにおいて、Surveroidは調査の内製化や検証サイクルの高速化を支援します。
Surveroidが選ばれる理由
・1問×1人×1円※から始められるシンプルかつ低価格な料金体系
・500万人以上のパネルから、目的に合ったターゲットを柔軟に抽出可能
・初心者でも安心の直感的なUIと充実したサポート体制
・定量調査も定性調査も対応可能(オプションでインタビュー実施も可)
・企画から分析・レポート支援までのオプションサービスも充実
「スピード」「コスト」「品質」のバランスが求められる現代のマーケティングにおいて、Surveroidは調査の内製化や検証サイクルの高速化を支援します。
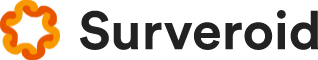 サーベロイドで受容性調査をしませんか?
サーベロイドで受容性調査をしませんか?
-
サービス概要・事例がわかる資料をダウンロードする
-
ターゲットの声を聴こう登録してみる(無料)
90 件








